《 次の「扉」は、気持ち悪さの先にある 》
―内省と問いが、脳を変えるとき —
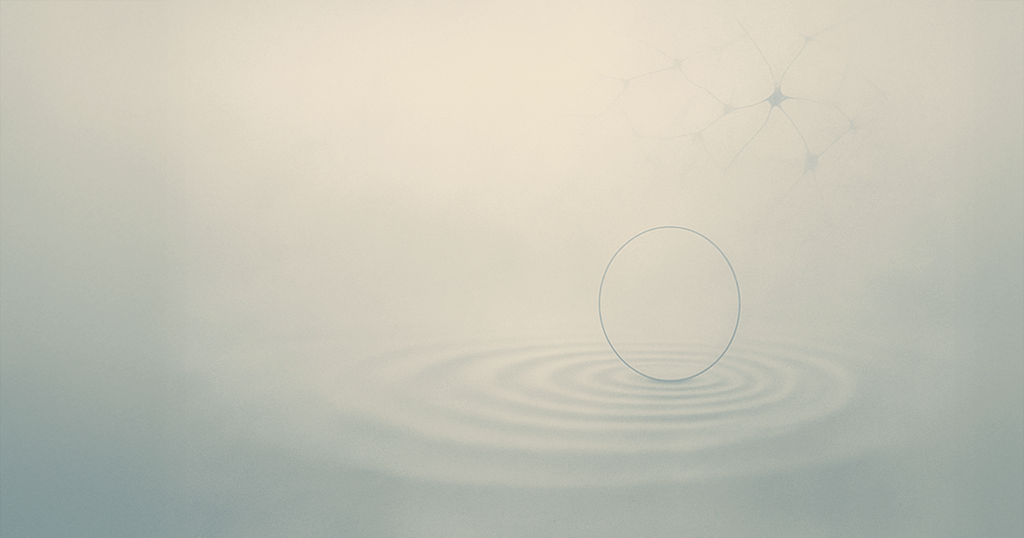
プロローグ:
人の厚みは、
答えをたくさん持っていることでは生まれない。
矛盾や違和感をそのまま抱え、
問いのままでいられる人に、
静かににじんでいくものだ。
脳は楽なルートを選びたがり、
見方や感じ方も気づかぬうちに固定化していく。
だからこそ、
違和感をごまかさず、
少しだけ留まる時間が必要になる。
このコラムは、
そんな揺れたままでいる自分に、
そっと寄り添うための話。
Vol.0|薄っぺらさは、その人だけの問題だろうか
「この人、なんだか薄っぺらいな」
そんなふうに感じたことは、誰にでもあるのではないだろうか。
表面的な言葉、借り物の思想、無理に整えた態度。
そうしたものに触れたとき、
私たちはどこか、軽さや薄さを嗅ぎ取ってしまう。
薄さがにじみ出る理由は、一つではない。
ときに、それはその人自身の内側の問題でもあり、
ときに、その人が置かれた場や関係性の影響でもある。
「わからない」と言えない空気や、
問いが立たない関係性にいると、
人は知らず知らずのうちに、薄さをまとってしまう。
同じように、問いや内省を手放し、
正解に寄りかかりすぎても、
厚みは自然と失われていく。
だからこそ、「内省」という営みを、
自分の内側にも、場にも根づかせられるか。
その問いから、この話を始めたい。
Vol.1|問いが立たないと、薄さがにじむ
■ 厚みは、目に見えないところに滲む
人の厚みは、言葉では説明しきれないものだ。
知識や経験、実績がどれだけあっても、
そこに厚みがあるかどうかは別の話になる。
逆に、目立つ肩書きがなくても、
不思議とその人から静かな重みや奥行きを感じることがある。
厚みというのは、もっと見えにくい場所、
つまり、その人が問いを持ち続けているかどうかに、
静かににじみ出てくるものだと思う。
問いを持つ人には、言葉の間や立ち居振る舞いに、余白がある。
揺れていい、と自分に許せているからだ。
矛盾や未整理なものを抱えたまま、
それでも前に進める人。
そんな姿勢そのものが、厚みとなって表れていく。
■ 問いが消えると、人は薄くなる
問いを持ち続けるのは、簡単なことではない。
特に、自分を取り巻く場や関係性によって、
問いは気づかぬうちに、静かに消えていく。
「わからない」と言いづらい空気の中で、
問いは立ちづらくなる。
正解や答えばかりが求められる場では、
揺れを抱えたままでいることは難しい。
そうして人は、問いを置き去りにし、
自分を守るために、薄さをまとい始める。
場が問いを許さなくなると、関係性も浅くなる。
浅さの中では、安心を装うために、
軽い言葉や借り物の態度が増えていく。
結果として、人の輪郭も、
どこか平面的に見えてしまう。
■ 自分自身の内側も、問いを拒むことがある
問いが消えていくのは、
場や関係性のせいだけではない。
自分の内側でも、
問いを遠ざけたくなる瞬間がある。
「もう、わかってしまったことにしたい」
「揺れ続けるのは、しんどい」
そんな感覚が、誰の中にもある。
問いを持ち続けるというのは、
常に安心から遠ざかる営みでもある。
不確かさと一緒にいる時間は、決して楽ではない。
けれど、その時間を避け続けることで、
人は薄さをまとうことに、知らず知らず慣れていく。
■ 厚みは、問いが立つ余白の中に生まれる
問いを持ち続けられるかどうかは、
自分の在り方と、場や関係性、
その両方に影響される。
厚みとは、問いが消えずに残り続けている人に、
静かににじみ出てくるもの。
そして、問いが立つ余白を失わない場や関係こそが、
その人の厚みを育てる土壌になる。
問いのある場所、問いを許せる自分。
それを少しずつ取り戻していくことが、
薄さから距離を置く、最初の入り口なのだと思う。
Vol.2|内省は、スッキリさせないための営み
■答えを急ぐと、厚みは消えていく
違和感を覚えたとき、
人はつい答えを出したくなる。
白黒をはっきりさせて、
スッキリしたいと思ってしまうのは、
ごく自然な反応だ。
自分の中に、曖昧なものや、
はっきりしないものが残り続けるのは、
居心地が悪い。
ただ、
その居心地の悪さをすぐに埋めようとすると、
問いは立たなくなる。
問いが立たなければ、厚みは育たない。
曖昧さを放置できる人だけが、
問いを抱え続けられる。
問いを抱え続けられる人だけが、
厚みを滲ませていく。
安心したい、スッキリしたいという感情に、
すぐ飛びついてしまうと、
そのまま人は、薄く軽くまとまってしまう。
内省は、
その衝動を少し脇に置き、
揺れたままでいられる時間を持つことでもある。
■ 脳が“スッキリ”を求めたがる理由
そもそも、
私たちの脳は、違和感や曖昧さを嫌う仕組みになっている。
脳は常に、世界を予測しながら処理しているからだ。
人と会話をするとき、
仕事をするとき、
日常のあらゆる場面で、
私たちは無意識のうちに
「こうなるだろう」と予測を立てている。
たとえば
- 「この人は、こういう反応をするはずだ」
-
「この行動をしたら、こういう結果が返ってくるだろう」
そうした予測が外れると、
脳はエラー信号を発する。
このときに生まれるのが、
違和感やモヤモヤ、不安といった感覚だ。
■ 予測が外れた瞬間こそ、厚みの入り口
予測が外れると、人は不快になる。
その不快をすぐに埋めたくなるのは、脳の構造として自然なことだ。
ただ、
その不快をすぐに埋めてしまうと、
自分の見方や感じ方は、今までの回路のまま変わらずに繰り返される。
逆に、
不快なまま少しだけ留まることができたとき、
脳は「新しい理解が必要だ」と判断し、
回路を組み替えようとし始める。
この仕組みを
予測符号化理論(Predictive Coding)
と呼ぶ。
内省とは、
この「気持ち悪さ」をただの不快で終わらせず、
問いとして抱え続ける時間を持つ営みでもある。
■ スッキリしなくても、問いが残っていればいい
すぐに答えを出せなくてもいい。
問いが残っていることそのものが、厚みに繋がっていく。
スッキリしなさを抱えたまま進むことができるかどうかが、
内省の質を大きく左右する。
安心のために、問いを消すのは簡単だ。
問いを残す勇気を持つことは、
厚みを育てるために欠かせない時間でもある。
内省は、
自分の中の矛盾や違和感と、すぐに手打ちしないための営みだ。
その不安定さの中でしか、
人の厚みは、静かににじんでこないのだと思う。
Vol.3|エラー信号を、すぐに埋めなくてもいい
■ 脳は“省エネ”で世界を処理している
私たちの脳は、常に膨大な情報を処理している。
そのすべてを一から丁寧に受け止めていては、とても追いつかない。
だから脳は、省エネのために
「こうなるはずだ」という予測を立て、
実際の出来事と照らし合わせながら、世界を理解している。
この仕組みについては、前の章でも少し触れた。
脳は、これまでの経験や、無意識の思い込みをベースに、
目の前の世界を「だいたいこんなものだろう」と理解しようとする。
そのおかげで、私たちは効率よく物事を判断できる。
ただ、この “だいたい” が外れたとき、
脳は違和感を覚える。
そしてその違和感は、
不快感やモヤモヤ、不安というかたちで、
意識に浮かび上がってくる。
■予測が外れると、脳はエラー信号を出す
たとえば、こんな場面を思い浮かべてほしい。
「この人は、こう返してくれるだろう」
と思って話しかけたのに、全く違う反応が返ってくる。
「こうすれば、こういう結果が出るはずだ」
と行動したのに、思い通りにならなかった。
こうした瞬間、脳の予測は外れ、エラー信号が発せられる。
これが、私たちが感じる違和感や不安、モヤモヤの正体だ。
エラーが生じたとき、脳は警戒する。
「何かがおかしい」「危険かもしれない」と、無意識に構え始める。
だからこそ、人は違和感を “異常” だと感じやすい。
その不快を、すぐに埋めたくなるのも、自然な反応だ。
■ 不快をすぐに埋めてしまうと、見方は変わらない
違和感を覚えたとき、多くの人は
その不快をすぐに埋めようとする。
たとえば:
- 自分の中で無理やり解釈を加え、すべて納得したことにしてしまう
- 相手や環境を、単純に「正しい」「間違っている」で整理しようとする
こうした行動は、一時的な安心感をもたらす。
ただ、その安心の裏側では、脳の回路は今まで通りのまま変わらず、
自分の見方や感じ方も、固定化されたままになる。
■ エラー信号は、脳が変わる入口でもある
脳は、エラーが生じたときにこそ、
「新しい理解が必要だ」と判断する仕組みを持っている。
このとき、脳の中では変化の準備が始まっている。
もし不快感や違和感をすぐに埋めず、
しばらくそのまま留まることができれば、
脳は、これまでの理解や回路では足りないと気づき、
新しい神経接続を探し始める。
このプロセスを経て、
脳は見方や感じ方を、柔らかく組み替えていく。
これが、次章で触れる
シナプスの新生や神経可塑性につながっていく。
■ 気持ち悪さに留まれる人は、厚みがにじむ
違和感を感じたとき、
すぐにスッキリさせようとせず、
問いのまま抱えていられる人には、
自然と厚みがにじんでいく。
矛盾や未整理なものを、そのまま抱えたままでいる姿勢は、
見方や感じ方の固定化を防ぎ、
自分自身を少しずつ柔らかく変えていく。
違和感は、脳が進化しようとする合図でもある。
すぐに埋めなくてもいい。
そのまま少しだけ、その場所に留まってみること。
それだけで、
脳も、自分の見方も、静かに変わり始める。
Vol.4|脳は、不快から組み替わる
■ 新しい理解は、違和感の中から始まる
違和感やモヤモヤ、不快感。
こうした感覚は、できれば避けたいものとして扱われがちだ。
ただ、脳の仕組みを見つめていくと、
むしろその不快こそが、
見方や感じ方を変えるための入り口になることがわかる。
脳は、予測が外れたときに「エラー信号」を発する。
それをすぐに埋めずに、
しばらく抱えたままでいられたとき、
脳は、今までの理解や回路では足りないと判断する。
その瞬間から、
脳の内部では、静かな組み替えが始まっている。
■ シナプスの新生と神経可塑性
脳の組み替えを支えているのが、
シナプスの新生と神経可塑性(プラスティシティ)という仕組みだ。
シナプスとは、神経細胞(ニューロン)同士をつなぐ接続部分のこと。
私たちが新しいことを学んだり、
考え方を柔らかく変えたりするとき、
このシナプスが新しく生まれたり、つながり方が変わったりする。
この柔軟な変化を、神経可塑性と呼ぶ。
違和感や不快感に少しだけ留まることで、
脳は「新しい理解が必要だ」と判断し、
シナプスの新生が促され、
見方や感じ方を変える準備が整っていく。
つまり、厚みは、不快を避け続けることで手に入るものではない。
むしろ、不快なまま、問いのまま留まる時間の中で、
静かに脳が組み替わり、見方に奥行きが生まれていく。
■ 違和感を避けることは、変わらないことを選ぶこと
違和感やモヤモヤを感じたとき、
その不快をすぐに埋めたくなる気持ちは、ごく自然なことだ。
ただ、そこで踏みとどまれるかどうかが、
見方や感じ方を変えられるかどうかの、分かれ道になる。
すぐに結論を出し、
既存の理解のまま物事を処理すれば、脳は楽ができる。
その分だけ、自分の輪郭や視点は、変わらずに固まっていく。
変わらないことを選ぶのは、安心を得るためには便利だ。
ただ、その安心の裏側では、
厚みは、静かに失われていく。
■ 気持ち悪さを、育てる時間に変える
違和感やモヤモヤに留まれる人は、
脳の仕組みそのものを、味方につけている。
問いのまま抱え、
気持ち悪さをごまかさずにいられる人には、
自然と見方の柔らかさと、言葉の奥行きがにじんでいく。
安心を求めすぎず、問いを残すこと。
不快をすぐに埋めず、違和感に少しだけ留まること。
その時間の中で、
脳も、自分も、静かに組み替わっていく。
Vol.5|自分の見方は、自分で選んでいるとは限らない
■ 見方や感じ方は、思っているより自動的にできている
「自分はこう感じる」
「私はこう考える」
そうした見方や感じ方を、
私たちは“自分自身”だと思いがちだ。
ただ、脳の仕組みを見つめていくと、
その実感も、少しずつ揺らいでくる。
脳は、これまでの経験や環境の中で、
無意識に回路を組み替えてきた。
違和感に留まれたときは、新しい回路が生まれ、
反対に、不快をすぐに埋めてしまったときは、
今までと同じ回路が、強化されていく。
そうしてできあがった回路が、
私たちの見方や感じ方の“下地”になっている。
つまり、今の自分の見方や感じ方は、
すべて自分が意識的に選び取ったものとは、限らないということだ。
■ 脳は「楽なルート」を選びたがる
脳は、省エネのために
“楽なルート”を好む。
見方や感じ方も、
その影響を強く受けている。
この“楽なルート”の下には、
気づかないうちに積み重なった
無自覚の前提が横たわっている。
たとえば:
- 今までと同じ考え方や価値観で、
物事を理解しようとする - 自分にとって安心できる情報だけを集めて、
違和感を無視する - 同じような考え方の人とばかり、
つながろうとする
こうした行動は、
無意識のうちに「楽なルート」に
乗っかっている状態だ。
■ 固定化に気づけるかどうかが、厚みの分かれ道
見方や感じ方が
完全に自分の意思だけで決まっていると思い込んでいると、
違和感や問いに耳を傾ける余白がなくなる。
反対に、
自分の見方や感じ方が、
無意識の回路の影響を受けていると気づけたとき、
少しだけ立ち止まることができる。
「これは本当に自分が選んだ見方なのか?」
「脳の楽なルートに、ただ乗っかっているだけじゃないのか?」
そんな問いが立つ瞬間、
自分の厚みを取り戻す小さな入り口が生まれる。
■ 無自覚の前提に、違和感が入り込む
自分の見方や感じ方は、
脳の“楽なルート”に沿って形づくられていく。
そして、そのルートの下には、
たいてい無自覚の前提が横たわっている。
「こういうものだろう」
「こうあるべきだ」
「これは正しい」
そうした前提が、
自分の内側に知らず知らず積み重なり、
その上に、今の見方や感じ方がのっている。
問いを持ち続けることや、
違和感に留まることは、
そうした無自覚の前提を一枚ずつ剥がし、見直していくための時間でもある。
自分の見方を、完全にコントロールすることはできなくても、
無自覚の前提に気づけるだけで、
見方や感じ方は少しずつ変わっていく。
その営みの中にしか、
自分の厚みは育たないのだと思う。
Vol.6|問いのまま、揺れている自分でいい
違和感や問いを抱えたまま進むのは、落ち着かないものだ。
つい答えを出したくなったり、正しさにしがみつきたくなったりする。
不快をすぐに埋めてしまえば、安心は手に入る。
ただ、その安心と引き換えに、見方や感じ方は硬くなり、
自分の厚みは、静かに失われていく。
だから私は、揺れている自分を、そのまま許したいと思う。
問いのまま、違和感のまま、曖昧さと一緒にいる時間が、
見方や感じ方を静かにほぐしていく。
自分の中に無自覚の前提があることを忘れずに、
気づき続けることを手放さない。
厚みは、答えを持つことで生まれるものではない。
むしろ、問いのままでいられる強さと、揺れたままでいられる余白の中に、
少しずつにじんでいくものなのだと思う。
今すぐスッキリしなくてもいい。
気持ち悪さをごまかさず、そのまま抱えて歩いていくこと。
その営みそのものが、静かに自分を変えていく時間になる。