《 カテゴライズの罠 》
- わからなさを奪う「わかったつもり」 -
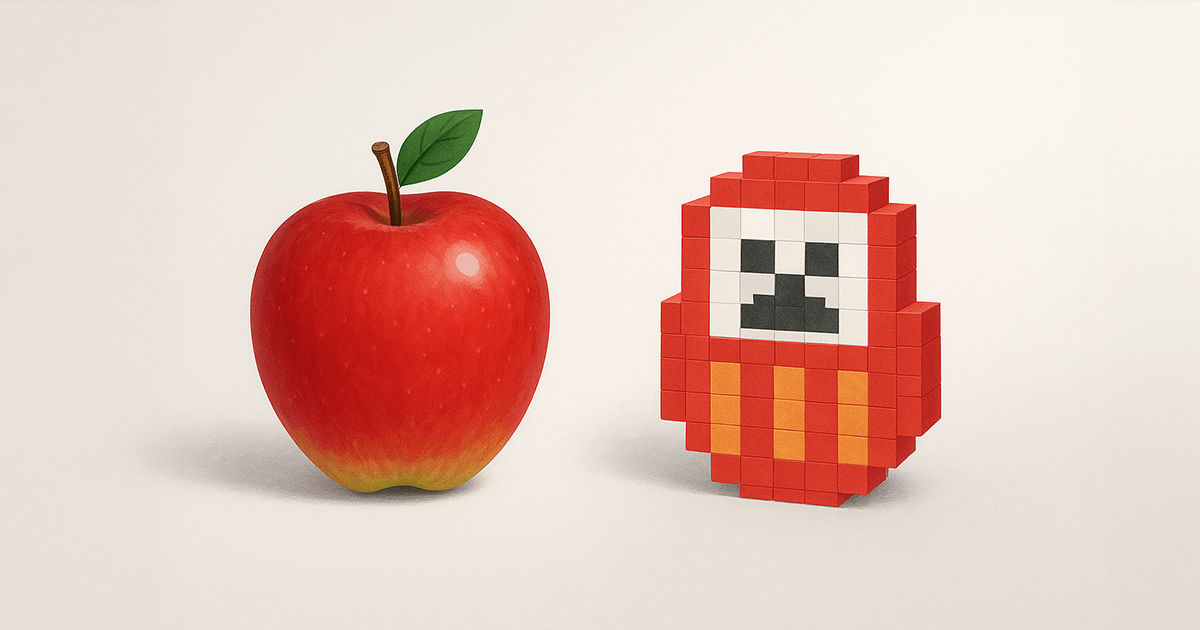
プロローグ:
人は「わからない」に直面すると、すぐに既知の枠に押し込もうとする。
曖昧さに耐えるより、「わかったつもり」で安心したいからだ。
血液型や診断テストはその好例であり、社会もまた「結論を出さない態度」を許さない。
しかし、明晰さとはすべてをはっきりさせることではない。
むしろ、はっきりしないものをはっきりしないまま見続ける力にある。
本稿では、カテゴライズの罠を通して、わからなさとともにいる可能性を探っていく。
Vol.0|赤いものを前にして
— 「わからない」に耐えられるか -
このコラムは、師匠がかつてSNSに投稿した一枚の画像から始まる。
赤いりんごと赤いだるま。
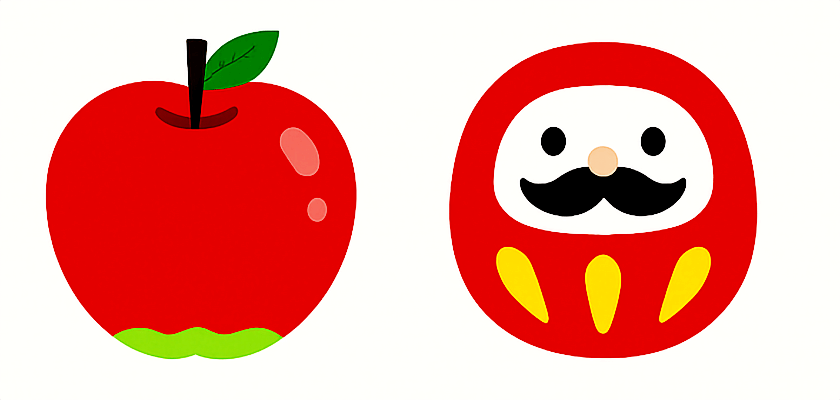
同じ色をしていても、まったく違うものだ。
りんごは、これまでの経験の中にあって「知っているもの」の象徴。
だるまは、経験の外にあり「知らないもの」の象徴。
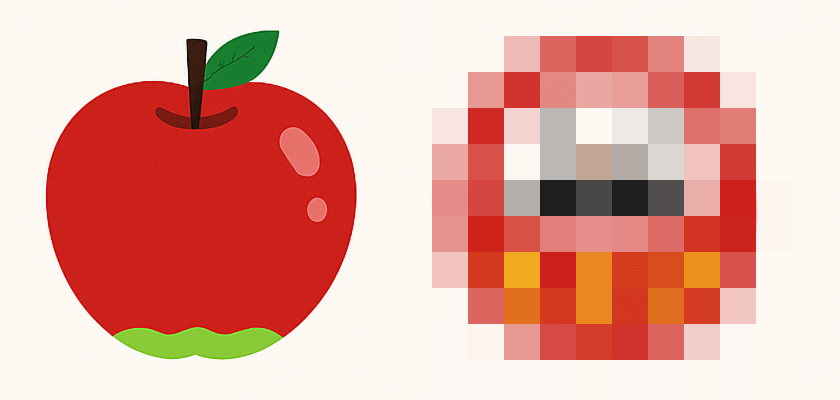
説明を聞いても、どこかはっきりせず、曖昧さが残る。
このとき、人はだるまを「りんごのようなものだ」と思い込もうとする。
はっきりしないことに耐えられず、知っている枠(赤いと既に知っている“りんご”)に回収してしまうのだ。
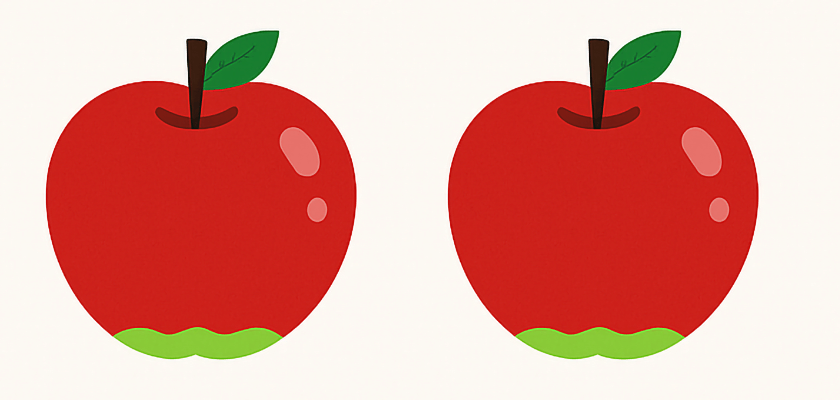
だが実際には、ぼやけただるまを“だるま(わからないもの)”として見ている方が、理解に近い。
「りんごだ」と決めつけた瞬間、その存在はもう観察されない。
明晰であるとは、すべてをハッキリさせることではない。
むしろ、ハッキリしないものをハッキリしないままに留めておくこと。
そこに、理解の可能性がひらかれている。
Vol.1|わかりやすさの誘惑
— ラベルが与える安心感 -
■ 盛り上がる会話の裏で
合コンや職場の雑談で、こんな場面は珍しくない。
「やっぱりA型でしょ?」「あ、当たった!」
血液型の話題は、それだけで場を和ませる。
MBTIの診断結果をシェアし合うのも同じだ。
「ああ、だから君はそうなんだね」と言える便利さがある。
■ きっかけとしてのラベル
こうしたタイプ分けは、会話の入口としては悪くない。
共通の話題になり、相手との距離を縮める助けにもなる。
ただ、その診断やラベルをその人そのものとして扱った瞬間に、複雑さは切り落とされてしまう。
■ 観察を止めるスイッチ
ラベルは便利さと同時に、危うさをはらんでいる。
「几帳面なはず」「破天荒なはず」と思った途端、その人の奥行きは消えてしまう。
「その人を見ている」のではなく、「カテゴリーをなぞっている」にすぎない。
同じことは自分にも起こる。
「私はO型だから大雑把」「内向型だから人付き合いが苦手」
そう言った瞬間に、自分の奥行きもまた削ぎ落とされる。
自分を見ているようで、実はラベルをなぞっているだけになる。
■ 本当に理解しているのか
ラベルは安心を与える。
だが「わかったつもり」になった瞬間に、その人の奥行きも、自分の奥行きも、観察の射程からこぼれ落ちていくのではないか。
Vol.2|増えつづけるラベル
— わからなさに耐えられない欲求 -
■ 解放と表現のあいだで
ジェンダーやセクシュアリティの領域では、LGBTQ+の頭文字に新しいラベルが加わり続けている。
もともと「カテゴライズからの解放」を願って始まった運動は、やがて「自分を説明できる枠を持ちたい」という欲求とも結びついていった。
ラベルはしばしば「居場所」として機能し、孤立していた人に言葉を与える。
■ 安心を求める動き
ラベルがあれば、言葉にしにくい経験を説明できる。
周囲も理解できた気になる。
複雑な現実に触れたとき、人は「わからないまま」に留まることが難しい。
ラベルの増加は、その安心を求める自然な動きだといえる。
■ 理解に近づいたのか
ただ、ラベルを増やすことが理解の深まりに直結するわけではない。
名前を付けた瞬間に「わかったつもり」になり、その先の観察を止めてしまう危うさが潜んでいる。
ラベルの増殖は、理解を進めると同時に、未知に向き合う機会を削いでしまう。
■ 曖昧さとともに
ラベルは肯定も否定もできない二重の性格を持つ。
重要なのは、ラベルの外に残りつづける曖昧さに気づいているかどうかだ。
その曖昧さを抱えたまま観察を続けること。
ラベルの増殖が示しているのは、まさにその難しさである。
Vol.3|親切の暴力
— 「わかるように」が奪うもの -
■ 親切そうに見える言葉
「小学生にもわかるように説明して」
この言葉は日常でよく耳にする。
一見すると親切で、理解を助けるように思える。
しかし、それは本当に小学生自身が求めていることだろうか。
■ 一方的な態度
「わかるようにしてあげる」という言い方には、相手を下に見てしまうまなざしが潜んでいる可能性がある。
相手の理解力を低く見積もり、こちらが補ってあげるものだと勝手に決めてしまう。
そこには、相互的な学びの関係性が欠けている。
■ 学びの本質
子どもは、意味を知らない言葉に出会っても、文脈の中で少しずつ推測し、やがて自分の言葉にしていく。
赤ん坊が言語を覚えるのも同じで、「わからないままに触れ続ける時間」こそが成長を育てる。
■ 奪われる機会
一方的に「わかる形」にしてしまうことは、その時間を奪う可能性がある。
観察や思考の芽を摘み、相手が自分でつかむはずのプロセスを断ち切ってしまう。
親切に見える態度の裏に、そんな危うさが潜んでいる。
Vol.4|「わからない」は罪なのか
— 曖昧さを拒む社会の力学 -
■ 許されない答え
「わからない」と答えることは、社会の中で歓迎されにくい。
学校では正解を即座に返すことが評価され、職場では結論を早く提示することが求められる。
問いを抱えたままでいることは、未熟や怠慢と見なされがちだ。
■ 迅速さへの圧力
スピードが重視される時代にあって、曖昧なままに留まる態度は不安を招く。
だからこそ人は、確かな既知の答えに飛びつきやすくなる。
安心を優先し、「わかったつもり」へと自らを追い込んでいく。
■ 観察が切り落とされる
しかし、安心のために早々に結論を出すことは、観察を続ける機会を奪うことでもある。
本当はまだ見えていないものを、「なかったこと」にしてしまう。
曖昧さを拒む力学が、理解を遠ざけてしまうのだ。
■ 社会にしみ込む構造
「わからない」を答えとして認めない空気は、制度や文化の中に深く組み込まれている。
それは誰か一人の態度というより、社会全体がつくりあげた構造といえる。
私たちはその中で、知らず知らず「観察を止めるスイッチ」を押しているのかもしれない。
Vol.5|わからなさと共にいる
— 明晰さの本質へ -
■ 安心よりも観察へ
「わからない」を「わかった」に変換するのは簡単だ。
安心できるし、効率もいい。
しかし、その瞬間に観察は止まり、世界の奥行きは切り落とされてしまう。
■ 曖昧さを抱える勇気
霧の中に立つように、輪郭の見えないものと共にいる。
その曖昧さを奪わず、「まだ見えきっていない事」として留める。
それは不安を伴うが、同時に想像力と信頼を育てる態度でもある。
■ 明晰さとは
明晰であるとは、すべてをはっきりさせることではない。
むしろ、はっきりしないものをはっきりしないまま受けとめられること。
そこで初めて、本当に見えてくるものがある。
■ 未来への問い
カテゴライズの罠を超えるのは、「わからない」を抱きながら問いを手放さずにいる勇気だ。
その勇気の先に、私たちがまだ知らない世界と出会う可能性がひらかれている。



