《 エンパシーはOS? 》
- 技術としての想像力と組織の感性 -
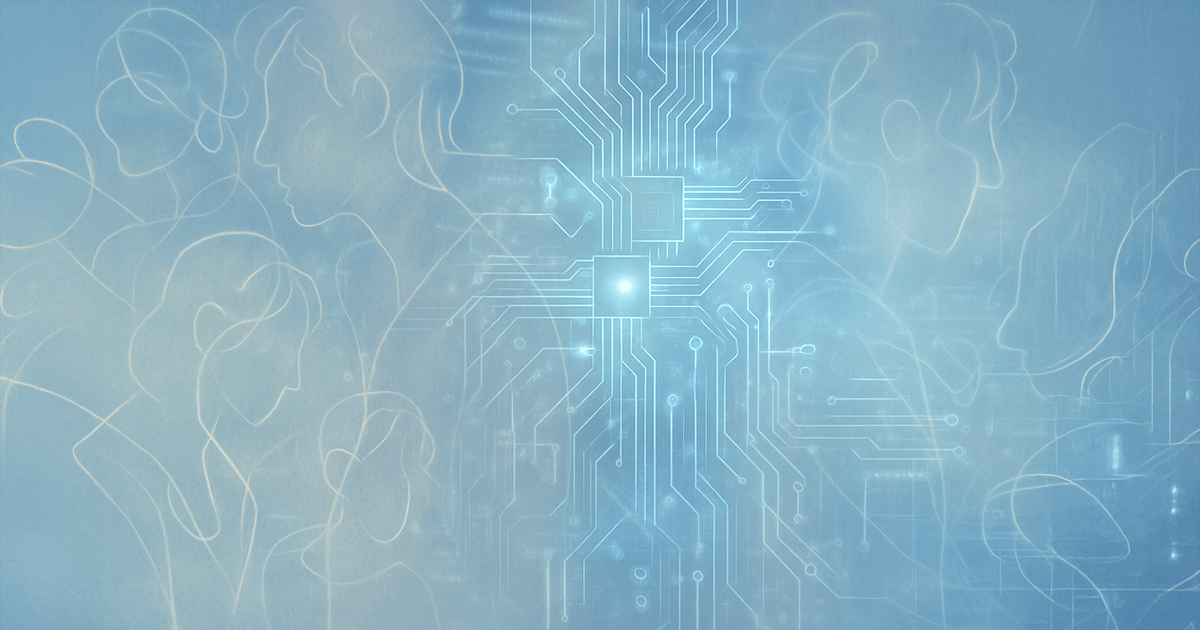
プロローグ:
わたしたちは、つい「わかり合うこと」に救いを求めてしまう。
しかし本当は、「わかろうとする」営みにこそ、希望はあるのかもしれない。
それは、技術であり、構造であり、祈りに近い姿勢だ。
感じることと問うことのあいだをたゆたいながら、
ときに設計という手つきで、それを手渡していく。
エンパシーというOSは、そんな静かな意志から起動する。
Vol.0|「共感の不自由さ
— 「わかろうとする」ことの意味 -
「わかり合う」ことではなく、
「わかろうとする」ことから始めたい。
——たとえ、それが一方的でも。
■ 共感という言葉が、すこし窮屈に思えるとき
「共感しています」「共感できました」
SNSでも、社内プレゼンでも、マーケティングのコピーでも。
あらゆる場所で交わされているこの言葉には、たしかに温度がある。
とはいえ、ときどき思うのだ。
この言葉のうしろには、“わかり合えたという錯覚”が
ひっそりと立っているんじゃないか、と。
それは、ほんとうに相手に近づいた感触なのだろうか?
それとも、「同じ感情を知っている」というラベルを貼って
安心してしまっただけなのだろうか?
■ エンパシーとシンパシー
英語では“共感”に、Empathy と Sympathy のふたつがある。
Sympathy は「同情」「感情の共有」
Empathy は「他者の内面に立ち入って、感じようとする力」
とはいえ、日本語ではどちらも「共感」としてひとまとめにされている。
ここに、ひとつの混線がある気がする。
「わたしもそうだったよ」と寄り添うこと。
それもたしかにやさしさだけれど、
もっと大切なのは、
「わたしには経験がないけれど、あなたの世界を想像してみる」ことじゃないだろうか?
Empathy とは、他者のまなざしを生き直す想像力だ。
■ 感性のインフラとしてのエンパシーOS
わたしたちがビジネスや組織に持ち込む「思考法」や「戦略」は、
どれも表面的なアプリケーションにすぎない。
その土台にあるのが、
“他者の内面とどう関わるか”というOSだ。
このOSがアップデートされないままでは、
どんなに流行のフレームワークを持ってきても、
思考も関係性も、どこかでノイズを起こしてしまう。
エンパシーは、「感性のインフラ」だ。
そしてそれは、感情に流されることではなく、
感情を丁寧に扱う技術でもある。
■ 「わかる」のではなく、「近づく」という営み
わたしたちは、誰かをほんとうに「わかる」ことなんてできない。
同じ痛みでも、同じ喜びでも、それを感じている背景はまったく違う。
だからこそ、「わかり合おう」とするほどすれ違うこともある。
でも、「わかろうとする」ことはできる。
その人の見ている風景、
その人の内側の天気に、そっと寄り添うこと。
そして、それは一方的でもいい。
報われなくても、通じなくても、それでいい。
マーケティングも、マネジメントも、家族も、社会も。
すべては「わかり合えたふり」から歪み始める。
わかろうとする営みだけが、関係を結び直す。
■ 「エンパシーOS」は、問いのOSでもある
問い続ける。想像しつづける。
その相手のなかに、まだ見えていない風景があると信じる。
そうした姿勢の積み重ねだけが、関係性の地層を深くしていく。
わたしはこの連載を通して、「役に立つ」ことの前にある、
「わかろうとする」という営みの可能性を見つめていきたい。
マーケティングにも、組織づくりにも、思想としてのエンパシーOSを。
それは、ひとを知ることの技術であり、愛し方の設計でもある。
Vol.1|エンパシーの本質
— OSとしての共感力 -
■“わかる”の正体を疑ってみる
「ちゃんと伝えたのに、なぜか伝わらない」
「共感してもらえなかった」
「上司はまるで人の気持ちがわかっていない」
コミュニケーションの不和の多くは、
“わかったつもり”と“わかられたつもり”のズレから始まる。
だけど本当は、
わかる/わからないというのは、そんなに明快なものじゃない。
それは、感情や体験の中にある“質”の問題であり、
他者の文脈に想像力を介して接続するという、
とても繊細なプロセスだ。
■ なぜ“スキル”ではないのか?
よく「共感力を高めよう」「傾聴のスキルを身につけよう」と言われる。
でも、ここで語りたいのは、それとはちょっと違う話。
わたしたちが提唱する「エンパシーOS」は、
会話のテクニックではなく、
“人を見る時のレンズの設計”そのものだ。
つまり、それはこういうことだ:
相手の発言を、どんな前提で解釈しているか?
自分の思い込みやバイアスに気づける構造になっているか?
その場の沈黙に、どう意味を与えるOSなのか?
スキルがアプリケーションなら、
OSは思考と感受性の根幹にある。
だから、「インストール」ではなく
「設計」として捉え直す必要がある。
■ フロムの“愛の技術”
エーリッヒ・フロムは『愛するということ』の中で、こう述べている。
「愛とは感情ではなく、技術である」
つまり愛とは、たまたま相手に惹かれた感情ではなく、
その人を見つめ続ける態度であり、訓練可能な営みであるということ。
エンパシーもまた、同じではないか?
自分のレンズを透明にして、相手の世界にふれる。
自分の中に“相手を映す余白”を持てるように、日々調律していく。
それは、感情の技術であり、
共に生きるための習慣であり、
OSのアップデートそのものだ。
■ 感性を組織に埋め込む
組織の中で「心理的安全性」が叫ばれるようになった。
でも、それを支えるのは施策ではなく、見えない感性のインフラだ。
意見を出せる空気
誤解を修正できる余白
上司が「わかってくれようとする」ことに対する信頼
これらは、数値化できないが、
組織の文化や成果に深く根を張っている。
つまり、「役に立つ」前に「わかろうとする」文化があるかどうかが、
土壌を決める。
■ 共感の技術としてのマーケティング
エンパシーOSは、組織内だけでなく、顧客との関係にも深く根ざしている。
マーケティングは単に「誰に・何を・どう届けるか」ではなく、
「誰の、どんな感情に、どう伴走するか」という営みである。
悩みを解決するだけでなく、
その人の内面の旅路にどう佇むかを意識すれば、
表現も体験設計もまったく異なる質を持つ。
それを可能にするのが、想像力という技術を支えるOS、すなわちエンパシーなのだ。
■ 「わかろうとする」ことをアップデートする
エンパシーはやさしさではない。
むしろ、とても厳しく、痛みを伴う技術だ。
自分が理解しているつもりのものが、
まったく異なる姿で現れることもある。
それでも、わたしはこのOSを信じたい。
マーケティングにも、組織づくりにも、
人と人の関係にも。
“正しさ”ではなく、
“わかろうとする姿勢”から生まれる可能性を。
Vol.2|想像力の育成
— 他者の世界に近づく技術 -
■ 「わかろう」とするのは、本能じゃない
人は本来、他人の内面を“本当に”理解できるわけではない。
相手の言葉を自分のフィルターを通し、
自分の経験に引き寄せて解釈してしまう。
それ自体が悪いわけではない。
しかし、そこから「わかっているつもり」になると、
コミュニケーションはズレていく。
だから、「エンパシー」は単なる感受性ではなく、
“意志”であり、後天的に育てられる技術だと考える。
■ 想像力、他者理解のリハビリ
たとえば、こんな問いを自分に立ててみる。
- この人の言葉は、どんな背景から生まれてきたんだろう
- なぜこの表現を選んだのか? どんな経験があるのか?
- 自分が同じ環境だったら、同じ反応をするだろうか?
これは「相手の立場になる」ことではない。
「相手の文化に触れる(世界を探る)」こと。
異国を旅するようなものだ。
自分の国の常識やルールをそのまま持ち込まず、
その土地の言葉で、その土地の暮らし方を生きてみる。
旅行のとき、わたしたちは自然とそうしている。
食べ方も、時間の感覚も、言葉のテンポも、その国に合わせる。
エンパシーも、それと同じだ。
自分の感性を一旦“横に置く”という勇気。
そこから初めて、他者の文化に“入国”する扉が開く。
■ 小さなエクササイズ:組織でできる「エンパシーの筋トレ」
ここからは、少し現場にも応用してみよう。
組織やチームの中で、こんな習慣を意識的に設計してみる。
▶【1】会話のあとに「自分の翻訳フィルター」を検証する
- 「わたしは、あの人の話を“どういう前提”で解釈したのか?」
- 「もしかして、〇〇というバイアスで聞いてなかったか?」
これは、自分の“OS設定”を点検する作業でもある。
▶【2】“事実”と“感情”を分けてフィードバックする
- 「事実としてこういう状況があって、それに対して私はこう感じた」
- 「あなたはどういうふうに感じたのか、教えてほしい」
これだけで、コミュニケーションの質がぐっと変わる。
▶【3】「想像する習慣」をチームに仕込む問いかけ
- 「この提案を、他部署の〇〇さんだったらどう受け取ると思う?」
- 「この言葉、相手の生活背景から見たらどう響く?」
“他者の風景に滞在する力”を、対話の中で鍛えていく。
■ 想像力の欠如は、時に暴力になる
エンパシーが欠けるとき、人は無意識に“傷つける側”になる。
わざとではなくても、
相手にとって見下しや無視、排除と受け取られる行動をしてしまう。
なぜなら、“相手がどう感じるか”を想像できていないから。
想像力とは、相手を守る防波堤だ。
エンパシーOSを育てることは、
見えない暴力を減らす営みでもある。
■ 想像することは、愛することに似ている
エーリッヒ・フロムの言葉を、もう一度借りるなら——
「成熟した愛とは、相手を理解しようとする意志に根ざしている」
エンパシーもまた、“わかりたい”という祈りのようなものだ。
完璧にはわからない。たどり着けないかもしれない。
それでも「そこに行こうとする」気持ちを、何度でも起動しなおす。
OSとしてのエンパシーは、その“わかろうとする起動ボタン”を、
毎日押せるように設計されているか?
そこにこそ、すべての始まりがある。
Vol.3|文化と共感
— 副組織に埋め込む感性-
■ 組織にインストールされる「無意識の文化」
組織には、「空気」のように漂う“感性のルール”がある。
それは、ルールブックには書かれていない。
けれど、誰もがそのルールに従って振る舞っている。
たとえば、
「忙しいのに、質問していいのかな?」
「言っても、どうせ変わらないよね…」
「ミスはすぐに指摘されるけど、頑張りはスルーされる」
こうした無言の文化は、“想像力の遮断”を引き起こす。
すると、人と人の間には、透明だけれど厚い壁ができていく。
■ エンパシーOSを文化として組み込むには?
エンパシーは「個人のセンス」ではなく、
組織の仕様にすることができる。
そのためには、次の3つのレイヤーで設計していく必要がある。
【1】対話の“しかけ”をつくる:偶然を必然にする
- 「部署を超えたコーヒーブレイク」
- 「1on1を“聞く練習”の場と定義しなおす」
- 「週1回の“問いだけ持ち寄るミーティング”」
偶発的な共感ではなく、
構造化された“共感の接点”を持つ。
【2】翻訳の文化を育てる:「伝える」より「解釈を合わせる」
- 「この表現って、別部署にはどう聞こえるかな?」
- 「この言葉、社外の人ならどう解釈する?」
これは、Vol.2で語った「異国を旅する視点」を、
チーム内に持ち込むということ。
“共通言語”ではなく、
“翻訳し合える文化”を育てる。
【3】制度に滲ませる:「優しさが報われる仕組み」
- 「フィードバックは感情の共有から始める」
- 「“気づいたことメモ”を報酬化する文化」
- 「思いやりが“見える化”される称賛制度」
想像力を働かせた人が、損をしない世界にしていく。
それが、エンパシーを継続可能な技術に変える。
■ 優しさを“組織コスト”にしない
よくある話だが、
「空気を読める人」や「気遣いができる人」ばかりが、
感情労働を引き受けて、どんどん消耗していく。
エンパシーは、そういう“優しい人”に依存するものであってはならない。
それは本来、組織がデフォルトで持つべきOSなのだ。
だから必要なのは、
「エンパシーが個人技ではなく、組織の仕様である」という前提をつくること。
■ 感性のインフラは、構造になると持続する
ここで改めて触れたい言葉がある。
「感性のインフラ」とは、
ふだん意識されないけれど、人と人の間を静かに支える“水脈”のようなもの。
その水脈を、「制度」や「習慣」や「文化」として可視化していくことで、
やさしさは循環しはじめる。
感性は、組織のパフォーマンスを上げる。
でも、それは「感性の見える化」と「構造への落とし込み」があってこそだ。
■ エンパシーは贅沢ではない。必要なOSである
「気を遣う余裕なんてない」
「そんなふうに丁寧に話せるほど、現場はヒマじゃない」
そんな声もあるだろう。
とはいえ、だからこそ言いたい。
“想像力のコスト”を削る組織は、結果として人が離れていく。
エンパシーは、贅沢品じゃない。
長く働ける環境、言葉が届く関係性、
自分を持って帰れるチームをつくるための、必須OSだとわたしたちは思う。
Vol.4|エンパシーの持続性
— 感性を育てる仕組み -
■ 共感は、消耗品ではない
共感は、燃やして終わる“やさしさ”ではない。
それは本来、循環させる水のようなものだ。
とはいえ現実の現場では、
“察する力”や“気づき力”がある人に偏っていき、
やがてその水路が枯れていく。
つまり、感じる力は、放っておくと枯れる。
だからこそ、組織には「感性のメンテナンス」が必要になる。
■ アップデートされる“感じ方”—リズムとしてのエンパシー
エンパシーOSの持続可能性を高めるには、
組織の「リズム」そのものにエンパシーを埋め込む必要がある。
たとえば——
- 感情の定点観測:「最近、どんな違和感ありました?」
- 変化の言語化:「今、うちのチームの“温度感”ってどう?」
- “わからなさ”の共有:「これ、ちょっと説明できないんだけど…」
こうした時間や問いを、習慣として持ち続ける。
それは、感じ方の精度を高め、
変化の兆しをキャッチするアンテナを保つことでもある。
■ “答え”ではなく、“揺らぎ”を記録する
エンパシーの怖さは、「わかった気になること」にある。
一度「この人はこういう人」と解釈してしまえば、
もうそれ以上、探ることをやめてしまう。
でも、本当の共感は、
「まだわかりきっていない」と感じ続けることにある。
だから大切なのは、
完了された“答え”ではなく、
未完のままの“揺らぎ”を記録しておくこと。
- 「あの場面、Aさんはなぜ無言だったのか?」
- 「あの時、Bさんの一言は、実はSOSだったのかもしれない」
このように仮説の種を持ち続けること。
それが、エンパシーのバージョンアップを支える。
■ 感性が風化しない組織に必要なこと
時間が経てば、どんなチームも“慣れ”ていく。
すると、最初にあった感度は少しずつ鈍くなり、
やがて「前はこんなこと、言い合えてたのにね」という空気になる。
この“風化”を防ぐために必要なのは、
リーダーだけが敏感でいるのではなく、
みんなで感度を更新し合うこと。
具体的には、こんな営みがある。
- 「違和感が出世する」文化:違和感が議論の起点になる
- 「感性ジャーナル」:小さな気づきを定期的に書き留めるチーム手帳
- 「感性のデモデー」:月に1回、お互いの“感じたこと”を発表する場
感性が機能する組織には、
感性を話題にしてもいい空気がある。
■ 共感は“静かな対話”の連続である
「声の大きい人の意見が通る」
「ちゃんと伝えるには、論理が必要だ」
そんな前提が支配する世界では、
エンパシーは居場所を失ってしまう。
とはいえ、ほんとうは、
共感とは“静かな対話”の連続である。
それは、「あなたの言葉が、わたしの中に響いている」という、
たしかに存在したはずの微細な共鳴のこと。
それを丁寧にすくいあげ、
見える化し、重ねていく。
それが、“感じ続ける組織”の呼吸なのだ。
Vol.5|沈黙の技術
— 感じる力の取り戻し -
■ 沈黙の背景には、「感じないほうがラク」な構造がある
わたしたちは、いま“感情の交通量”が飽和した時代に生きている。
SNS、チャット、ノートアプリ、リモート会議…
情報の流れは速く、心の声は追いつけない。
だからこそ、組織の中でも
「言わない・感じない・流す」が、無意識の生存戦略になる。
- 「察して欲しい」と思われることが怖い
- 「そこまで気を遣えない」が言えない
- 「感じないほうが効率的」という暗黙知
こうして、“感じる力”は切り離され、
やがて沈黙が当たり前になる。
■ “わかりあえなさ”に耐える力こそが、OSである
エンパシーとは、“すぐにわかる”ことではなく、
“わからない”ことに留まれる力。
つまりそれは、情報処理能力ではなく、感性の持久力だ。
- 答えが出ない話題に、ともにいる
- 気まずさをスキップせず、抱える
- 「わかろうとする」が“わかる”より尊い
これって、すごく非効率だけど、
とても人間的な営みだと思う。
そして、この非効率さを丁寧に取り扱えることが、
これからの組織の“柔らかさ”になる。
■ 組織のインフラに、感性というAPIを埋め込む
ここで言いたいのは、エンパシーを「意識高いスキル」として扱わないでほしいということ。
むしろ、組織のOSやプロセス設計に組み込む「API」として見てほしい。
たとえば——
- KGI/KPIの設計時に、「感性の質」を評価軸として扱う
- 採用面接で、「共感的に聴ける」問いを投げてみる
- フィードバック制度に、「感性のフィードバック」欄を設ける
つまり、“仕組みの中で、感性がふるえる余白を残しておく”こと。
それは、ただ優しい組織というよりも、
“ずっと対話し続けられる組織”をつくるということ。
■ 感性は、見捨てられたものの中に宿る
これからの時代、
データやロジックでは拾えない何かに耳をすます力が問われていく。
たとえば——
会議のあとに残る、“誰も言語化できなかった違和感”
数字の裏にある、“意味を失った努力”
一見どうでもいいような、“ちいさなまなざし”
こうした“余白”に宿る感性を、ちゃんと扱えること。
それが、見過ごされてきた声への接続点になっていく。
■ わたしたちは、右腕に想像力を持てる
ここまでの話は、決して理想論ではない。
エンパシーとは、トレーニングできる技術であり、
組織の文化としてデザインできる“仕様”でもある。
「感じることに、言葉をあげる」
「わからなさを、対話に変える」
「黙っている声に、マイクを渡す」
こうした営みの積み重ねが、
わたしたちの社会や組織をもう一度、
“人間のサイズ”に戻していく道なのだと思う。
最後にもう一度、エーリッヒ・フロムの言葉を借りる。
「愛するということは技術であり、学ぶことができる。」
そう、エンパシーもまた、“感じる技術”なのだ。
それは誰かの才能ではなく、日々の選択であり、呼吸であり、そしてOSでもある。
Vol.6|感性の課題
— 副作用と設計への応用 -
■ 「感性」にも副作用がある
感性やエンパシーが、絶対的な善であるかのように語られることがある。
しかし、感じる力はときに、わたしたちを壊す。
感じすぎて、立ちすくんでしまう。
わかろうとしすぎて、自分が崩れていく。
他者の痛みに反応しすぎて、いつの間にかそれがわたし自身の痛みになっている。
「エンパシーは技術である」と前回までで語ったが、
技術には、誤作動や濫用、そして設計ミスというリスクがある。
だから今ここで、もう一度問おう。
“感じる力”をどこまで使いこなせるのか?
■ 誤作動としての「シンパシー」の罠
「わかってあげてるつもり」が、かえって相手を傷つけることがある。
それは本来のエンパシーではなく、自己投影の錯覚、つまりシンパシーの誤用だ。
- たとえば、「あなたの気持ちはよくわかるよ」と言いながら、
その言葉が自分の過去の経験に基づいている場合。 - たとえば、誰かの痛みに対して、
自分が感じたくないからと「励まし」で蓋をしてしまう場合。
それは、わかろうとすることではなく、
「わかったことにしておきたい」自分の都合かもしれない。
■ 感性の逆利用——エンパシーは操作されうる
マーケティングや政治の現場では、「共感」や「感情」はしばしば「エンパシー」として語られるが、実際には多様な感情操作の側面を含んでいる。
たとえば、
- CMで家族の物語を流し、「泣ける」体験と商品を結びつける手法。
- 社会運動で「かわいそう」を武器にし、他の立場の声を沈黙させる行動。
- SNS上での感情的な炎上を演出し、注目を集めるプロパガンダ。
これらは、その一例である。
これらは、感性にアクセスする「インフラ」や仕組みの一部として機能しているが、その使われ方が倫理的にどうかは必ずしも検証されていない。
このような現象は、多くの場合、純粋な「エンパシー」(他者の内面に立ち入って感じ取ろうとする想像力)ではなく、
「シンパシー」(同情や感情共有)や「自己投影」の誤用や悪用に近い。
例えば、誰かの痛みを「自分の過去の経験」と重ねてしまい、相手の本質とは異なる理解を押し付けたり、
不快な感情を避けるために「励まし」という形で蓋をしてしまうことは、真の共感ではない。
本来のエンパシーは、相手の世界を想像し理解しようとする技術であり、単なる感情の模倣や共有とは異なる。
その一方で、こうした感情操作の仕組みは、マーケティングや政治の文脈で非常に有効に使われているため、私たちは注意深くその影響を見極めなければならない。
■ 共感疲労(Compassion Fatigue)という現象
特に医療・介護・教育・相談など、人の痛みに長時間寄り添う現場では、
「共感しすぎて、燃え尽きる」現象が起こる。
- 他人のつらさに心を寄せ続けることで、
自分の内側の境界線が溶けてしまう。 - やがて“感じること”そのものに、
疲労感や無力感を覚えるようになる。
この「感じすぎる」現象は、SNS時代にも共通する。
“毎日、誰かの痛みが流れてくる”情報環境のなかで、
共感のリソースは、いつの間にか枯れていく。
わたしたちは、「受けとる感性」と同じくらい、
「距離を置く想像力」を育てる必要がある。
■ 感性を、構造へ:エンパシーの設計的応用
では、「感じすぎないために、感じないようにする」しかないのだろうか?
いや、むしろ逆だ。
感じることを、構造へ翻訳するという道がある。
◎ カスタマージャーニーやサービスデザイン
一人ひとりの顧客体験に共感するだけでなく、
それをマップとして可視化し、組織全体で共有する。
◎ 共感マップやペルソナ設計
「この人にとっての“当たり前”はなにか?」を探る問いが、
価値あるプロセス設計に繋がる。
◎ チーム内での“感性の言語化”
「あのとき、どう感じたか?」を丁寧に拾い上げる対話は、
組織の中に感情が通う設計図を育てる。
“感じる”という営みは、ただ受け取るだけで終わらせず、
設計に昇華することで、はじめて持続可能な力になる。
エンパシーとは、誰かを救うための「ヒーロー性」ではない。
むしろ、問いかけを持ち続ける“共振体”のような存在であること。
そしてそれは、ひとりきりで抱える必要のないものだ。
感性を言語にし、言語を構造にし、
構造をふたたび感性へと還元する循環。
その営みのなかに、わたしたちの新しい
“想像力の共同体”が宿る。
■ Epilogue:右腕に想像力を持つということ
わたしたちは「相手の文化に触れる」ように、
日々、他者の内面という異国を旅している。
そこで必要なのは、地図ではなくコンパスだ。
それは、正解を指すのではなく、方向性を感じ取る道具。
そのコンパスが、感性というインフラの上に置かれているならば、
わたしたちは、もっとやさしく、もっとしなやかに、
この複雑な社会を生き抜く術を持てるのかもしれない。
脚注
※ API(Application Programming Interface)
ソフトウェア同士が機能やデータをやり取りするための「接続口」や「共通の言語」のこと。
このコラムでは、「エンパシーや感性を“個人の資質”ではなく、誰でもアクセス可能な“仕組みの一部”として組み込む」という意味で使用。
つまり、個人の努力や性格に依存せず、設計の中に“つながりやすさ”を内蔵するという発想。



