《 再び、問いから始める 》
—文明の裂け目に立つ私たち
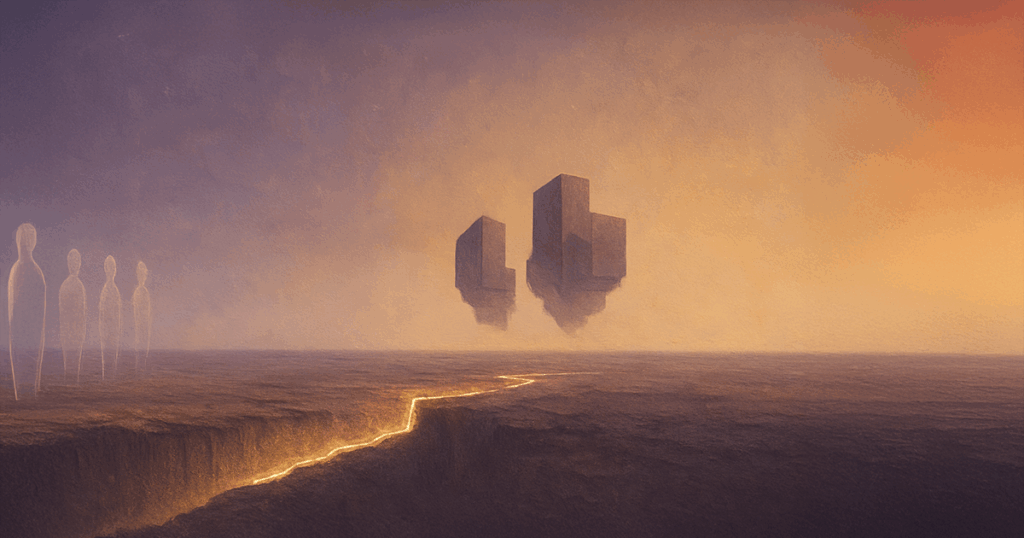
プロローグ:
問いとは、ただ正解を導くための道具だったのだろうか。
社会や教育の制度が“答えのある問い”に偏ってきた中で、
見過ごされてきたもう一つの問いがある。
それは、正解に向かわず、構造そのものを揺さぶる「生成の問い」。
いま、文明の裂け目から、
その問いが静かに息を吹き返そうとしている。
私たちは再び、問いの声に耳を澄ませるところから始められるだろうか。
序|
問いとは、いつも“ひとつ”だったのか?
あるいは、私たちがそれを“ひとつしかないもの”として扱ってきただけなのか。
ふと、そんなことを考える。
現代の教育制度の中で、あるいはビジネスや社会の現場で、
問いは「問題を解決するための道具」として扱われることが多い。
「なぜ成果が出ないのか?」
「どうすればもっと効率的か?」
こうした問いの立て方は、すでに正解や目標が前提として存在することを前提としている。
つまり、“答えに向かうための問い”だ。
でも、本来「問い」とは、それだけだったのだろうか?
もしかしたら私たちは、問いを「役に立つ」ものとして手なずける過程で、
もっと根源的な「問いの力」を、置き去りにしてきたのかもしれない。
文明が大きく揺らぐとき、問いが再び前面に現れるのは、その兆しかもしれない。
問いが“再び”立ち上がるということは、
それまでどこかに追いやられていたということだ。
そしてその「どこか」は、教育という仕組みの中にも、深く静かに刻まれている。
Ⅰ|二つの問い
— 問いを問うという営み
“問い”には、少なくとも二つの異なる性質がある。
■ 一つめの問い:解決のための問い
- 答えを出すための問い。
- 問題解決・合理性・効率の向上など、構造の“内部”で働く。
- 明確な目標に向かう設計されたプロセスの一部。
- 教育制度・企業研修・政策決定の多くが、こちらの問いを軸に設計されている。
■ 二つめの問い:生成のための問い
- 世界や制度の「前提」を揺るがす問い
- 「そもそもなぜ?」「それは誰の価値観?」といった“意味の根源”に触れようとする。
- 答えがなくても成立する。むしろ、問い続けることで世界が変わっていく。
- 哲学や芸術、詩、あるいは個人の内的対話において息づいている。
この二つの問いには、どちらが優れている、という優劣はない。
どちらも、人間の営みにとって欠かせないものだ。
ただ重要なのは、いま自分が立ち上げている問いが、
どちらの性質を持つものかを自覚すること。
それを見失ったとき、問いは手段としての機能だけを残し、
内省や構造の更新から遠ざかっていく。
「なぜ問うのか?」
「その問いは、何を可能にし、何を隠すのか?」
「この問いは、何に対して立ち上がっているのか?」
こうした“問いへの問い”を通してしか、
私たちは問いを取り戻すことができない。
Ⅱ|問いを置き去りにした文明
文明は、どこから崩れ始めるのだろうか?
その問いに対して、「構造の内部」から解答を探し続けるのが、現代的なアプローチだ。
景気後退・気候危機・人口減少・技術格差。
けれど、これらの“問題”に対して有効な“解決”を講じることが、
果たして文明を救うことにつながるのだろうか?
もしかすると、文明が崩れていくときには、
それまで封じ込められていた“問いそのもの”が、ふいに顔を出す瞬間があるのではないか。
それは、構造の内部からは立ち現れない、外部からの侵入であり、
あるいは内部からの覚醒ともいえる。
「これはそもそも、誰のための構造なのか?」
「その繁栄は、どんな暴力の上に築かれていたのか?」
こうした根源的な問いは、平時の文明には受け入れられない。
なぜなら、それは“解決”の文法に従わないからだ。
それはただ、問いとして存在し、構造そのものの輪郭を浮かび上がらせてしまう。
だからこそ、文明は“問い”を制度の外に追いやり、
“答え”を量産しつづけることで、自らを正当化してきた。
問いを排し、効率と成果を循環させることで、
自壊を先延ばしにしてきたとも言える。
Ⅲ|教育という制度と、“解決の問い”の同調
問いが制度の中で管理されはじめたとき、
その最たる場が「教育」だったのかもしれない。
産業革命以降、教育制度は「知識を効率的に伝達し、役に立つ人材を育てる」ことを目的に整備されてきた。
そこでは、「問い」とはあくまで正答のあるものとして扱われる。
- テストに出る問い
- 解ける問い
- 解くべき問い
すでに前提が定められ、ルールが設計された「枠組みの中の問い」が繰り返される。
それによって、教育は“解決の問い”を中心に据えた制度となった。
そして多くの子どもたちは、“生成の問い”を内に抱えたまま、
その問いに言葉を与えることなく、日常のなかに封印していく。
それでも、その封印は決して消えたわけではない。
むしろ、構造の外で、いつか言葉を持つ日をじっと待ちつづけている。
Ⅳ|文明の終わりに現れる「生成の問い」
面白いのは、文明が崩れかけるとき、
抑圧されていた“生成の問い”がふたたび表舞台に立ち上がることだ。
これは歴史の中で繰り返されてきた現象なのかもしれない。
宗教から科学へ。
神から理性へ。
定理からコードへ。
いずれの移行期にも、“なぜ?”という問いは濁流のように噴き出していた。
問いが立ち上がるということは、構造が裂けはじめた兆しでもある。
そしてそのとき、はじめて言葉にならなかった「生成の問い」が、
ふたたび世界に輪郭を与えはじめる。
今、私たちが直面している文明の揺らぎのなかでも、
AI、気候変動、格差、孤独といった「答えなき問題」に囲まれて、
ふたたび“問いそのもの”が立ち現れようとしている。
Ⅴ|教育を「問いの場」に還すために
では、教育はこれからどう変わることができるのだろうか?
あるいは、どう変わらなければならないのだろうか?
一つ確かなのは、問いを“答えのための道具”として扱うだけでは、
次の時代を担えないということだ。
これからの教育には、「問いを問い続ける力」そのものが必要になる。
それは、“正しい答え”を導く力ではなく、
“そもそも正しさとは何か”を問う力。
“問い続けること”が可能な土壌を耕す力。
そしてそのためには、問いには二つあること、
そして今どちらを立ち上げているのかに自覚的であることが、
何よりも大切なリテラシーになるのではないだろうか。
文明が崩れかけるそのときに、
もう一度、問いそのものと共にある教育を、取り戻せるかどうか。
その可能性だけが、私たちの手の中に残されている。
Ⅵ|問いを抱えるということ
—「解けなさ」と共に生きる力
問いを抱えるということは、不安定さと共に生きるということだ。
“答えがある”という安心から距離を置き、
言語化されない違和感や未分化な気配のなかに、静かに立ちつくすということ。
もちろん、すべての問いに“生成の問い”を求めるべきではない。
日常には、明確な“解決の問い”が必要な場面もある。
電車が遅れていたら原因を知りたいし、
社会に制度不備があるなら改善策を考えたい。
大切なのは、「今、自分がどちらの問いに立っているのか」を自覚すること。
生成の問いを“答え”に短絡させず、
解決の問いを“真理”と誤認しないこと。
私たちはその両方を行き来しながら、
日々の生活と、世界の深みに、同時に触れている。
それは、効率でも正解でも測れない、
“生きるという経験”そのものと、どう向き合うかという態度でもあるのだ。
Ⅶ|問いの再興
— 裂け目から立ち上がる未来へ
もし、文明が問いを置き去りにしてきたのだとすれば、
そして今、裂け目のなかで問いが再び立ち上がってきているのだとすれば、
私たちは今、極めて希有な瞬間に立ち会っているのかもしれない。
問いは、崩れゆく文明の残響のなかから、
新しい物語の予兆として浮かび上がる。
「この構造のままでいいのか?」
「何を失って、何を得てきたのか?」
「そもそも、“人間らしさ”とは何だったのか?」
それらはまだ言葉にならない問いかもしれない。
それでも、その未分化のざわめきを無視せず、
すぐに“答え”に変換せずに、ただそこに耳を澄ますこと。
教育も、文明も、その再編はそこからはじまる。
問いを取り戻すとは、
「言葉にならなかった声を、言葉にならないまま引き受ける力」
を取り戻すことなのかもしれない。
そしてそこから、
「問いと共にある未来」へ、
まだ見ぬ歩みが始まっていく。



