罹ってる、という感覚について
- 反応の奥に眠る“まだ言葉にならない問い” -
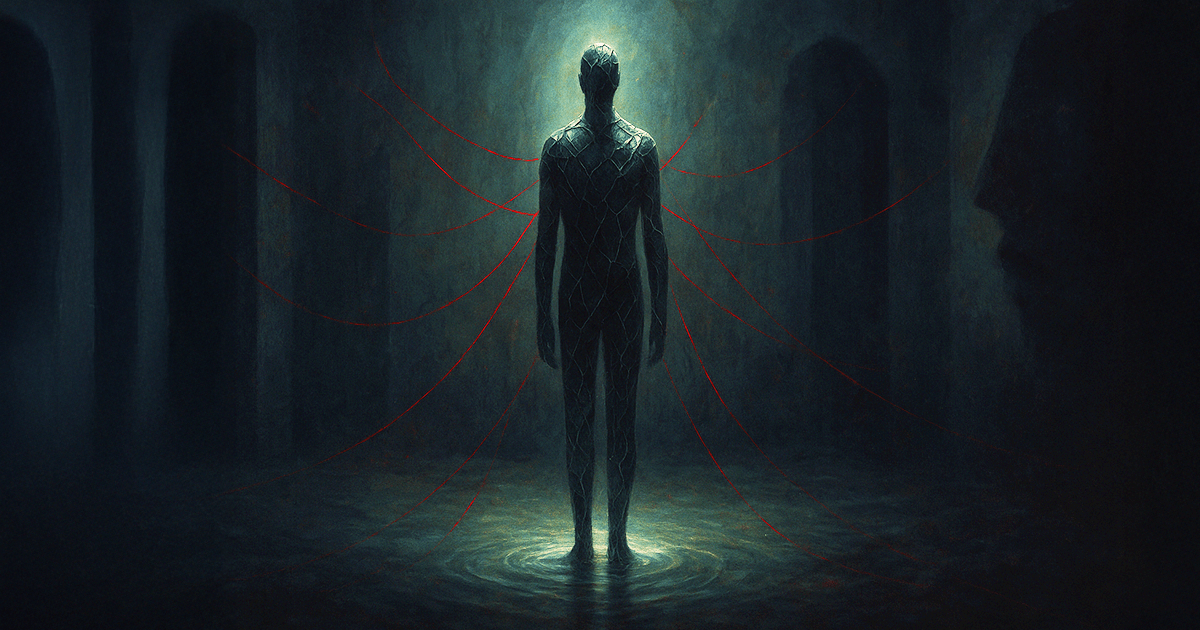
プロローグ:
ふとした瞬間、自分でも説明できない言動をとってしまうことがある。
なぜそんなに反応したのか、なぜそこまで囚われてしまったのか。
そんなとき、私たちは何かに“罹っている”のかもしれない。
それは不調ではなく、内側で言葉にならない問いが動きはじめたサインだとしたら…
この“罹り”の感覚に耳を澄ませることで、まだ見ぬ自分と出会う道が開かれていくのかもしれない。
Vol.0|まだ言葉にならないものの兆し
— 反応が教えてくれる、問いの入り口 -
■ それは反応か、それとも問いか?
人は時折、何かに“罹っている”ように見えることがある。
たとえば、普段より饒舌になったり、逆に黙り込んだり、急に怒りっぽくなったり、笑いが止まらなくなったり。
本人にとっては「いつもの自分」のつもりでも、どこかで違和感がにじむ。
その瞬間、私たちは何かに心を奪われ、内側で何かが立ち上がろうとしているのかもしれない。
それは、反応なのか?
それとも、まだ言葉にならない問いなのか?
■ 1次プロセスの輪郭
プロセスワークの視点では、私たちはふだん「1次プロセス」と呼ばれる、思考や行動のスタイルに同一化している。
たとえば「私は冷静な人間だ」とか、「感情を抑えるのが大人だ」とか、そうした“自分らしさ”の感覚。
でも、その背後には、未だ言葉になっていない別の側面――「2次プロセス」的な何かが存在している。
人生のある瞬間、その2次プロセスがふと現れそうになる。
それが、1次プロセスとの境界=“エッジ”に触れたときだ。
多くの場合、人はそのエッジに立たされたとき、かえって「いつもの自分」を強く押し出す。
それは、自分自身の足場を守るための無意識の反応とも言える。
でも、そこにこそ“問い”が潜んでいるのかもしれない。
■ 「罹る」という状態
私はこの状態を「罹っている」と呼んでいる。
「ハマっている」「取り憑かれている」「引っ張られている」――それらの言葉に近いが、どこか少し違う。
罹るというのは、外から何かが侵入してきたようで、実は自分の深層から何かが“上がってきている”ような感覚でもある。
焦燥感、そわそわ、過剰な正当化、同じ思考の反復。
それらは、明確な理由がないのに続いてしまう。
そのとき、何が起きているのだろう?
そして、そこにどんな問いが眠っているのだろう?
■ 問いはいつも、輪郭を持たない
問いというのは、しばしば遠回りをする。
はじめから「問いのかたち」をして現れるわけではない。
むしろ多くの場合、それは態度や言葉、反応の変化として、じわじわとにじみ出てくる。
本人がそれと気づかぬうちに、まるで身体の深部から浮上してくるかのように。
問いはときに、過剰な沈黙として、
ときに、やけに軽やかな明るさとして、
ときに、自分でも辻褄の合わない言い訳として現れる。
そしてそのどれもが、“罹っている”兆候なのかもしれない。
■ 兆しに耳を澄ませるということ
私たちは、自分の罹りを「修正すべきもの」として扱いたくなる。
ただ、そこにあるのが「まだ問われていない問い」だとしたら?
罹っていることそのものに意味があるとしたら?
いま、自分の中にある違和感、繰り返し、ざわつき。
そのすべてを「何かが動き始めている徴候」として眺めてみる。
問いのかたちは、まだわからなくていい。
ただ、「罹っている」という感覚を入り口として、
私たちは少しずつ、自分という存在の奥へと降りていくことができるのかもしれない。
Vol.1|罹っている他者に出会うとき
— 共鳴のなかで立ち上がる、関係としてのケア -
■ その人は、何に罹っているのだろう?
ふと、誰かの様子に「いつもと違う」と感じることがある。
声の調子、言葉のテンポ、目線の揺れ方。
それらがほんのわずかにズレて見えたとき、人は無意識のうちに“他者の罹り”を察知するのかもしれない。
たとえば、必要以上に冗談を繰り返す人。
妙に沈黙が長い人。
話が堂々巡りになる人。
それが「その人らしくない」と感じられるとき、何かが起きている。
でも、それを“説明できる言動”に回収しようとする前に、もう少しだけ立ち止まってみることはできるだろうか。
その人は今、何に罹っているのだろう?
そして、なぜその罹りは、私の目にとまったのだろう?
■ 他者の罹りに、私が反応するとき
他者の違和感にこちらが過敏に反応してしまうとき、それは単なる観察ではない。
ときにそれは、自分の中にある未処理の問いや不安が、鏡のように照らし出されている兆しでもある。
たとえば、感情をむき出しにする人に苛立つとき。
沈黙する人に不安を感じるとき。
そこには、「そうしてはいけない」という自分の1次プロセスが反応している可能性がある。
つまり、「その人が罹っている」ように見えるとき、実は私の中にも何かが罹っているのかもしれない。
他者の状態に過敏になるとき、私たちはどれだけ自分自身の内側に気づけているだろう?
■ 罹りは、共鳴する
「罹り」は個人のものとして現れるように見えて、実は場や関係の中で共鳴していく。
誰かが罹っているとき、その人を見ているこちら側の空気もまた微細に変化する。
呼吸が浅くなったり、言葉がうまく出なくなったり、逆に喋りすぎたり…
そのとき私たちは、ただ「見ている」のではなく、「巻き込まれている」のかもしれない。
ただ、それを悪いことだとは思わない。
むしろその共鳴のなかに、関係性の中に現れる“問い”の種がある。
私たちは共に罹り、共にその意味を問う存在なのではないか。
■ 他者の罹りを、どう受け取るか
「その人は今、罹っているのだな」と気づいたとき、私たちはどんなふうにそこにいることができるだろう。
正そうとする? 慰める? スルーする? 距離を取る? それとも、ただ隣にいることを選ぶ?
ときに、「寄り添う」という言葉でさえ、過剰な意味づけや介入になってしまうことがある。
むしろ、「そのままそこにいさせる」という選択肢がありうるのではないか。
他者の罹りを、“直さず” “わかろうとしすぎず” “放り出さず”受け取ること。
それはたぶん、とても難しい。
ただ、そこに理解ではなく、関係としてのケアが生まれる可能性がある。
■ 罹りをわかちあう、という営み
罹っているとき、人はしばしば孤立している。
自分の反応に巻き込まれ、自分の中に閉じてしまっている。
でも、誰かが「その状態に気づいてくれている」と感じるだけで、
あるいは何も言われなくても「見守られている」と感じられるだけで、
その人の内側に小さな“隙間”が生まれることがある。
それは、まだ言葉にならない問いが、ほんの少し息をしはじめる瞬間かもしれない。
他者の罹りを、問いの前兆として受けとめ、
それに過剰に反応する自分もまた、問いの只中にいるのだと自覚する。
そのとき、関係は「ケアされる者/する者」という二項ではなく、
共に罹っている者たちの、静かな対話の場へと変わっていくのかもしれない。
Vol.2|罹りのなかで立ち止まる力
— 問いになる前の時間を、生き延びる -
■ すぐに「戻ろう」としてしまう私たち
何かに罹っているとき、私たちは無意識にそれを「早く解消しよう」とする。
落ち着かなさを抑えようとし、理由を探し、正当化したり忘れようとしたり。
それはごく自然な反応でもある。
ただ、その動きは、もしかすると「まだ現れていない問い」を押し戻す行為でもあるのかもしれない。
反応の裏に、言葉にならない何かがある。
それに気づきながらも、つい日常へと「戻ってしまう」私たち。
その揺れのなかに、問いの気配が立ち上がっているのではないだろうか。
■ 罹りを“持ちこたえる”という選択
「罹っている」状態をすぐに終わらせようとせずに、少しだけそこにとどまってみる。
それは、混乱や違和感を無理に整理せず、そのまま感じ続けるという選択でもある。
何が起きているのかを急いで理解しなくてもいい。
むしろ、「何が起きているかわからない」という状態にこそ、何かが宿っていることがある。
問いは、明快さよりも曖昧さのなかから立ち上がる。
罹っている感覚を抱えたまま、ただそこに“持ちこたえる”ことでしか見えてこない風景があるのかもしれない。
■ 「問いにする」前の時間
問いは、思考として整った瞬間から問いになるわけではない。
その前には、かたちのないまま、ただ“存在している時間”がある。
焦燥、不機嫌、沈黙、奇妙な笑い、言葉のもつれ。
それらはすべて、問いになる前の「兆し」たち。
その前の時間を無視して、「で、何が問題なの?」と急ぐと、
問いの芽ごと切り落としてしまうことがある。
問いは、立ち上がるまでのプロセスも含めて“生きもの”なのかもしれない。
■ 罹りの時間を引き受けるということ
罹っている状態を「正す」「改善する」ものとしてだけ見るのではなく、
「引き受けるべき時間」として扱うという発想。
それは、自分のなかでまだ消化されていない層と共にいる、という選択でもある。
問いが立ち上がる前の、言葉にならない混沌。
その混沌を、排除せず、制御せず、ただ共に呼吸する。
それができたとき、私たちは自分のプロセスの一部に、
ようやく“居場所”を与えることができるのかもしれない。
■ 罹りを生きるということ
「罹り」は治すべき“状態”ではなく、
問いが生まれようとしている“動き”なのかもしれない。
もしそうだとしたら、罹っているときこそ、
私たちはもっとも「変化の入口」に立っているのかもしれない。
それは不安定で、理解できなくて、誰にも説明できない時間。
でも、そこにしか開かれない扉がある。
罹っている自分をすぐに止めようとせず、そのまま受けとめてみること。
それが、「問いと共に生きる」という営みの、最初の一歩なのかもしれない。



