《 空振りした希望 》
- 届かなかった問いをめぐる、対話のフィールドノート -
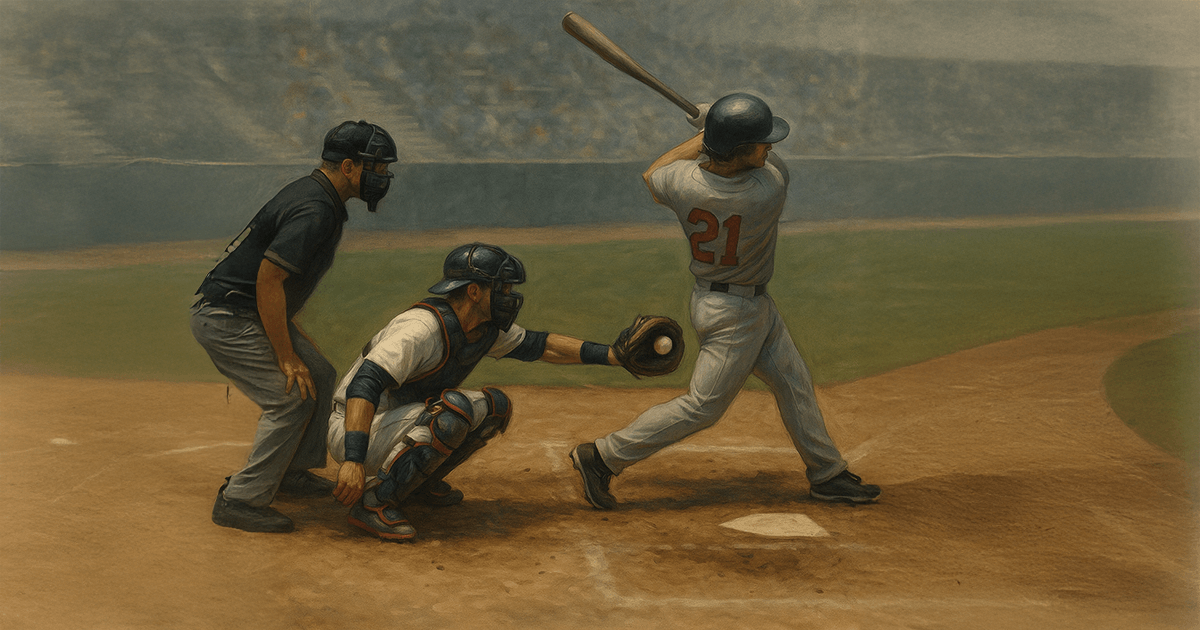
まえがき
この話は、わたしがコンサルティング業務を始めて最初に契約した、あるクライアントとの出来事を綴った記録です。
まだ立ち上げたばかりの頃で、実績も十分ではなく、「仕事が欲しい」という気持ちも当然ありました。
そのうえで、目の前の相手にどこまで誠実に向き合えるか、自分なりに考え、判断を重ね、契約に至りました。
結果として、その関係は長くは続かず、3ヶ月で契約は終了しました。
関係の終わり方も含めて、いくつかの釈然としない感覚が、今もどこかに残っています。
この文章は、誰かを責めるために書くものではありません。
むしろ、「どのようなズレが生まれていたのか」「なぜその判断に至ったのか」を、冷静に振り返っておきたいと思ったからです。
そしてなにより、同じような経験をするかもしれない未来のわたし自身へ、残しておきたいという気持ちもあります。
誠実であろうとすることが、常に報われるとは限りません。
それでも、誠実さを手放さずに、仕事を続けていきたいという思いがあります。
【第一章|空振りは、希望のかたちをしてやってくる】
■ 最初の契約
初めてのクライアントとの契約だった。
仕事が欲しかった。
実績も、自信も、まだこれからだったから。
声をかけてもらった時、
「やっとはじまる」と思った。
だからこそ、
その最初の一件を、丁寧に丁寧に、取り扱ったつもりだった。
■ 違和感と判断
相手の言動には、いくつかの違和感があった。
「内省したい」と言うが、
その態度には、強い正解主義とコントロール欲がにじんでいた。
「言ってることと、やりたいことが違う」
――そう感じた瞬間は、契約前から何度もあった。
ただ、「そこには手をつけないでほしい」というような領域にこそ、
むしろ“内省”の力が届くかもしれない。
そう思って、自分なりに筋道を立て、契約を結ぶ決断をした。
■ ルールの明示とリスク説明
コンサルティングという仕事の性質を、あらかじめ伝えた。
「言われたことをやる」のではなく、
「一緒に問い、構造を見ていく」ことが仕事だと。
その説明に対し、相手は「それで問題ない」と答えた。
万一、途中で契約を打ち切る場合はどうなるか、
支払い条件はどうするか、リスクについても正直に話した。
すべて書面ではなく、会話の中で確認した。
それでも、関係は破綻した。3ヶ月で終わった。
■ 何が残ったのか
納得した上で契約し、自分なりに最善を尽くした。
だから後悔はしていない――はずだった。
でも、どこかに釈然としない感覚が残った。
「仕事が欲しかったから、あえて見て見ぬふりをしたんじゃないか?」
「わかっていたのに、都合よく希望を抱いたんじゃないか?」
「それを“誠実”と言って、自分を正当化してないか?」
そんな問いが、あとから何度も浮かんでは消えた。
■ 選んだのは、自分だ
相手がどうだったかではなく、“飲んだ”のは自分だ。そう思う。
だけど、誠実に判断しようとした時間や、問いを届けようとした姿勢が、
まるごと無視されたような終わり方に、どこか「裏切られた感覚」だけが、薄く残っている。
■ 伝わらない、痛み
「内省」や「気づき」といった言葉が、自己都合的に使われていると感じることが何度もあった。
言葉の定義ではなく、構造の話をしても、伝わるのは表層だけ。
“どの行動をしたか(Doing)”ではなく、
“なぜその行動を選んだのか(Being)”を問おうとするたびに、
「自分が悪いです」という反省の言葉で返ってきた。
わたしは、責めていたわけではなかった。
ただ、見えない前提や、自分では気づけない選択の癖に触れようとしていた。
けれど、それは常に「怒られているように聞こえる」のだと、途中からわかってきた。
無自覚のBeingを問いかけても、それが伝わることは少なく、
たとえ何かが届いたように見える瞬間があっても、
「全部わかりました」「もう大丈夫です」という言葉で、
その“気づき”はすぐに蓋をされてしまった。
「無自覚の前提は、なくならないんです」と何度も伝えた。
それでも、返ってくるのは「もうありません」のひと言だった。
わたしは何度も「空振りした」と感じた。
それでもなお、問いを届けようとしていた自分の姿勢を、どこかで信じていた。
ただ、今振り返ってみると、やはり迷いは残っている。
「本当にあれでよかったのか?」
「もっとできることがあったんじゃないか?」
「あの言い方は、厳しすぎたんじゃないか?」
自分の最適解は、必ずしも相手の最適解とは限らない。
そのことを引き受けながら進むのが、わたしの仕事だと思っている。
だから、最後にいつもこうつぶやく。
「これで、よかったのか?」と。
【第二章|約束できること、できないこと】
■ 言葉の手前にある“姿勢”
コンサルティングという仕事をしていると、
「どこまでしてくれるのか?」という問いに直面することがある。
求められるのは、成果か、提案か、導きか。
そうした問いの背後には、無意識の期待や、これまでの業界イメージも含まれている。
わたしたちが提供したいのは、技術や指示ではなく、「問いを通じた関係性」だ。
つまり、“正しさ”ではなく、“見え方を変える力”のようなもの。
それは成果として測定しにくく、誤解されやすく、あいまいで、
だからこそ強く信じていないと揺らいでしまう。
■ スタンスは、構造に宿る
わたしたちが約束できるのは、
「一緒に問いを引き受ける」ということ。
逆に言えば、相手がその問いを“自分の問いとして持つ気があるか”までは、
こちらから強制できない。
その構造は、契約前にも共有したつもりだった。
コンサルティングは、指示ではなく、観察であり、再構成であり、解釈のずらし合いだと。
「こうしてください」という依頼をされた時点で、
少しずつ関係性がねじれていく。
それでも、「伝わるはずだ」と思っていた。
スタンスの説明だけではなく、
“関わりの中でその意味が立ち上がってくる”と信じていたのだと思う。
■ 一方向では生まれないもの
わたしたちが扱う「問い」は、双方向でしか機能しない。
それは一種の契約のようなものでもある。
「問いを受け取ることを、相手が選ぶかどうか」――
そこには、こちらからは手を出せない領域がある。
この一件を通して、わたしは「丁寧に伝えれば、きっと伝わる」という前提が、
どこかにまだ残っていたことに気づいた。
言葉を尽くし、仕組みを説明し、順を追って関係を築けば、
信頼は育つと思っていた。
人はそれぞれの速度でしか動けない。
そして、望んでいない変化を、真正面から受け取ることはできない。
「伝える」だけでは足りない。
「伝わらないかもしれない」という前提ごと、関係性を設計し直す必要がある。
その痛みを、ようやく少しだけ引き受けられるようになってきた気がする。
■ わたしたちが、約束しないこと
成果を保証することはできない。
正解を提供することもしない。
代わりに、問いの所在を一緒に探す。
見えない前提を、一緒にほどいていく。
それは、すぐに評価されるような仕事ではないかもしれない。
誤解されることの方が多いかもしれない。
それでも、「問いをともに持つ」という姿勢が、
ある種の磁場を生むことを、何度も体験してきた。
今回は届かなかった。意味がなかったとは思わない。
「わかってもらう」ことを目指すのではなく、
「わからないままでも関係をつくれるか」を、問い続けるしかないのだということ。
【第三章|風景が重なる瞬間】
■ 重ならない視点
わたしたちが「伝わる」と思っていることの多くは、
同じ言語を使っているというだけで、
実は何ひとつ重なっていないことがある。
「問いとは何か」「内省とはどういう時間か」――
その前提を共有できていないまま、同じ言葉を使って会話が進んでいく。
すると、たとえば「問いをもらえるのがありがたい」と言ってくれるその言葉すら、
わたしの想像とはまったく別の意味で発せられているのだと、ある瞬間にわかってしまうことがある。
そのズレは、とても緩やかに進行する。
はじめのうちは、お互いの信頼や誠意のなかに、なんとか包摂されてしまう。
だが、そのうち、発した言葉がすこしずつ意図とちがう形で受け取られ、
それに対する反応もずれてくる。
そして、相手の表情に「防御」や「迎合」の色が見えはじめたとき、
わたしは思うのだ――これは、まだ風景が重なっていない、と。
■ 見ている風景が違うという前提
問いを通して見てほしい風景がある。
だが、それは「わたしの見ている景色を共有したい」ということではない。
そうではなくて、
自分が今見ている風景だけがすべてではない、という可能性に気づいてもらいたい。
世界の解像度が上がっていくような感覚。
それこそが、わたしが提供したかった体験だった。
だが、相手がそのことに気づく手前で、
「自分はもう全部見えています」と語ってしまうとき、
わたしはそこに虚しさを覚える。
内省は、何かを知ることでも、理解することでもない。
むしろ、まだ知らなかった前提に気づいてしまう、ということだ。
その意味で、わたしの仕事は「気づきの提供」ではなく、
「問いの提示」である。
■ 風景が重なるということ
ほんの一瞬でも、視界が重なったと感じる瞬間がある。
それは、共感でも、納得でもなく、
相手が自分の足元を見直し、少し立ち止まったような気配のときだ。
正しいかどうかではなく、
「そういう見方もあるのか」と、ふと目線が外れる。
そのとき、何かがはじめて動き出す。
だが、それは簡単には起こらない。
多くの場合、すぐに元の視点に戻ってしまう。
自己防衛やプライド、効率や成果という思考が、再び目を覆う。
だからこそ、その一瞬が貴重なのだと思う。
■ それでも風景を届けたい
わたしは、すべての人と風景を重ねたいわけではない。
ただ、「風景はひとつではない」ということを知っている人となら、
同じ空間にいられる気がする。
たとえ完全には伝わらなくても、
「伝えようとする姿勢」が互いにあるだけで、その場の空気は変わる。
これは、サービス提供者と顧客の関係に限らない。
すべての人間関係に言えることだ。
それでもなお、伝わらないことはあるし、
望んだ風景が見えてこないこともある。
だが、それでも問いを届けたい、と思ってしまう自分がいる。
そのことを、今はもう責めずにいようと思っている。
【第四章|誠実の臨界点】
■ 境界線の見極め
「誠実でありたい」という姿勢には、いつも境界がつきまとう。
その境界とは、相手の期待に応えすぎて、
自分をすり減らしてしまうラインのことだ。
わたしは、相手の痛みや迷いに触れようとするたびに、
いつの間にか“全力で応えようとする側”になってしまっていた。
それは自分の意志でもあり、ある意味では癖でもある。
ただ、それが“誠実さ”なのか、“過剰な配慮”なのか。
その見極めは、当事者の間では本当に難しい。
■ 差し出すことと、巻き込まれること
相手の問いに対して、自分の時間や感情を投げ出すことは、惜しくなかった。
ただ、いつしかその問いが、
“相手の代わりに考える”という構図にすり替わっていく。
「それ、どういう意味ですか?」と問うたとき、
相手が沈黙したまま、わたしが答えを用意してしまうような場面が何度もあった。
問いを差し出したつもりが、
いつのまにか、自分がすべてを引き受けようとしている。
巻き込まれていることに気づいた時には、
すでに手遅れだったりする。
それでも、「まだ届くかもしれない」と思ってしまう。
■ 自分を踏み越えてしまう瞬間
自分の価値観を守りながら、相手に関わり続けるのは難しい。
特に、「仕事が欲しい」「失いたくない」という気持ちが入り混じると、
判断が鈍る。
あの時も、わたしは相手に配慮するあまり、
自分の基準をいくつか、そっと踏み越えてしまった。
言い方を変えたり、伝える順序を変えたり、沈黙の時間を長く取ったり。
そのどれもが、わたしなりの誠実だったつもりだった。
ただ、今思えば、「誠実」という言葉を盾にして、
自分の“譲れないもの”を、少しずつ削っていっただけだったのかもしれない。
■ どこまで背負うか
コンサルタントという仕事は、
「介入」と「距離」のあいだで揺れ続ける。
踏み込まなければ見えないこともあるし、
踏み込みすぎると、相手の変化を奪ってしまうこともある。
どこまで背負うか。どこまで踏み込むか。
この判断には、正解がない。
でも、あのときのわたしは、
「誠実であること」に囚われすぎていたのかもしれない。
そうすることでしか、
自分の“価値”を証明できないと思っていた節が、今となっては見えてくる。
誠実さは、いつだって独りよがりにもなりうる。
そのことを、自分の仕事の初期に体験できたことは、
苦しくも、ありがたかったのだと思っている。
【第五章|問いを手放すということ】
■ 問い続けることの限界
わたしはずっと、「問いを届けること」が自分の仕事だと思っていた。
問いを持つことで、人は立ち止まり、
自分の声に耳を澄ますことができる。
そう信じてきたし、
それを信じることで、自分自身を支えてもきた。
ところがある時から、
その問いが届かなくなる感覚があった。
どれだけ言葉を尽くしても、
相手にはただの“正解探し”として受け取られる。
「わたしは何をやっているんだろう?」と、
問いを投げかける側のわたし自身が、宙づりになっていく。
■ 「響かせる」ことと「届く」ことの違い
問いは、“響かせる”ことができても、
必ずしも“届く”わけではない。
相手の内側に、まだ受け取る準備ができていない場合、
問いはただのノイズになる。
そのことを、頭ではわかっていたはずだった。
それでも、何かが届くはずだと信じたくなる。
そして、届かない現実に、どこかで自分を責めてしまう。
問いは、「届ける側」がコントロールできるものではない。
わたしにできるのは、
「相手が受け取れる状態かどうか」を見極めること、
そして、問いが根を張れるような“土壌”を整えることだと思う。
それは、問いの意味を先回りして説明することでも、
答えを誘導することでもない。
ただ、相手が自分の声に触れられるような“空気”を、静かに整えていくこと。
届くかどうかよりも、届いていいと思える“場”があるかどうか。
それこそが、問いを生かすために必要な前提なのかもしれない。
■ 「問い」を差し出すタイミング
どんなに優れた問いでも、
それを差し出す“タイミング”を誤れば、
むしろ関係性を傷つけることがある。
「問い」とは、関係のなかで慎重に扱うべき“刃”のようなものだと、今では思う。
あのとき、わたしはその刃を無自覚に抜いてしまっていたのかもしれない。
そして、相手はその鋭さに耐えきれず、心を閉ざしてしまったのかもしれない。
問いは相手を開かせるための手段ではない。
その人が“自分で開くため”の、静かな触媒にすぎない。
その役割を見誤ったとき、
問いは暴力になり得る。
■ 手放すという選択
問いが届かないと感じたとき、
わたしは長らく、「どうしたら届くか」を考え続けてきた。
しかし、ある時ふと、
「届かないことを受け入れる」という選択肢があるのだと気づいた。
問いを手放すということは、無関心になることではない。
それは、「今は届かない」という現実を、自分の中で引き受けることだ。
そして、問いを置いたまま、相手から一歩、身を引くことでもある。
相手がそれをいつか拾い上げるかどうかは、もうわたしの手の中にはない。
問いは差し出されたその瞬間から、もうわたしのものではない。
だからこそ、わたしは、差し出すことに責任を持たなければならないのだ。
【第六章|それでも、問いを差し出す理由】
■ 向き合い続ける意味
この仕事をしていると、
「どうせ届かないんじゃないか」と感じる瞬間は何度もある。
それでもなお、問いを差し出そうとするのは、
どこかでそれが“人間への敬意”だと信じているからかもしれない。
相手を信じる、というよりも、
「問いかけることができる存在として見る」という視点そのものに、敬意があると思うのだ。
問いは答えを求めるための道具ではない。
それは、まだ言葉になっていない違和感や、
無自覚に見過ごしてきた選択の“癖”に、光を当てる行為だ。
問いは、すぐに効く“薬”ではない。
それでも、それがじわじわと沁みて、何かを変えていくことがある。
■ 自分のための問い
正直に言えば、問いを差し出すのは、相手のためばかりではない。
それは、わたし自身が「自分の選択に責任を持つため」に必要な行為でもある。
「この言葉でよかったか?」
「このタイミングは適切だったか?」
「相手に委ねる準備は、自分にできていたか?」
そんな問いを、自分自身にも差し出し続ける。
だからこそ、わたしは問いという営みを、
他者との“取引”ではなく、
自分の立ち位置を確かめる“軸”として扱っている。
問いが伝わるかどうかは、
相手の反応ではなく、自分の姿勢に照らして判断したい。
「届いたかどうか」ではなく、
「差し出せたかどうか」――その違いを、わたしは大切にしたい。
■ 誰かに“背中”を見せるということ
問いを届けるということは、
ときに言葉にする以上の影響を与える。
表面的な言葉ではなく、
「その問いを差し出す態度そのもの」が、相手に届くこともある。
だから、伝わっていないように見える時でさえ、
「問いを差し出す」という選択をした自分の背中を、
誰かが見ているかもしれない――そう思うことがある。
それは、目の前の相手かもしれないし、
遠くにいる第三者かもしれない。
あるいは、いつかの自分自身かもしれない。
それでも問いを手放さないという態度は、
「問いとともに在る」という姿勢を、誰かに示すことになる。
問いを差し出すという行為は、
孤独で報われない営みのように見えるかもしれない。
それでも、それが“風景”となって残ることも、確かにあるのだ。
【第七章|それでも、問いを差し出す理由】
■ 希望としての問い
問いは、明快な答えを求めるためのものではない。
むしろ、すぐに答えが出ないからこそ、
問いは「生きている実感」と関わるのかもしれない。
この仕事を続ける中で、
わたしは何度も、問いが届かずに終わった場面に出会ってきた。
それでも、問いを差し出すという行為そのものが、
希望なのだと思う瞬間がある。
それは、相手の変化を期待しているのではない。
自分がどう在るか、自分がどんな“姿勢”で関わるか。
問いを差し出すことは、
その姿勢を確認し続ける行為でもある。
■ 声を荒らさず、問いを投げる
「問い」を届けるとき、つい力が入ってしまう。
「どうしてわかってくれないのか」と思うとき、
語気が強まってしまう。
それはたいてい、自分の“正しさ”にしがみついている時だった。
ほんとうの問いは、静かに差し出される。
声を荒らさずに投げられた問いは、
相手の中で時間をかけて響くかもしれない。
すぐに返事がなくてもいい。
反応が薄くても、意味がなかったわけじゃない。
「すぐに伝わる問い」だけが、本物ではない。
わたし自身が、「答えを急がないこと」に耐えられるかどうか。
その姿勢が、いつも問われている。
■ 問いを手放さずにいること
問いが返ってこなかったとき、
「もういい」と投げ出したくなることがある。
そう思いながら、わたしは完全に手放すことはできなかった。
問いは、相手のために差し出しているようでいて、
実は、自分自身の存在を支えるものでもあった。
わたしにとって、問いを持ち続けることは、
「信じる」ということと、どこかでつながっている。
問いを差し出すという姿勢を、
どれだけ踏みとどまって守り続けられるか。
それは、誰かの変化ではなく、
自分の「仕事」に対する信念そのものなのかもしれない。
【あとがき】
あらためて、当時のことを思い出しながら書き進めるうちに、
忘れかけていた感情や、言葉にならなかった違和感が、静かに浮かび上がってきました。
それは、わたし自身の姿勢を問い直す作業でもありました。
この一連の記録は、誰かを責めるためのものではなく、
問いを届けるという営みの中で、どのようにズレが生まれ、
どこで何かがすれ違っていったのかを、冷静に見つめ直すための備忘録です。
書きながら何度も立ち止まりました。
「わたしは、本当に誠実だったのか?」
「問いを差し出す準備は、できていたのか?」
そんな自問に向き合いながら、
あの時間を再訪したような感覚がありました。
これは、ある意味で、失敗の記録です。
でも、問いが届かなかったという経験が、
今のわたしの視点を形づくってくれたのだと思います。
問いは、ときに届かない。
それでも、問いを手放さずにいられる自分でありたい。
そう願いながら、これからもわたしたちは、
この営みを続けていきます。



