《 買うという心理 》
- 顧客の“現在地”から始めるマーケティング再設計 -
顧客の“現在地”から始める
マーケティング再設計
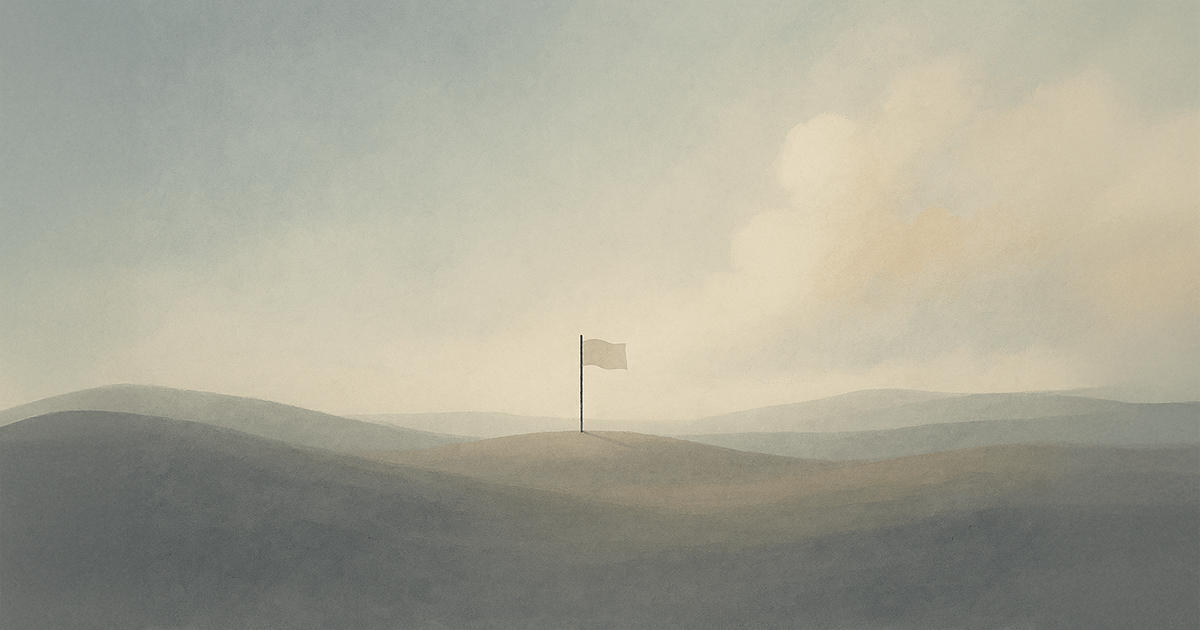
プロローグ:
「売るために、どう伝えるか」ではなく、「なぜ選ばれるのか」。
いま、マーケティングの重心は、構造の最適化から、関係の設計へと移行しつつある。
顧客は情報の過多に疲れ、納得できる文脈と“意味ある選択”を求めている。
本シリーズでは、AIDMAやSIPSといった購買心理モデルを表層的に扱うのではなく、「誰にとって、なぜ機能するのか」という問いを軸に据える。
マーケティングを“誘導”ではなく“橋渡し”としてとらえ直すことで、顧客の心理と行動のあいだに、確かな手応えをもたらす起点となるはずである。
Vol.0|なぜ、それを選んだのか?
— 顧客の“現在地”から始める -
■ モデルでは捉えきれない選択がある
人は、なぜそれを選んだのだろう?
誰かが何かを「買う」という行為には、必ず心理の動きがある。
AIDMAに代表されるような購買心理モデルは、その動きを言語化し、マーケティングに活かすために生まれてきた。
実際、モデルを知っているだけで、販促や接点設計の精度はぐっと上がる。だからこそ、知識として身につける意味は今も大きい。
ただ一方で、「最新のモデルはこれだ」と紹介されるフレームをそのまま使っても、成果が上がらない、あるいは離脱が増えるということも決して珍しくない。
なぜか? それは、「モデルが悪い」のではない。モデルが想定している“顧客の現在地”と、実際の顧客の心理がズレているからだ。
加えてもう一つ──そもそも提供している商品やサービスと、選んだ心理モデルの“相性自体”が合っていないケースもある。
モデルの設計思想と、プロダクトの性質が食い違っていれば、誘導どころか混乱を生むことすらある。
■ 「今、ユーザーはどこにいるのか?」
たとえば、ある人があなたのサイトを見ているとする。
この人は今、「興味」を持ちはじめたばかりなのか?
すでにいくつか比較検討した上で「記憶」の段階にいるのか?
それとも「行動」直前で、背中を押されたいだけなのか?
この“現在地”を誤って読むと、どんなにいい商品でも、どんなに響く言葉でも、ユーザーはページを静かに閉じてしまう。
購買モデルとは、誘導のフレームではなく、“感情の地図”だ。
この地図を「今、この人がどこに立っているのか」を知るために使うのが、本質的な役割なのだと思う。
■ そのモデル、本当に合ってますか?
たとえば、アプリのように繰り返し使うことが前提の商品と、
一度きりの購入がメインのプロダクトでは、顧客の心理プロセスはまったく違ってくる。
SaaS( Software as a Service )なら体験→継続→紹介までを意識したAARRRモデルが向いている。
一方で、情緒的な価値を持つアート作品やクラフト雑貨であれば、SIPSのような“共感・参加”型のプロセスの方が相性がいい。
モデルとは、“いつでも誰にでも使える汎用ツール”ではない。商材の性質や世界観にフィットしたものを選ぶ必要がある。
ここを見誤ると、心理の地図ではなく“地雷”になってしまうこともある。
■ 驚きは、異業種からやってくる
「同業他社がやっているから、うちもこのモデルで」と思い込むことは多い。
でも実際は、最も大きな競合が業界の外側に存在していることが多い。
たとえば、外食サービスの競合は、必ずしも他のレストランではない。
むしろ──
- 家にいながらすぐ届く「Uber Eats」
- 料理せずに済む「冷凍ミールキット」
- 外出そのものを遠ざける「Netflix」や「YouTube」
といった、“そもそも出かけない”という選択肢そのものが、最大のライバルかもしれない。
この視点を持つことで、顧客への届け方そのものが、根本から再設計されていく。
■ 服よりスマホ。交流よりゲーム。
いま若年層において、可処分所得や関心の使い方にも、はっきりとした変化がある。
- 服にはこだわらない
- メイクは最低限
- 飲み会にも行かない
- その代わり、スマホの通信費、サブスク、ゲーム課金にはしっかり投資する。
これは、「人と直接会う場」にお金を使わなくなった現れでもある。
外見ではなく、デジタル上の体験や自己表現に可処分リソースが流れている。
つまり、衣料ブランドの競合がゲームや音楽アプリになっているようなもの。業種が違うからといって、安心できる時代ではない。
■ 「売る姿勢」なくして、モデルは活きない
わたしは以前、《売るという姿勢》というコラムを書いた。
そこでは、マーケティングを「伝える技術」ではなく、「関係性の設計」として捉え直す必要があることを描いた。
購買心理モデルも同様に、誘導の道具ではなく、共感や納得を支える“橋”として使われるべきものだ。
それは同時に、顧客の“今の心理”と、“次の一歩を踏み出す感情”とをつなぐ、もうひとつの橋でもある。
この橋が適切に架けられていなければ、顧客はその先に進むことなく、ページを離れてしまう。
モデルを使う前に、問うべきことがある。
- 「自社の商品は、どのモデルと相性がいいのか?」
- 「今、顧客はどんな気持ちでここに来ているのか?」
- 「その競合は、本当に“同業者”なのか?」
そうした問いに丁寧に向き合った先にこそ、購買心理モデルは“図式”から“設計力”へと変わっていく。
Vol.1|購買心理は“型”ではなく“地図”である
Vol.1|購買心理は“型”ではなく
“地図”である
—関係の流れを読み解く視点 -
■ 型に頼ると、ユーザーが見えなくなる
マーケティングの現場では、「この心理モデルを使えばうまくいく」といった話がよく出てくる。
AIDMA、AISAS、SIPS、DECAX……。フレームとしての完成度は高く、整理もしやすい。だから導入しやすい。
とはいえ、それに頼りすぎると、肝心のユーザーの姿が見えなくなることがある。
なぜなら、購買心理モデルは“人の動き”ではなく、“人の心の動き”を扱っているからだ。
その人がいま何を感じていて、何をまだ感じていないのか。“型”でそれを完全にトレースするのは、どこか無理がある。
■ モデルはマニュアルではなく、地図
心理モデルは、行動の設計書ではない。
本質的には、顧客の感情の位置を確認するための“地図”のようなものだ。
いま、ユーザーはどこに立っているのか。
どこまで来ていて、どこで止まっているのか。
その「現在地」が見えなければ、次のステップを設計することもできない。
つまり、モデルは“誘導するもの”ではなく、“読み解くもの”であり、“気づくもの”だという視点が必要になる。
■ 「次に進めない」理由は、心理のつなぎ目にある
たとえば、AIDMAの流れに沿って考えると──
ユーザーが「Desire(欲求)」まで進んだのに、なぜか「Memory(記憶)」に残らず離脱してしまう。
このとき問題になるのは、Desireの質ではない。
DesireからMemoryへの“橋渡し”がなかったことにある。
気持ちの切れ目に、何も置かれていない。
共感も納得もないまま、ただ一歩を踏み出せずに終わる。
モデルを使いながらも、「心の連続性」を見落としてしまうことは、意外と多い。
■ 心理モデルは“関係性”を前提にした設計である
購買心理モデルは、感情を分解した図解に見えるかもしれない。
しかし本質的には、「誰かが何かを選ぶ」その関係の流れを見つめるツールだ。
そしてその流れは、商品やサービスが一方的に進めるものではない。ユーザーの理解度や関心度、コンディションによって常に揺れ動いている。
つまり、モデルは「設計の正解」ではなく、「関係の観察図」である。
図に従って動かすものではなく、図を見ながら“今、何が起きているか”を確かめるための視点装置なのだ。
■ 型にはめると、関係がこぼれる
もちろん、モデルを活用することで、設計の指針が持てるようになる。
しかし、フレームに当てはめることに夢中になってしまうと、いま目の前にいる顧客の感情のグラデーションが見えなくなる。
その瞬間、商品と顧客のあいだにあったはずの“関係”が、言葉にならずにこぼれ落ちる。
誰かの選択には、必ず“流れ”がある。
その流れをなぞるためにモデルを使うのか、モデルで仕切ってしまうのか。
その違いは、とても大きい。
■ 「今どこにいるのか」を見る力がすべての起点になる
購買心理モデルを活かすとは、「この人はいま、どこにいるのか?」という問いを丁寧に持ち続けることだ。
モデルを型として当てはめるのではなく、その型をいったん解いて、いまここにある関係の中で再構築していく。
この感覚さえ持てていれば、どのモデルを選ぶかはあまり重要ではなくなる。
モデルは道具であり、地図であり、会話の補助線である。
その本質を見失わない限り、どこまでも使える。
次の章では、代表的な購買心理モデル(AIDMA、AISAS、SIPSなど)を個別に整理しながら、それぞれの構造と活用のポイント、向いている業種について読み解いていく。
モデルを“選ぶ”のではなく、“活かす”ための視点で考えることをお勧めします。
Vol.2|モデルの誤読が、誘導ミスを生む
Vol.2|モデルの誤読が
誘導ミスを生む
— 自社の顧客に近いルートを照らす -
■ モデルを「選ぶ」ではなく「照らす」
購買心理モデルを活用するうえで大切なのは、「どれが正しいか」を決めることではない。
自社の商品やサービス、顧客の行動パターンを照らしたとき、どのモデルが“近い構造”としてヒントになるかを見極めることだ。
すべてを使う必要はない。
ただ、どれも一度は知っておいて損はない。
モデルは地図だ。いざというとき、ルートを見失わないための。
以下に、代表的な購買心理モデルを、構造・特徴・相性のよい業種・注意点とともに簡潔にまとめる。
■ AIDMA(アイドマ)
古典的・マス広告向き
- 流れ:
Attention(注意) → Interest(興味) → Desire(欲求) → Memory(記憶) → Action(行動)
- 特徴:
・マスメディア全盛時代に広く使われたモデル
・認知から購買までを段階的に整理
・情報を受け取る側が“受動的”であることが前提
- 向いている業種:
・日用品、食品、家電、保険、教育教材などのテレビ・チラシ・駅広告展開
・単価が中~高で、比較検討よりも記憶と印象が効くもの
- 注意点:
・ネット時代に入り、検索・比較・レビューといった“能動的な行動”が主流になっている
・使う場合は、記憶→行動までの補助設計が不可欠
■ AISAS(アイサス)
検索・シェア時代の標準形
- 流れ:
Attention → Interest → Search → Action → Share
- 特徴:
・ネットで検索する行動を前提に構成されたモデル
・行動後の“シェア”まで含むのが特徴
・ユーザーが情報を探す・広めることを重視
- 向いている業種:
・ガジェット、化粧品、家具、ECサイト、レビュー系商品
・情報検索と比較が活発な分野
- 注意点:
・検索に乗らない商品は、途中で止まる
・「Search」が起こるような入口設計が重要になる
■ SIPS(シップス)
共感・参加型ブランドに適応
- 流れ:
Sympathize(共感) → Identify(確認) → Participate(参加) → Share(共有) - 特徴:
・SNSやクラフトブランドなど、“世界観”が大切な商品に強い
・「使うこと」が目的ではなく、「関わること」に意味がある領域向き
- 向いている業種:
・クラフト雑貨、サステナブル系、ライフスタイルブランド、ローカルサービス
・顧客が“選ぶ理由”よりも“共鳴する関係”で成り立つ商材
- 注意点:
・広く共感されるかどうかよりも、誰と深くつながるかに重きを置く必要がある
・「共感疲れ」が起きると、自然に離脱される
■ DECAX(デキャックス)
コンテンツマーケ重視型
- 流れ:
Discover(発見) → Engage(関与) → Check(確認) → Action(行動) → eXperience(体験・共有) - 特徴:
・情報接触からエンゲージメント、体験共有までを想定したフロー
・コンテンツ経由で徐々に関係を深めていくモデル
- 向いている業種:
・コンサル、教育、ウェルネス、BtoB、SaaS系など、“売る前の理解”が必要なもの
・顧客が“選ぶ理由”よりも“共鳴する関係”で成り立つ商材
- 注意点:
・初動で「発見される」ことが最大のハードル
・時間軸が長いため、短期施策との併用が前提になる
■ AARRR(アー・アー・アール・アール)
サブスクリプションやアプリ向け
- 流れ:
Acquisition(獲得) → Activation(活性化) → Retention(継続) → Referral(紹介) → Revenue(収益) - 特徴:
・プロダクト主導型の事業に強い。ユーザーの“使い続ける体験”が前提
・デジタルプロダクトや課金モデルに特化した設計
- 向いている業種:
・アプリ、サブスク、Webサービス、ゲーム、SaaS、会員ビジネス全般
- 注意点:
・初期段階(獲得・活性化)に失敗すると、残りの流れが機能しない
・数字だけ追いすぎると、設計思想が浅くなるリスクもある
■ モデルは「正解」ではなく「仮説の地図」
ここで紹介したモデルたちは、あくまで“仮説の地図”だ。
どれを選ぶかではなく、どのモデルで見たときに、自社の顧客の行動がもっとも自然に理解できるか?
その視点で読み解くことが大切になる。
また、業種やサービス特性、提供者の姿勢によっては、複数のモデルが重なり合う“複合形態”になることもある。
次回はその「複合形態」についても触れていきます。
Vol.3|ビジネスモデルを探す?
— 他業種から学び、相性を馴染ませる-
■ モデルは、使うものではなく、馴染ませるもの
「いま注目されている購買心理モデルはどれですか?」
そう尋ねられることがある。
たしかにAIDMAから始まり、AISAS、SIPS、DECAX、AARRR……といったモデルは、それぞれ時代背景や技術進化に応じて登場してきた。
ただ──モデルの選定を、“最新かどうか”や“流行っているかどうか”という基準で決めてしまうと、見落とされるものがある。
それは、自分たちがどんな商品やサービスを提供しているかという前提だ。
そして何より、そのサービスが、誰のどんな「状況」に差し出されているのかという現実だ。
モデルを選ぶのではなく、今の自分たちのビジネスに、どのモデルが自然に馴染むかを見極める。
その姿勢こそが、これからのマーケティングに求められているのではないだろうか。
■ 他業種の方が、ヒントになることもある
たとえば、飲食店の競合は、ほかの飲食店とは限らない。
本当の意味でのライバルは、“その日、外に出るかどうか”という行動選択を左右する存在かもしれない。
つまり、動画サブスクやゲーム、Uber Eats。外出しないという選択肢そのものが、飲食店の売上に影響する可能性がある。
競争は、業種の中だけで起きているわけではない。
服の売上が伸び悩む理由も、洋服の質が落ちたからではない。若い世代が「服よりスマホ課金や通信費に可処分所得を使うようになった」ことも大きい。
交流の場そのものが少なければ、服にお金をかけるモチベーションは下がる。
この視点に立てば、「競合=同業種」という思い込みが、いかに視野を狭めていたかに気づく。
自分たちのビジネスが、顧客の“どんな選択肢”と並んでいるか?
この問いを立てることで、まったく異なるアプローチが見えてくるはずだ。
■ 相性の良さは、“扱う商品”と“届け方”で変わる
購買心理モデルには、それぞれ適した文脈がある。
たとえば、AIDMAのようなマスメディア前提のモデルは、一定の情報量を一方向的に届けられる構造に適している。
一方、SIPSは、SNS時代の共感ベースのモデル。
DECAXやAARRRは、継続的な関係や体験を通じた価値提供に強い。
問題は、それらのモデルが、自社の商品特性と噛み合っているかどうか。
瞬発力のあるキャンペーン商品なら、AIDMA型が有効かもしれない。
クラフトやライフスタイル系のプロダクトであれば、SIPSやDECAX。
SaaSやサブスクであれば、AARRRのような長期運用型のモデルが合ってくる。
そしてもちろん、顧客の“現在地”によって、同じ商品でも心理モデルは変わる。
たとえば、「ある人にとっては“検索”から入るプロセス」が、「別の人にとっては“共感”から始まる」こともある。
だから、万能なモデルなど存在しない。
■ 経営者の姿勢によって、モデルの馴染み方も変わる
「自分たちは、どんな人に、どんな価値を届けたいのか」
この問いを真剣に考えている経営者ほど、モデルの選び方も慎重だ。
たとえば、同じ飲食業でも──
“味”や“接客”の完成度で勝負する店もあれば、
“世界観”や“文化的価値”で共感をつくる店もある。
両者では、適した心理モデルが異なる。
つまり、業種だけで相性を決めるのではなく、サービスの個性や思想を含めた“全体像”で判断する必要がある。
その意味で、購買心理モデルは「答え」ではない。
あくまでも、「問いを深めるための補助線」として、柔軟に使うものなのだ。
■ モデルは、仮説であり、対話の入り口である
顧客の購買行動は、決してモデルどおりには進まない。
それでも、モデルを持っておく意味はある。なぜならそれは、顧客の心理状態と行動の接続点を“予測し、仮説を立てる”ためのものだからだ。
そしてその仮説は、マーケティングの施策だけでなく、接客やプロダクト設計、価格のあり方にまで影響する。
モデルを“運用する”のではなく、“顧客との対話を設計するための地図”として使う。
そうしたスタンスに立つとき、購買心理モデルは「売るための武器」ではなく、顧客との関係を少しだけスムーズにする橋として役立ち始めるのかもしれない。
■ 具体例:モデルの“馴染ませ方”
たとえば、こんなふうにモデルを“部分的に取り入れる”設計が考えられる。
ローカルカフェ
・SNSで世界観に共感させる(SIPS)
・来店前にメニュー検索を促す(AISAS)
オンライン英会話
・無料体験で学びの価値を実感(AARRR)
・教材動画で知識提供(DECAX)
ハンドメイドブランド
・職人ストーリーを届けて共鳴(SIPS)
・数量限定で記憶に残す(AIDMA)
BtoB SaaS
・ホワイトペーパーで課題提起(DECAX)
・トライアルで定着化(AARRR)
こうした具体例は、「自社ではどうだろう?」という思考をうながす起点になる。
一つのモデルにすべてを託すのではなく、今の顧客行動に照らしてどの段階が必要かを見極め、柔軟に組み合わせることが大切だ。
■ モデルは“選ぶ”ものではなく、“育てる”もの
フレームを一度導入したら終わり、ではない。
実践を重ねながら、顧客の反応やズレを観察し、別のモデルの要素を加えたり、段階を入れ替えたりすることもある。
その繰り返しのなかで、モデルは“仮説”から“習慣”へと育っていく。
やがて、自社の文脈に溶け込み、無理なく機能する“体温のある構造”として根づいていく。
購買心理モデルは、売るための型ではない。
顧客との関係を読み解き、整えるための「実用的な羅針盤」なのだ。
Vol.4|売るという姿勢と、購買心理の接続
Vol.4|売るという姿勢と
購買心理の接続
— モデルを“誘導”ではなく“橋渡し”に変える -
モデルを“誘導”ではなく
“橋渡し”に変える
■ 売ることは、関係をつくること
「売る」という言葉には、どこか構えてしまうような冷たさがある。
でも実際には、その行為の背後には、誰かに何かを届けたいという意図があるはずだ。
それは、“伝える”ことよりも、“関わる”ことに近い。
購買心理モデルも、本来はそうした関係性の中にある。
どの段階で、どんなふうに声をかければよいのか。
どうすれば、相手の今の気持ちに寄り添い、次のステップへと踏み出してもらえるのか。
それを読み解くための仮説が、モデルである。
■ モデルを「売り手目線」で見る危うさ
たとえば、「今この顧客はDesireにいるから、次はMemoryを促そう」と、誘導の手順としてモデルを使おうとすることがある。
一見、合理的なステップに見えるが、そこには“売り手目線”の強さが滲んでしまう。
顧客の心理は、機械的なフローでは動かない。むしろ、ちょっとした違和感や、説明しきれない躊躇によって止まることの方が多い。
だからこそ、モデルは「押し込む道順」ではなく、「相手の今いる場所を理解するための設計図」として捉え直す必要がある。
■ “橋をかける”というマーケティングの本質
購買心理モデルは、**現在の心理状態と、次に訪れる可能性のある心理状態をつなぐ“橋”**でもある。
たとえば、AIDMAの「Desire」の段階にいる顧客に対して、無理に「Action」へと促すのではなく、「Memory(記憶)」に残るような体験や印象を丁寧に設計することで、自然に行動へつながる道を整える。
この“架け橋”をどう築くかが、マーケティングの実践であり、それを担うのが「売るという姿勢」なのだと思う。
声のかけ方、届け方、タイミング。
どれも「正解」はなく、関係の中で変わり続ける。
■ 売る姿勢が、モデルに“熱”を与える
同じAIDMAでも、ただ順番通りに設計された導線と、「この人に本当に届けたい」と願う売り手の姿勢に裏打ちされた導線とでは、まったく異なる空気を持つ。
モデルは構造を示すもの。
でも、それを動かすのは、売り手の「在り方」なのかもしれない。
その在り方が、メッセージや世界観に“温度”を与える。
選ばれるブランドとは、モデルがうまく設計されているからではなく、そのモデルの運用に、姿勢の一貫性があるからだ。
つまり、「売るという姿勢」が、モデルの効果を左右する。
■ 購買心理モデルと、思想の接点
「売るという姿勢」は、思想に近い。
なぜこの商品を届けたいのか?
誰と、どんな関係をつくりたいのか?
その答えが定まっていないと、どんなに構造を整えても、伝わるものは薄くなる。
だからこそ、購買心理モデルは “選ばれるための技術” ではなく、“関係を築くための思想と構造の接続点” として扱われるべきだ。
そして、どんなに理論的に整っていても、最後に立ち上がるのは、「そのブランドや商品が、どんな未来を描こうとしているか」なのだ。
Vol.5|マーケティングの地平線に、“意味”を置く
Vol.5|マーケティングの地平線に
“意味”を置く
— 情報ではなく、世界観が選ばれる時代へ -
情報ではなく、世界観が選ばれる時代へ
■ いま、選ばれているのは「意味」かもしれない
モノもサービスも、どれを選んでもそこそこに満たされる時代。
「まずいものを探す方が難しい」という実感は、あながち誇張でもない。
だからこそ、最後の決め手はスペックでも価格でもなく、その商品やブランドがまとっている“意味”にあるのではないか。
誰かの暮らしの中で、何を語っているのか。
その商品と付き合うことで、どんな時間が流れるのか。
そうした見えにくいものが、選択を決める鍵になりつつある。
■ 情報の“最適化”では動かない感情
マーケティングの世界は長らく「情報の伝達」を主軸にしてきた。
誰に、何を、どう届けるか。その問いのもとで、多くの技術が洗練されてきた。
だが、情報の伝達が上手くなったからといって、人の心が自然と動くわけではない。
「正しさ」や「便利さ」では埋まらない何かが、今、問われている。
それは言い換えれば、「このブランドに触れたとき、自分がどうありたいか」という、極めて個人的な感覚の話かもしれない。
■ “買う”とは、意味に参加するという行為
たとえば、フェアトレードのチョコレートを買うとき。
人はその味やパッケージだけでなく、その背後にある倫理や物語に対して共鳴している。
あるいは、小さな雑貨店で見つけた一輪挿し。
それがどんな世界観の中で生まれ、どんな手で作られたのかを知ることで、ただの花器以上の意味が立ち上がってくる。
“買う”という行為は、そのブランドの価値観に参加するということ。
選択とは、共感のかたちのひとつなのだ。
■ マーケティングは「意味の設計」になっていく
今後、マーケティングにおける差異化の軸は、商品の性能や導線設計といった“外側の構造”だけでは不十分になる。
「このブランドは、なにを信じているのか?」
「どんな社会との関わり方をしているのか?」
「この世界に、どんな風景をもたらそうとしているのか?」
そうした“内側の輪郭”が、選ばれる理由になっていく。
それは、コンセプトを立てるだけでは成立しない。実践の中で一貫した振る舞いとして現れること。
その“意味の厚み”こそが、ブランドの地力になる。
■ 最後に選ばれるのは、「わたしにとっての意味」
どれだけ丁寧に設計されていても、その世界観が「わたしに関係ある」と感じられなければ、人は動かない。
だからこそ、マーケティングの言葉や構造は、“押しつけ”ではなく、“余白”をともなっている必要がある。
「この商品が、あなたの暮らしにどんな景色をもたらすか」
「その選択が、あなたの価値観にどう響くか」
そうした問いを、開いたまま残しておくこと。
それが、“意味を選ぶ”時代におけるマーケティングの姿勢なのかもしれない。



