■ 「プロセス」としての生の躍動
『マズローの向こうへ』が示す最も重要な視座は、
到達点を持たない運動の定義にある。
「これを失えば、自分ではなくなる」と
感じるほどの譲れない掟に沿って、
内側の源泉から動き続ける。
その「プロセスその物」にこそ、
私たちが追い求める生の躍動が宿るのである。
ルビンの壺の境界線上で、
自らの基調音を世界へと響かせ続けるこの運動は、
次章で述べる「世界への応答」という
実働へと繋がっていく。
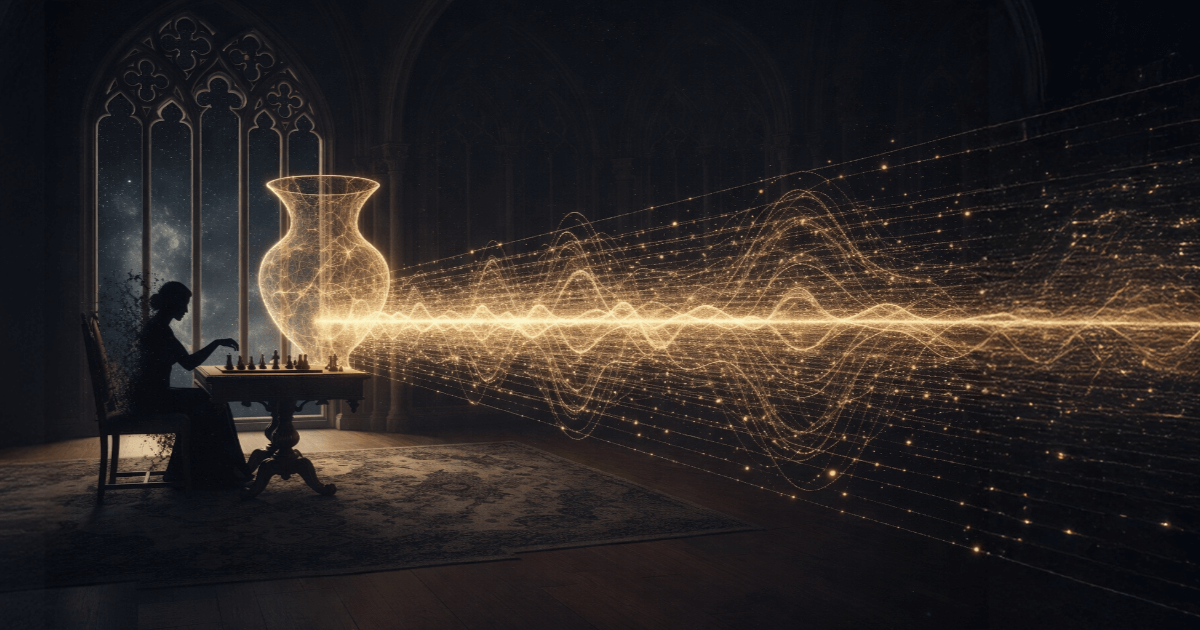
名目GDPの伸びと幸福度が相関しなくなるように、
過去の蓄積に基づく欲求の充足は、
ある地点で必ず限界を迎える。
コラム『マズローの向こうへ』において綴った通り、
階段を一段ずつ登るようなモデルは、
物質的な「欠乏」を埋めるための便宜的な地図に過ぎなかったのではないか。
私たちは「正解」とされる道を歩み、
自己実現という名の頂へ辿り着く。
だが、その達成の静寂の中で、
予期せぬ客人が訪れる事がある。
それは、
言いようのない虚無感であり、
身体を重く縛りつける「鬱」という感覚だ。
かつてユングは、鬱を「黒衣の婦人」に例えた。
彼女を追い払うのではなく、
客間に招き入れてもてなし、
その言い分を聞く事。
人生の正解を生き、
成功を手にした後に届くこの招待状は、
決して生命の敗北ではない。
むしろ、
エゴという小さな「図」が完成を見たと同時に、
その背景に隠されていた広大な「地(セルフ)」が、
自らを現そうとする反転の前兆なのではないか。
過去の蓄積による意味付けが通用しなくなったその場所は、
成長の終わりではない。
自らを「図」として固定する歩みを止め、
世界という「地」との相互浸食—
すなわち、
内側から突き上げる純度の高い欲求が、
既存の構造を震わせ始める始発点なのである。
私たちは、
自分という存在が自律した個体であり、
自らの意志で輪郭を描いていると信じて疑わない。
だが、その確信が揺らぎ、
エゴという「図」が機能不全に陥った時、
私たちは一つの奇妙な図形と向き合う事になる。
■ 境界線を共有する紐帯(ちゅうたい)
ルビンの壺を眺める時、私たちは図(壺)と地(背景)が、
実は一本の境界線を共有する「不可分の紐帯」である事を知る。
壺という形が成立するためには、
背景という「地」がその形を正確に、
かつ一分の狂いもなく譲り受けていなければならない。
一方が欠ければ、他方もまた消滅する。
この図形が突きつけてくるのは、
私たちが「自分の欲求」だと思い込んでいた物が、
実は背景としての「世界の構造」から要請された形であるという、
ある種不気味なほどの相補性だ。
自分という「図」は、単独で存在しているのではない。
世界という「地」との境界線そのものが、
今の自分を形作っているのである。
■ 「選ぶ私」の揺らぎと背景の再発見
ここで、コラム『応答の構造』Vol.0「自由という名の罠」を思い出してほしい。
そこでは、自らの意志で道を選び続けているはずなのに、
なぜか同じ風景に立ち戻ってしまう「居心地の悪さ」が語られていた。
このデジャヴのような閉塞感の正体こそ、まさにルビンの壺の「地」である。
私たちは「何を選ぶか」という図にばかり固執し、
自分をその形へと追い込んでいる「地の構造」を無視し続けてきたのではないか。
選択の自由を信じれば信じるほど、
その選択を成立させている背景(地)の引力に無意識に支配されてしまう。
虚無とは、エゴという図を凝視しすぎた結果、
その形を支えていた広大な「地」を見失った時に生じる摩擦なのだ。
■ 実存の反転と「地の要請」
内側から突き上げる純度の高い欲求は、
単なる個人の所有物ではない。
それは、
背景である世界が「私」という固有の余白を使い、
何かを表現しようとしている「地の要請」そのものなのだ。
図と地が反転するその瞬間、
私たちは「自分が生きている」という能動的な感覚から、
「構造に生かされている」という、
より大きな、
しかしどこか鋭い実存へと足を踏み入れる事になる。
それは『応答の構造』Vol.4で描かれた、
「選ぶ」と「選ばされる」の境界が消え、
世界と自分が互いに選び合っている事に気づく瞬間の感触とも重なっている。
世界が私に形を与え、私が世界の形を規定する。
この鏡合わせのような連関を認める所から、真の実働は始まるのである。
図と地の反転によって見えてきた物は、
自分という「図」を支える背景の存在であった。
コラム『マズローの向こうへ』において提示した通り、私たちが抱く欲求とは、
下から上へと一段ずつ登る「階段」のような単線的な構造ではない。
それは、
複数の欲求が同時に響き合い、
重なり合う「網の目」の構造をもっているのである。
■ 基調音としての「純度の高い欲求」
欲求の網の目が無秩序に崩れないのは、
全体をひとつにまとめる「内側の調律点」が存在するからだ。
これこそが、
本稿の核心である「純度の高い欲求」の正体である。
それは、
「これを失えば、自分ではなくなる」と感じるほどの、
内側の譲れない掟のような物だ。
日常の雑音に紛れていたこの基調音が、
成功の後の虚無という静寂の中で、
再びその鋭い響きを現すのである。
■ 自己組織化という生命の躍動
人がこの「純度の高い欲求」に従うとき、
内側では自然な秩序が立ち上がる。
この力学を組織に置き換えた物が「自己組織化」である。
外部からの指示や管理エネルギーに依存するのではなく、
構成員それぞれの「純度の高い欲求」と組織の大義が共鳴し合う事で、
全体に機能としての秩序が生まれる現象だ。
これは、
ピラミッドという単線的な図式を捨て、
個々の響き合いが全体を形作る
「生きた網の目」へと移行するプロセスに他ならない。
■ 「プロセス」としての生の躍動
『マズローの向こうへ』が示す最も重要な視座は、
到達点を持たない運動の定義にある。
「これを失えば、自分ではなくなる」と
感じるほどの譲れない掟に沿って、
内側の源泉から動き続ける。
その「プロセスその物」にこそ、
私たちが追い求める生の躍動が宿るのである。
ルビンの壺の境界線上で、
自らの基調音を世界へと響かせ続けるこの運動は、
次章で述べる「世界への応答」という
実働へと繋がっていく。
■ 響き合いのただ中に在る事
この振動(欲求)が極限まで高まった時、
人は没頭の状態に入る。
そこでは「選ぶ私」という意識を超え、
自らの基調音を世界という背景(地)へ響かせ、
また背景からの響きを受け取るという、
絶え間ない交流が起きている。
この「響き合いのただ中に在る事」こそが、
私たちが解き放つべき欲求の真の姿であり、
次章で述べる「世界への応答」という
実働の根源となるのである。
背景としての世界(地)を再発見し、
自らの欲求が「網の目」の構造をもった
振動であると定義したとき、
一つの視座が浮かび上がる。
それは、
私たちが求めているのは
「幸福」という名の
静止した状態ではなく、
今、
この瞬間の止まることのない
「身体の動き」その物である
という事実である。
■ 「意味の呼びかけ」に応じる内なる掟
『応答の構造』において綴った通り、
自由とは何物にも縛られない
恣意的な意志のことではない。
それは、
世界の側から絶えず発せられている
「意味の呼びかけ」に対し、
自分を自分たらしめる「内なる掟」を
以て応え続けている、
その状態を指す。
自らの内側にある「純度の高い欲求」を
基調音として、
世界という背景(地)から届く問いに、
自らの身体を以て応じていく。
この「応答」こそが、
単なる生存を超えた「実働」の正体である。
■ 動き続ける「プロセス」その物の肯定
『マズローの向こうへ』が提示した核心は、
成果や到達点に価値を置く
従来の目的論からの脱却にある。
「これを失えば、自分ではなくなる」と
感じるほどの譲れない掟に沿って、
内側の源泉から動き続ける。
その「プロセスその物」にこそ、
生命の本質的な躍動が宿っている。
図としてのエゴが完成や終わりを求めるのを止め、
地としての世界との絶え間ないやり取りに身を投じる。
この未完のまま進み続ける運動の中にこそ、
真の自由が存在する。
■ 不条理という背景との共鳴
ユングが説いた「黒衣の婦人」という虚無や、
世界のままならなさ(不条理)を客間に招き入れることも、
また一つの応答である。
それらを排除すべき障害と見なすのではなく、
自らの「基調音」を響かせるための「背景」として受け入れる。
自らの掟を世界に共鳴させ、
また世界からの響きを自らの掟に取り込んでいく。
そこにあるのは、終わりなき共創の連鎖である。
この身体的な応答を積み重ねること、
それ自体が「生きる」ということであり、
私たちが目指すべき「生成」としての実働なのである。
私たちは、自由とは
「自分の意志で何でも選べること」だと思い込んでいる。
しかし、
その恣意的な選択こそが、
実は自分を閉塞感へと追い込んでいたのではないか。
ここに至り、
自由の本質は「選択」から「応答」へと反転する。
■ 「選ばされる」ことの解放
『応答の構造』において重要な事実は、
自由とは意志の強さにあるのではなく、
世界の呼びかけに対して
「身体が勝手に動いてしまう」ような、
ある種の不可避な応答にあるという点だ。
自分が主導権を握って
「選んでいる(図)」という自意識が消え、
世界の構造(地)からの意味に、
自らの「内なる掟」が共鳴し、動き出してしまう。
このとき、主客の境界は消え、
人は「自らの意志」という狭い檻から解放される。
この「選ばされる」ような身体の動きこそが、
最も純度の高い自由の現れなのである。
■ 自己組織化という「実働」の規律
『マズローの向こうへ』が組織論として提示した「自己組織化」は、
個人の実存においても極めて厳格な規律として働く。
自己組織化とは、単なる放任ではない。
外部からの管理(指示や統制)を必要としないほど、
内側の「基調音(純度の高い欲求)」が明確であり、
それが周囲や背景と共鳴し合っている状態を指す。
自由とは、
好き勝手に振る舞うことではなく、
自らの「譲れない掟」に従い続けることで、
自律的に自らの秩序(形)を立ち上げ続ける
「実働」その物である。
この内側から立ち上がる秩序こそが、
社会の既存の構造に飲み込まれない唯一の盾となる。
■ 意味の網の目を生きる。
私たちが生きているのは、孤立した点ではない。
複数の欲求や他者の存在、
世界の不条理が複雑に重なり合う
「網の目」の中である。
この網の目の中で、
自らの「基調音」を響かせ、
世界からの微かな呼びかけに
身体的に応じ続けること。
その連続的なプロセスの中にこそ、
生の実感は宿る。
それは、
どこか安全な場所へ辿り着くための手段ではなく、
この複雑な網の目そのものを、
自らの掟を以て編み直していく「生成」のプロセスである。
自由とは、
そのような終わりなき応答の連鎖、
すなわち「実働」の中にしか存在しないのである。
私たちは、
正解が書かれた「完成された地図」を求めて彷徨ってきた。
しかし、
自らの「内なる掟」に目覚め、
世界との応答を始めた時、
地図は、
自ら歩む足跡によって事後的に描かれる
「生成の地図」へと姿を変える。
■ 「不足を埋める」から「源泉から動く」への転換
マズローのピラミッドが象徴していたのは、
足りない物を外部から補い、
頂点というゴールを目指す「欠乏」の力学であった。
だが、
私たちが辿り着いた事実は、その逆である。
「これを失えば、自分ではなくなる」という
内側の源泉(純度の高い欲求)から動き出す時、
人生は不足を埋める作業ではなく、
内側から溢れ出すエネルギーの横溢となる。
この
「源泉に沿って動き続けるプロセス」こそが、
私たちが生きるべき実働の基盤である。
■ 自己組織化される「実存の秩序」
この実働は、
個人の内側に閉じない。
個が自らの「基調音」を響かせ、
世界という「網の目」の中で
他者や場と共鳴し合う時、
そこに外部の統制によらない
「自己組織化」された秩序が立ち上がる。
自由とは、
社会が用意した選択肢から選ぶことではなく、
自らの掟と世界の呼びかけが交差する地点で、
自律的に自らの形(秩序)を更新し続ける
規律のことである。
それは、
静止した「自己実現」ではなく、
動きながら形を変え続ける
「動的な均衡」としての生である。
私たちは、
自らの内側にある「純度の高い欲求」という
基調音に耳を澄まし、
世界という広大な背景(地)からの
呼びかけに応答する術を学んだ。
このプロセスには、
あらかじめ用意された終着点も、
完成を約束された地図も存在しない。
■ 「生」という名の応答を続ける
『マズローの向こうへ』と
『応答の構造』が
交差する地点で見出した物は、
所有すべき「幸福」という状態ではなく、
動き続ける「身体」その物であった。
自らの譲れない掟を携え、
不条理や虚無さえも共鳴の材料として
引き受けながら、一歩を踏み出し続ける。
その
絶え間ない応答の集積こそが、
かつて私たちが「自分」と
呼んでいた物の正体であり、
それが世界という網の目を
刻一刻と編み変えていく実働となるのである。
■ 響き合う網の目の中で
ピラミッドの頂点を目指す
孤独な競争は終わりを告げた。
これからは、
個々が自らの基調音を誇り高く響かせ、
互いに自己組織化しながら、
予測不能なハーモニーを奏でていく時代である。
自らの輪郭を世界に委ね、
同時に世界を自らの意志で彩る。
このルビンの壺の境界線上で行われる
終わりなきダンスこそが、
私たちが獲得した真の自由の姿に他ならない。
■ 生成は続いていく
この言語化の試み自体もまた、
一つの大きな応答であった。
書かれた言葉は固定された真理ではなく、
次なる実働を呼び起こすための新たな「呼びかけ」である。
私たちは、未完の地図を手に、
再び現実という名の場へと戻っていく。
そこには常に、新しい意味の響きと、
それに応じるための「身体の動き」が待っている。
生成は、止まる事を知らない。
私たちの実働は、
今、この瞬間から
再び始まっていくのである。

「うちは風通しがいいって、言われるんですよね」
彼はそう語ったあと、自分でその言葉に小さく首をかしげた。
それはたしかに“そういう空気”でつくられた職場だった。
笑顔もある。報連相もある。反論も一応できる。
でも、どこかが不自然だった。
誰かが本当に迷っているとき、
誰かが納得していないとき、
誰も、口を開かない。
議論の場では意見が出る。
しかし、それは「言っていいこと」の範囲を出ない。
「何か言いにくいことって、ありますか?」
ある日、そう訊かれたとき、
彼は反射的に「特にないですね」と答えた。
でもそのあと、なぜか胸のあたりがざわついた。
“自分自身も、誰かにとっての言いにくさの一部なのかもしれない”
そんな思いが、ふと頭をよぎった。
問いが届くとは、どういうことなのか。
それは、「答えられる問い」に出会うことではなかった。
むしろ、自分が見ていなかった視点が、
急に目の前に差し出されるようなことだった。
セッションのあと、
彼は部下と話すときの自分の表情が、気になるようになった。
口を挟むタイミングが、一瞬だけ遅れるようになった。
自覚的なのか、無自覚なのかはわからない。
ただ、以前とは違って、そこを“観察”している自分がいる事は、なんとなく感じている。
風通しをつくっている“つもり”と、
風が通っている“実感”のあいだには、
ずいぶん距離があることに、ようやく気づき始めたところだ。

特に困っているわけではなかった。
仕事も順調で、それなりに任されていたし、
人間関係も大きな問題はなかった。
強いて言えば、忙しさのわりに、
手応えがある日とそうでない日の差が、
最近ちょっと大きい気がしていた。
セッション前に送られてきたコラムを、
移動中に軽い気持ちで開いて読んでいた。
そこで出てきた問いのような一文に、
なぜかスクロールが止まった。
内容はよく覚えていないけれど、
「自分で選んでいると思ってたけど、本当にそうだろうか」
みたいなことが書いてあって、
なんとなく、それだけが残った。
考えたくて残ったわけじゃない。
たぶん、“思い出させられた”のだと思う。
日々の中で、考えないようにしてきたことを。
べつに答えが欲しいわけじゃなかった。
問いそのものが、ただ残っていた。
あの日から、何かが始まった──
……ような気がしている。
でもそれも、まだよくわからないまま、日々が流れている。

彼女は完璧だった。
資料は整理され、言語化も抜群。
最新のリーダーシップ論も、セルフコーチングも習得済み。
部下の話も最後まで聞くし、自己開示も忘れない。
“できている”はずだった。
なのに、どこかでいつも空回っていた。
目の前のチームが“本当に動き出す感覚”が、ずっと訪れなかった。
信じている理念もある。
正しいはずの姿勢もある。
でも、何かがつながらない。
自分だけが深呼吸をして、まわりは息を止めているような空気。
「みんなは、今、何を感じてるんだろう?」
それを誰にも聞けないまま、数ヶ月が過ぎた。
ある日、セッションで問いかけられた。
「あなたが“うまくいっている”と信じている、そのやり方は、あなたのものですか?」
彼女は、すぐには答えられなかった。
気づけば、やってきたことのほとんどが
“良いと言われてきたもの”をなぞることだった。
その問いは、答えを求めていなかった。
ただ、自分に静かに根を張っていく感じがした。
すぐに何かが変わったわけではない。
でも最近、
言葉が出てこないとき、黙っていることを自分に許せるようになった。
問いのないまま語るよりも、問いを残したまま立ち止まるほうが、
本当はずっと勇気のいる行為だったことを、いま少しだけ実感している。

彼は、いつも正解を持っていた。
部下に示す指針、顧客への回答、家族のための決断。
迷う前に動くことが、美徳だと信じていた。
ある日、「問いに向き合うセッション」があると聞いた。
正直、それが何の役に立つのか、すぐには分からなかった。
でも気づけば、彼はその場にいた。
セッションの帰り道、手元に答えはなかった。
ただ、一枚の紙に書かれていた問いが、頭から離れなかった。
──「誰に見せるための“正しさ”を演じていますか?」
その問いは、数日経っても消えなかった。
会議中、ふとした沈黙のとき、夜に一人でお酒を飲むとき。
誰にも言えないまま、彼の中でその問いは形を変えながら残りつづけた。
半年後。
彼はまだ、その問いに明確な答えを持っていない。
けれど、何かを決めるときの速度が少しだけ遅くなった。
立ち止まり、問いを思い出す時間ができた。
そして最近、部下にこう言われた。
「……最近、課長って、なんか言いかけて止めるときありますよね」
彼は笑ってごまかしたけれど、内心ではわかっていた。
その“言いかけた言葉”の裏に、問いがある。
それはまだ形にならないけれど、確かに自分の中に居座っている。