《 マネジメントの地形》
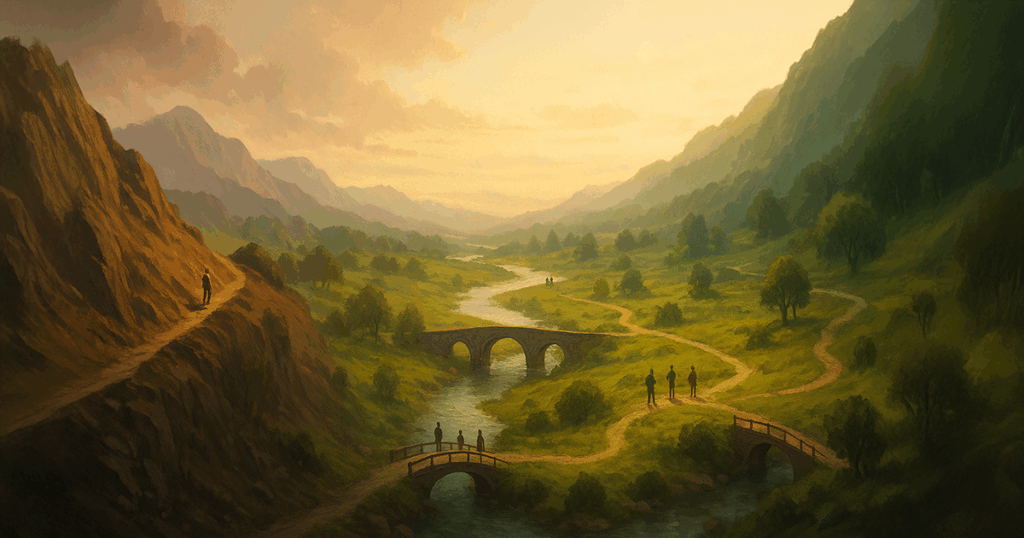
プロローグ:
計画を立て、誘惑に打ち克ち、自分を律する──。
私たちはいつからか、それを「できる人」の証だと信じてきた。
だが、社会に出た今、問われる力は変わっている。
“誰に、何を委ねるか”
“どんな仕組みをつくるか”
マネジメントとは、意志や根性の問題ではない。
環境を見つめ、関係性を設計する視点から、
新しい地形が、いま立ち上がろうとしている。
Vol.0|「セルフマネジメント神話」と委ねる力の再構築
■ 小さな「律しなさい」から始まった神話
たとえば、小学生の頃。
「計画を立てなさい」と繰り返し言われていた。
夏休みの宿題、受験勉強、試験対策。
その頃からずっと、
“できる人=自分を律せる人”という図式が、
静かに、そして確実に、自分の中に根を下ろしていた。
とはいえ──
それは本当に正しい「マネジメント」の物語なのだろうか?
■ 受験がつくり出す「セルフマネジメント神話」
受験で成果を上げた経験は、
ときに人生の誇りとなる。
スケジュールを管理し、誘惑を断ち、集中を保つ。
自分ひとりで立てた計画に自分で責任を持ち、
合格という明確なゴールに突き進んだ記憶は、
「自分はできる」というアイデンティティを
強く支えてくれる。
だがその成功体験が、
「他者の力を借りる」という発想を
どこかで無効化してしまっているとしたら──?
■ ビジネスに必要なのは、他者に委ねる力
ビジネスの現場は、受験とはまるで異なる。
- ゴールは常に変化する
- 人と状況によって優先順位が揺れ動く
- 予測不可能な出来事が頻発する
こうした複雑性の中で必要なのは、
「一人で何でもやる力」ではなく、
「誰に何を委ね、どんな仕組みをつくるか」という視点だ。
つまり、マネジメントとは単に自分を律することではなく、
“管理を外在化し、他者の力を活かす設計力”でもある。
■ 委ねる力が、次の地平へ導く
「スケジュール管理が苦手」と自覚していることは、
決して劣等感ではない。
それはむしろ、
“どこを他者に委ねるべきか”を見極める出発点だ。
セルフマネジメントの限界を知っている人ほど、
他者との協働や委任の価値を理解している。
その視点を持つ人こそ、
複雑で動的なビジネス世界を進むことができる。
「自分を律すること」が
本当に「できる人」の条件だろうか?むしろ、
「自分にできないことを誰に委ねるか」を知っている人こそ、
次の地平を見ているのではないか──。
Vol.1|「“できる”ことの呪い」
— 受験エリートが見落とす、マネジメントの地形 ─
■ スケジュール管理が苦手だった頃の話
小さい頃から、
スケジュールを立てるのが苦手だった。
夏休みの宿題、定期テストの勉強、受験の計画。
「計画倒れ」「三日坊主」「後回し」。
そんな言葉に、ずっと心当たりがあった。
そして、自分は「ちゃんとできる人間じゃない」んだ、
とどこかで思っていた。
でもその一方で、こうも思っていた──
「できる人たちは、セルフマネジメントがうまいんだ」と。
■ “できる人”=“自分を律せる人”という図式
塾、模試、進路指導。
どこに行っても言われたのは、「計画が大事」ということ。
そして、
「自分で立てた計画を自分で守れる人が、強い」という前提。
確かに、それで成果を出している人もいた。
勉強をルーティン化し、誘惑に負けず、合格を手にする。
その姿は、
“理想の人間像”として何度も提示された。
やがて、こんな図式が静かに根を張っていく──
「できる人」=「自分を律せる人」=「マネジメントができる人」
■ セルフマネジメント信仰の起点としての受験
でも、今あらためて思う。
この図式は、どこまで本当だったのだろう?
受験は、ある意味で極めて“閉じられた環境”だ。
- ゴールは明確
- 範囲は限定的
- 競争は個人単位
だからこそ、
“自分との戦い”という構図が有効だったのかもしれない。
とはいえ、社会に出てからはそうはいかない。
仕事はもっと複雑で、変化が多く、他者との連携を前提としている。
その世界において、
「受験的成功体験」をそのまま適用することはできるのか?
それでもなお、
「できる人はセルフマネジメントがうまい」と言えるのか?
■ “構造”を見落とさせる成功体験
振り返ってみれば、
自分で何もかもやりきったという受験の成功体験は、
どこかで「他者の力を借りる」という発想を
閉ざしていたのかもしれない。
- 誰に、何を、どう委ねるか
- 仕組みや構造をどう設計するか
- 行動を支える環境はどうあるべきか
そうした問いを持つよりも前に、
「まず自分が頑張るべき」というセルフマネジメント信仰が
前提になっていた。
それは、ある種の誇りでもあり、
同時に──
視野を狭める呪いでもあったのではないか。
■備忘録|“できた過去”が問いを止めてしまうとき
「自分はできるはずだ」
「これまでもやってきた」
「だから、もっとやれる」
そう思えることは、ときに強さになる。
とはいえ、それが問いを止めてしまう瞬間がある。
本当にこの方法でいいのか?
今の自分に合った構造は何なのか?
「できる前提」をいったん手放さない限り、
そうした問いが立ち上がらないまま進んでしまうこともある。
“できること”が、
“見えなくさせているもの”はないだろうか。
Vol.2|集中できないのは、意志が弱いからか?
— 意志 vs. 設計:勝てない戦いの構図 -
■ 「やる気」の限界
「集中力が続かない」「モチベーションが上がらない」
そんな自分を責めたことが、何度あっただろう。
予定通りに進まなかった日は、
怠けたような、意志が弱かったような、
そんな後ろめたさだけが残る。
「やればできる」なんて言葉に、
どこか励まされてきたはずなのに、
気がつけば、それが自分を追い込む呪文になっていた。
■ 意志だけが頼りだった時代
思い返してみると、あの頃は、
意志の力だけが頼りだった気がする。
時間を決め、気合を入れ、
誘惑を断ち、机に向かい続ける。
「やる気」と「根性」で何とかなると、
そう思い込まないと、続けられなかった。
でも、それは「仕組み」が不在だっただけではなかったか?
■「仕組み」という見えない支援
今振り返ると、
意志でどうにもならなかった瞬間こそ、
仕組みで支えるべきだったサインだったのかもしれない。
- 集中できない日があるのは当たり前
- 人によって得意な時間帯も違う
- 習慣化には「設計」と「外部刺激」が必要
こうした視点が当たり前になった今、
あの頃の自分は、少し気の毒に思える。
「できないのは、自分が弱いせい」としか思えなかったからだ。
■ マネジメントとは、「仕組みへのまなざし」
マネジメントの基本は、仕組みを見ることだ。
「なぜうまくいかないか」を、人ではなく構造から問う視点。
誰かの意志が弱いからではなく、
仕組みが支えていないからでは? と考えられる力。
そういう意味では、セルフマネジメントの第一歩も、
「意志を強く持つこと」ではないのかもしれない。
それよりもむしろ、
「自分がどこでつまずきやすいか」を知ること、
「どうすれば自然に続く仕組みができるか」を考えること。
その設計力こそが、マネジメントの入り口になっていく。
■ 備忘録|その視点の先に
“気合でやりきるしかない”という時代を通ってきたからこそ、
今の自分が持てる視点があるのだとすれば──
意志はもちろん、大切だ。
とはいえ、そこにすべてを預けることの危うさもまた、
かつての自分は身をもって知っているはずだ。
もしあの頃に戻れるなら、
もう少し、仕組みに甘えてもよかったのではないか。
あの「できなさ」は、きっと、
ひとりで背負うべきものじゃなかったのかもしれない。
Vol.3|「名選手、名監督にあらず」
— “できる人”ほどマネジメントを誤解する -
■ 「なぜ、こんなこともできないのか」
誰かに何かを頼んで、思うように進まないとき。
つい、そんな言葉が喉元まで出かかる。
「なんで、これくらいのことが分からないのか」
「なぜ、自分のように動けないのか」
でも、それを言葉にしてしまった瞬間、
何か大切なものを取りこぼしてしまう気がする。
■ 「できた人」に起こる、記憶の喪失
“名選手、名監督にあらず”。
よく知られた言葉だ。
優秀なプレイヤーが、
必ずしも優れた指導者にはなれないという。
そこには、構造的な盲点がある。
「自分ができるようになったとき、
人は“できなかった頃”の記憶を失う」という事実だ。
- なぜ、自分がその行動を取れたのか
- 何が、集中や継続を支えてくれたのか
- どんな失敗を経て、そこにたどり着いたのか
こうしたプロセスの細部は、
意外なほどに、すっぽり抜け落ちてしまう。
その結果、
「できない人」の行動が理解できなくなる。
■ 感覚ではなく、構造で教えるということ
マネジメントには、
「自分の感覚の翻訳力」が求められる。
「自分にとっての“当たり前”は、
他者にとってどう見えているか」
それを常に問い直す視点がなければ、
教えることも、任せることもできない。
- なぜ今このタスクが滞っているのか?
- 何が伝わっていないのか?
- どの前提が共有されていないのか?
それを“感覚”ではなく、
“構造”で捉える目線が必要になる。
そうでなければ、
「できない人を責めるマネジメント」に陥ってしまう。
■ 成功体験を“脇に置く”
皮肉なことに、
「自分はちゃんとやれた」経験が、
マネジメントの邪魔をする。
できるようになった人は、無意識にこう思ってしまう。
「自分ができたんだから、誰でもできるはずだ」と。
でもそれは、ただの“感覚の一般化”であって、
他者の事情や構造を見ようとしない視点にすぎない。
マネジメントとは、
自分の成功体験を“武器”にするのではなく、
一度“脇に置く”ことから始まるのかもしれない。
備忘録|翻訳されない優秀さの行方
「どうしてあの人は、こんなに頑張っているのに、伝わらないのか」
「どうしてこのやり方が、他の人には響かないのか」
そう感じる場面があるなら──
もしかすると、それは“自分の感覚”が前提になっているサインかもしれない。
感覚を持つことは、強みになる。
でも、それを他者に伝えるには、構造という橋が要る。
その橋をつくることが、マネジメントなのだとしたら。
あなたは今、
自分の「できる」を、誰かにどう渡そうとしているだろうか?
Vol.4|任せる技術は、預ける勇気
— マネジメントにおける“信頼”と“分離” -
■ 「自分がやった方が早い」は、いつから口癖になったのか
誰かに任せたとき、思うように進まなかった経験。
説明に時間がかかるくらいなら、
最初から自分でやった方が早い──
そんなふうにして、
いつしか仕事を抱え込んでしまう。
でも、それって本当に「合理的な判断」だったのだろうか?
もしかするとそこには、
言語化できない“不安”や“諦め”が絡んでいるのかもしれない。
■ 感情と業務の境界線
任せることが苦手な人ほど、実は、
「うまくいかなかったときの感情処理」に傷ついている。
- 中途半端な成果が返ってくる
- 頼んだ相手がその場を離れてしまう
- 責任が自分に跳ね返ってくる
そういった経験の積み重ねが、
「信頼」へのハードルを上げてしまう。
気づけば、任せることそのものが怖くなり、
責任と感情の境界線が、曖昧になっていく。
■ 「信頼」の設計には、“分離”が要る
任せるという行為には、
タスクと感情を分けて捉える力が必要になる。
- 任せたタスクの“完成度”は、感情の“評価”と切り離す
- うまくいかなかったときは、「構造」に立ち返る
- 責任の所在と、感情の流れを混同しない
この“分離”を保つことが、任せるための土台になる。
逆に言えば、それが曖昧なままだと、
いつまで経っても「任せられない」構造に戻ってしまう。
■ 委ねることは、設計であり訓練でもある
任せることは、気合や度胸でできるものじゃない。
そこには、手順・前提・期待値の設計が必要で、
何より、任せる側にも“訓練”が要る。
- どこまで伝えるか
- 何を見守り、どこで手放すか
- 失敗があったときにどうフォローするか
こうした構造の積み重ねがあって、
ようやく「任せる力」が育っていく。
備忘録|委ねることの、内側にあるもの
「自分がやった方が早い」と思ったとき、
それはただの効率の問題ではないのかもしれない。
- 説明するのが面倒
- うまくいかなかったときにイラッとする
- 失敗したら自分の責任になるのが怖い
そうした感情の地層が、
任せるという行為の下に静かに積もっている。
それでも──
委ねることを避け続ける限り、
“ひとりで抱え込む”構造は変わらない。
あなたは今、
「手放せていないもの」に、どんな感情が絡んでいるだろう?
Vol.5|セルフマネジメントという幻想
— 一人で抱え込まないマネジメントのために -
■ 「自分でやるべき」を前提にしていないか?
何かうまくいかないとき、
「もっとしっかりしなきゃ」「自分が弱いんだ」と思ってしまう。
自分を律すること、自分で完結することに、
“できる人”であるための条件を感じてきた。
それでも、それはいつから自分の中に根づいたのだろう。
「誰にも迷惑をかけないように」
「自分のことは自分でやる」──
そんな言葉の蓄積が、気づかないうちに
“ひとりでなんとかする”という幻想を形づくっていたのかもしれない。
■ 環境に委ねることは、敗北ではない
スケジュールが崩れる。
やるべきことが後回しになる。
そのたびに「自分はだめだ」と思ってしまう構造。
とはいえ、
もしかすると必要なのは「自分を責めること」ではなく、
環境や仕組みを見直すという、もうひとつの視点なのではないか。
完璧にできる自分を前提にせず、
忘れることもある、揺らぐこともある、という前提からはじめる。
そのときはじめて、
“管理されること”を恐れない働き方が立ち上がってくる。
■ リーダーとは、「整える人」かもしれない
「強くあれ」「迷うな」「人を引っ張れ」と言われてきたリーダー像。
でも本当に求められているのは、
“弱さ”を抱えたチームが滞りなく回るための、設計と配慮なのかもしれない。
たとえば──
感情に溺れずに判断できるよう、冷静な人にスケジューリングを任せる。
集中できる時間帯に合わせて、打ち合わせを設計する。
疲れているメンバーの分まで誰かが抱えるのではなく、業務の流れ自体を見直す。
そうした 「関係性と循環を整える力」 は、
声を張り上げるリーダーとは、まるで違う風景をつくる。
備忘録|“問い”を手放さずにいること
ひとりで背負い続けることが、
ほんとうに“強さ”だろうか。
それとも──
“誰かと設計を分かち合えること”こそが、
時代にふさわしいマネジメントなのだろうか。
名乗らずとも、誰かの歩みを静かに支える人たちがいる。
声高に語らずとも、整えることで未来をつくっていく人たちがいる。
そんな存在を、
いつか“リーダー”と呼べる時代が来るのかもしれない。



