《 親心と焦りのあいだで 》
- 変容を急かしてしまった日 -
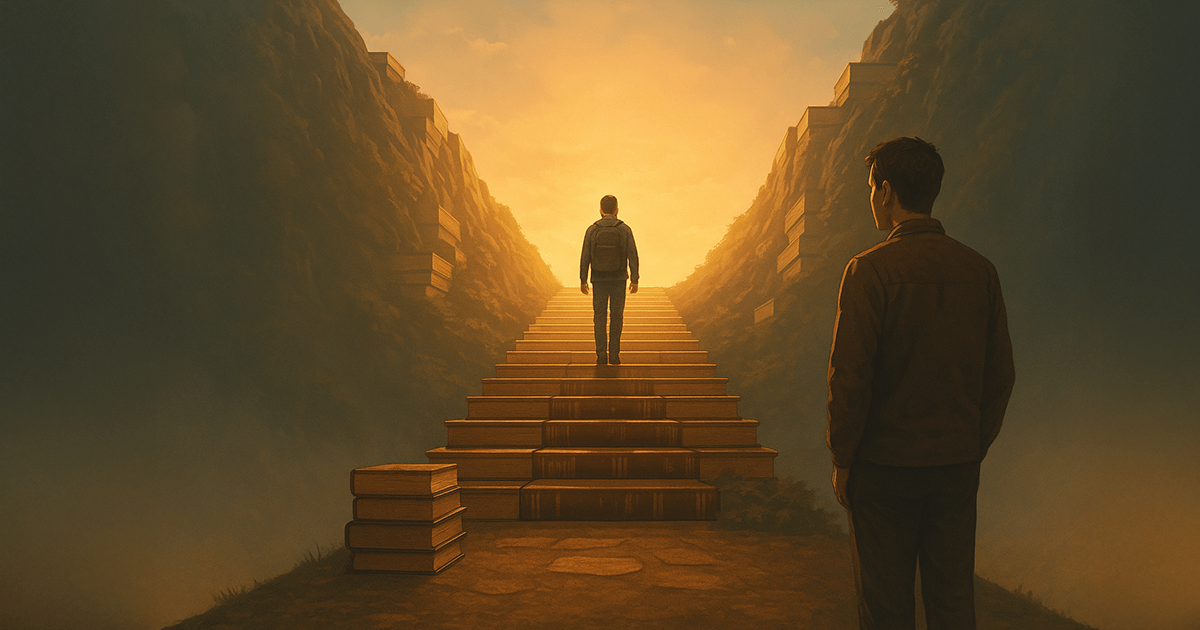
プロローグ:
誰かの可能性を信じたとき、人はどこまで寄り添えるのだろう。
うまくいってほしい、間に合わせてあげたい。そんな思いが募るほど、知らず知らずのうちに、わたしは焦りを相手に投げかけていた。
支えたつもりが、押していたのかもしれない。
これは、信じようとしたわたしが「信じきれなかった」ことをめぐる、ある失敗の記録である。
そしてその先に見えてきた、“信じる”という行為の、静かで新しい輪郭についての話でもある。
Vol.0|参考書の山と、切実さの不在
Vol.0|参考書の山と
切実さの不在
— 信じたいのに、信じきれなかったときの話 -
信じたいのに
信じきれなかったときの話
■「どう考えても間に合わない」現実
志望校に合格するために用意された参考書の山。
一冊ひとつひとつは決して不可能ではない。ただ、すべてを網羅するには、どう逆立ちしても時間が足りない。
いまの実力と状況を冷静に見れば、そのギャップは明らかだった。
そんな山の前に立って、「大丈夫っすよ」と笑う若者がいる。
口ぶりはポジティブで、堂々としているようにも見える。
でも、内心でわたしはずっとザワついていた。
「いや、本当にわかってる?」
「このままだと間に合わないかもしれないよ」
声には出さないまま、心の中で問いが浮かび、消えずに残った。
■“ちゃんとしているつもり”という無自覚
目の前にいたその人は、あるプロジェクトの中心を担う立場にいた。
自ら希望して始めた挑戦でもあり、本人の中にも思いはあったと思う。ただ、それ以上に目についたのは「自己認識とのズレ」だった。
本人は、自分なりにやれている感覚でいた。
「今はこれくらいで大丈夫」「そのうち仕上げます」
言葉にすれば確かに前向きだし、自信もありそうに見える。ただ、行動は伴っていなかった。
課題は山積みで、動きは鈍く、何よりも切実さが感じられなかった。
わたしから見れば、目の前の状況はもうギリギリだった。
それでも、彼の中にはたしかに可能性があった。
わたしはその光を見ていたし、「いけるかもしれない」と本気で思っていた。
だからこそ、余計に焦ってしまったのだと思う。
■“親ではない”という距離感のもどかしさ
関係性としては、わたしは彼の「支援者」「伴走者」という立場だった。
一緒に走ることはできても、引っ張ることはできない。
指示を出すことも、叱ることも、契約上はできるかもしれない。ただ、それはきっと、彼の自発性を削ぐことになる。
わかっている。頭ではちゃんと理解していた。ただ現実は、甘くなかった。
彼の動きが鈍いまま時間が過ぎていくのを見ていると、どうしても「このままでは間に合わない」という思いが先に立った。
そしてわたしは、つい“伴走者”ではなく、“推進者”として接してしまった。
焦りが、確実に滲み出していたと思う。
本来なら彼の内側から芽生えるべき切実さを、外から揺さぶって引き出そうとするような関わりになっていた。
そして今になって思うのは、「このままじゃ間に合わない」と思っていたのは、彼ではなく、わたしのほうだったのだということだ。
Vol.1|可能性があるからこそ…
— 信じていたのに、なぜ急かしてしまったのか -
信じていたのに
なぜ急かしてしまったのか
■「彼ならいける」と思っていた
わたしは彼の中にある、まだ見ぬ力を確かに感じていた。
言語化されていない思考の深さや、曖昧な感覚の扱い方、理屈ではなく感覚で空気を読むような繊細さ──
派手さやスピード感には欠ける。ただ、ちゃんと磨けば、まったく別次元の光を放つような、そんな資質が見えていた。
「彼ならいける」と思っていた。
いや、「いってほしい」と、どこかで強く願っていたのかもしれない。
■“信じる”と“期待する”は、似て非なる
信じるとは、なんだろうか──。
この頃、何度も自分にそう問いかけていた。
彼の中にある種を、信じていた。
だからこそ、それが発芽しないまま終わってしまうことが、どうしても怖かった。
でも、今思えば、わたしの中には“信じる”というより“期待する”気持ちが混ざっていたように思う。
- このタイミングで開花してくれたら。
- ここまで来たら、さすがに動くだろう。
- 今の状況を見たら、さすがに危機感を持つはず。
そうやって、彼の内側のプロセスを、どこかで「都合よく運ばれるもの」として見ていた節がある。
■「間に合わないかもしれない」という焦り
一緒に走り出したプロジェクトは、時間が限られていた。
やるべきこと、整えるべきこと、積み上げるべきもの──それらは冷静に見れば、簡単に終わる量ではなかった。
そして、進捗が思うように動かない中で、彼の様子に「今のままでも大丈夫」という空気が漂っていることが、わたしにはどうしても引っかかっていた。
「このペースじゃ、間に合わない」
そう思う気持ちが、日に日に強くなった。
そして、その焦りが、わたしの関わり方を変えていった。
■「急かしたくない」と思いながら、急かしていた
わたしは、彼を焦らせたくなかった。
せかされたり、詰められたりすることで失われてしまうような繊細な感性を、彼は持っていたから。
「彼のペースでいこう」と何度も言葉にしたし、実際にそう振る舞おうとしていた。ただ、そのペースがわたしには、どうしても「動いていない」ように見えてしまった。
だから、少しずつ声のトーンが変わった。
投げかける問いが増えた。
フィードバックが「気づかせよう」とするものになっていった。
そして気づけば、「寄り添っているつもり」の自分が、彼の足を押し始めていた。
Vol.2|急かしたのは、愛だったのか
Vol.2|急かしたのは愛だったのか
— 押したつもりはなくても、圧になる -
■「支える」と「推す」の境界線
わたしは彼を支えたかった。
前に進めるように、隣で歩幅を合わせながら並走していく関係を描いていた。
本人が選んだ道なら、責任を引き受けながら自分のペースで進むことこそが本質だと思っていたし、無理やり引っぱるような介入はしたくなかった。
ただ、ある時期を境に、その「支える」は少しずつ「推す」に変わっていった。
問いかけが多くなり、確認が増え、「そろそろ本腰を入れないと」というトーンが声の端々に混ざりはじめた。
本人が焦っていない分、わたしが焦る。
その焦りを「正論」や「未来の不安」に変換して、彼の前に差し出していく。
一見、コミュニケーションとしては丁寧だったかもしれない。ただ、そこにはもう、「信じて待つ」という余白はなくなっていた。
■「あなたならできる」は呪いにもなる
わたしは何度も、「あなたならできると思ってる」と伝えていた。
それは心からの言葉だったし、見せかけではなかった。ただ、それがどんなふうに届いていたのかは、わからない。
「あなたならできる」という言葉は、ときにプレッシャーとして響くことがある。
とくに、それをまだ自分で信じきれていない人にとっては。
わたしのまなざしが、いつの間にか「もうできていてほしい」という願望に変わっていたのなら、その信頼は励ましではなく、圧として伝わってしまっていたかもしれない。
■彼の“いま”を見ていない
わたしは気づかぬうちに、「これからどうするか」「このままで間に合うか」ばかりを見ていた。
つまり、彼の“いま”を、ちゃんと見なくなっていた。
「いま、どう感じているのか」
「いま、自分をどう思っているのか」
「いま、どこでつまずいているのか」
その“いま”の実感を一緒に味わうよりも、「このままでは」という未来の欠損を補うような問いを投げていた。
気づけば、彼のとなりにいるというより、少し前方に立って「こっちだよ」と示している自分がいた。
■これは、愛だったのだろうか
いま、あらためて振り返る。
わたしが焦っていたのは、彼を想ってのことだった。
ほんとうにそうだったと思う。ただ、それは「彼のために」と思いながらも、どこかで「自分が信じたものを、形にしたい」という願望でもあった。
だから、たしかにそれは愛だった。ただ同時に、それは自分の信じたい未来への執着でもあった。
愛と執着の境界線は、思った以上にあいまいだ。
信じていたからこそ急かし、期待していたからこそ詰め、願っていたからこそ、重くなった。
Vol.3|「親業を辞める」と言えたあの頃
Vol.3|「親業を辞める」と言えた
あの頃
— どんな選択も、彼らの人生だと信じられたあの瞬間 -
どんな選択も、彼らの人生だと信じられた
あの瞬間
■「もう、親でいるのはやめよう」と決めた日
何年も前、実際にわたしは親として大きな決断をした。
子どもの人生に対して、「こうした方がいい」「これは危ない」といった思いを持ちながらも、ある日を境に、もう口を出すのはやめよう、親業を辞めようと心に決めたのだ。
もちろん、親子関係そのものを手放したわけではない。
そうではなくて、「先回りして良かれと思うことを言う親」としての自分を、やめようと決めた。
それは、「わかっているつもりだった」と気づく決断でもあった。
自分の正しさよりも、彼ら自身が選んだ人生を信じること。
結果ではなく、自分で選ぶという行為そのものを尊重すること。
その覚悟は、想像していたよりもずっと落ち着いていて、ずっと深かった。
■あのときは、未来を見ようとしなかった
あのときのわたしは、先の未来を見ようとしなかった。
いま目の前にいるその人が、どんなふうに決断しているか、その瞬間の確かさを一緒に味わうことに集中していた。
選んだ先がどうなるかではなく、いま、この瞬間をどう生きているかに重心を置く。
それが、わたしなりの「信じる」という行為だった。
だからこそ、たとえその選択が「わたしから見れば絶望的」だったとしても、本人が自分なりの一手として選んでいる限り、そこに口をはさむ理由はなかった。
■なぜ今回は、あの感覚を保てなかったのか
なのに、今回──
わたしはなぜ、同じように関われなかったのだろう。
彼のことを信じていた。
でも、未来の失敗を思って先回りし、つい手を出してしまった。
なぜ、あのときできた「信じて見送る」ことが、今回は難しかったのか。
もしかすると、それは責任の重さだったのかもしれない。
一緒に創るプロジェクト、一緒に築く未来、それらに対して、わたし自身も当事者だったから。
信じることが、同時に「任せきること」になってしまうとき、それはとても怖い。
とくに、もうその道のりの困難さがわかってしまっているぶん、なおさら怖い。
■信じるには、余白がいる
いま振り返れば、あのときの「親業を辞めます」は、わたしの中に信じる余白が残っていたからできたのだと思う。
時間的にも、関係性の中にも、そして自分の心の中にも、焦りや責任に飲まれていなかったぶん、その人の人生をゆだねる感覚が持てていた。
でも今回は、その余白が持てなかった。
信じたいのに、間に合わせたい。
寄り添いたいのに、間違わせたくない。
そんな矛盾した想いが交差する中で、わたしは「信じる」という言葉を持ちながら、その本質からすこしずつ離れていってしまっていたのかもしれない。
Vol.4|信じることの、次のステージへ
Vol.4|信じることの
次のステージへ
— 手放すことと、祈ることの間で -
■代理で乗り越えることは、できない
あのとき、わたしは強く思った。
「この子たちの人生は、わたしが代理として乗り越えることはできない。」
どれほど大切に思っても、どれほど先が見えていても、彼らの人生を代わりに生きることはできない。
ならば、わたしにできることは何か──
そこに残ったのは、たった一つの答えだった。
祈ること。
どの時点を切り取っても、必ず幸せでいること。
目の前にどんな出来事が起きようとも、その人の人生がどこかで必ず祝福されていること。
わたしができるのは、それを信じて、安心したまなざしと、安心した言葉を投げかけてあげることだけだった。
■変な親面は、もうしない
だからわたしは決めた。
変な親面は、もうしない。
「ああしなさい」「こうしなさい」
善意の皮をかぶったコントロールを、やめようと決めた。
それだけで関係が、とてもよくなった。
不思議なもので、わたしが構えを下ろしたとたん、向こうも自然に心を開いてくれるようになった。
アドバイスをしなくても、頼ってくれるようになった。
手放すことで、つながりが深まる。
それは、どこか逆説的なようでいて、今となってはすごく自然なことのようにも思える。
■今回、なぜできなかったのか
だからこそ、今回の件は、苦しかった。
わたしには一度、手放す感覚を知っていた過去がある。
それなのに、今回は、どうしてもそれができなかった。
信じたいのに、間に合わせたかった。
祈りたいのに、動かしたかった。
もしかしたら、今回の関係には自分も賭けていた部分があったからかもしれない。
彼の歩みに、自分の仕事としての成果や意味を重ねてしまっていたのかもしれない。
だとしたら、それは「信じる」の中に混ざった、わたし自身の期待だった。
■信じることは、見送ることではない
今、あらためて思う。
信じるというのは、ただ見送ることではない。
祈りながら、そばにいること。
評価でもなく、助言でもなく、「あなたの歩みを尊重しています」という姿勢で関わり続けること。
そして何より、相手の切実さのタイミングすら、自分の手を離して、委ねていくということ。
それは、わたしにとって、信じることの次のステージなのかもしれない。
もう少し、待てる自分に。
もう少し、手放せる自分に。
そんなふうに変わっていけたらいいなと思う。



