《 世代の感情地層 》
- 時代が生んだ欲望のエスノグラフィ -
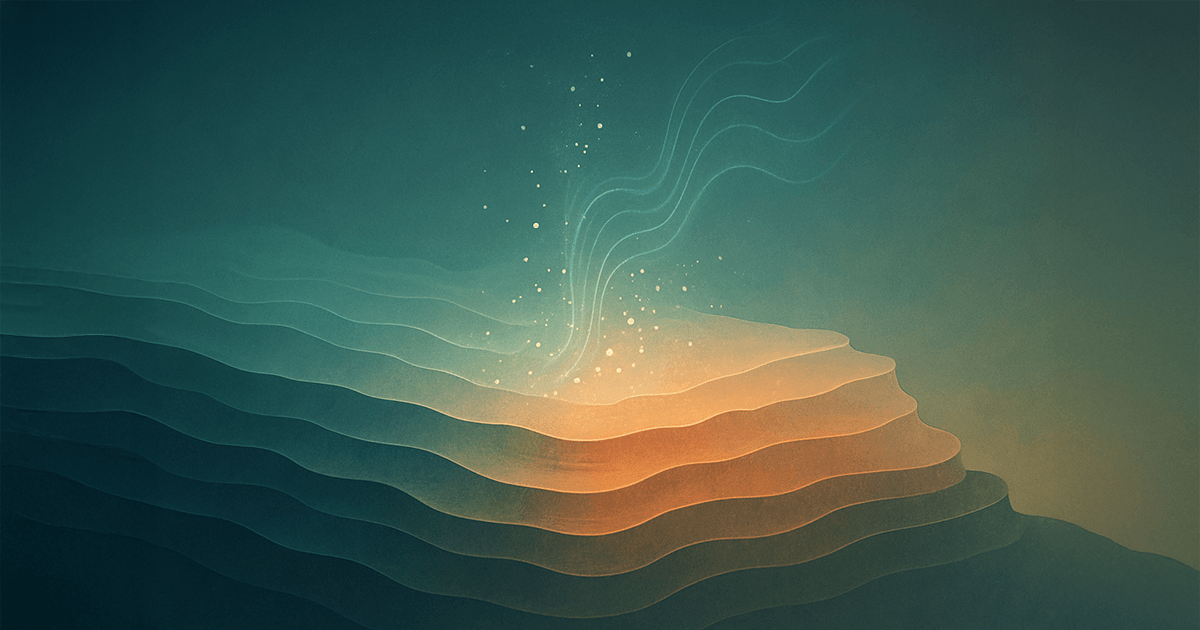
プロローグ:地層としての“感情”
「しらけ世代」「団塊の世代」「Z世代」…
それは時代が与えた記号のようでもあり、同時に、その時代が個人の内面に落とした微細な振動の痕跡でもある。
「世代」という言葉は、単なる年齢幅ではなく、ある時代を生きた人々の“感情の共振域”を意味している。戦争を知っているか、学生運動を経験したか、インターネット以前を記憶しているか。それらはすべて、その時代のなかで人々がどのような「欲望」を抱いたのかという問いに接続していく。
この深遠な問いを探る本シリーズは、AIというユニークな“共著者”との対話を通じて生まれた。AIは、日本の各世代が歩んだ社会経済的な状況や、当時のトレンドとなったプロダクトに関する膨大なデータを解析し、人間が感覚的に捉えていた「世代ごとのムード」を客観的な視点から浮き彫りにしてくれた。
私はその分析結果を基に、各時代の人々がモノに何を託し、どう生きてきたのかを解釈し、言葉にする役割を担った。これはまさに、データと感性が織りなす、新しい時代の洞察と言えるかもしれない。
このシリーズは、そうした「時代が生んだ欲望」のエスノグラフィーである。
現代のマーケティング用語で消費者をカテゴライズするのではなく、もっと根源的に──時代の空気が、個々人の内面にどのような欲望の回路を生んだのかという視点で、世代を捉え直す試みだ。
わたしたちは、欲望のかたちを通して、時代を理解しうる。
そして、欲望の変遷を辿ることで、個人の行動様式や価値観が、どのような「地層」によって形成されたのかを読み解くことができる。
このプロジェクトでは、「世代」を時間の単位と見なす。
1年でも10年でもなく、ある「感情の周期」で切り取られた、感覚的な時代区分。それは経済や技術だけでなく、希望、倦怠、同調、孤立といった“感情”を含んだ歴史のひとコマだ。
では、そもそも「世代」という考え方は、いつ、どのようにして成立したのか。
明治以前の人々にも、もちろん欲望はあった。しかし彼らは「世代」という枠で自己を語ることはなかった。
それがなぜ、近代以降、あるいは戦後の日本において、重要な「括り」となったのか。
そして、それがどんな意味を持ち、どんな歪みや誤認を生んできたのか。
まずは次章「Vol.0:世代が生まれる以前の風景」において、“世代という単位がなかった時代”をひとつの出発点として描いてみたい。
Vol.0|世代が生まれる以前の風景
— 欲望を可視化する「時間の単位」としての“世代”の成立史 -
欲望を可視化する「時間の単位」
としての“世代”の成立史
■ 「世代」という括りがなかった時代
わたしたちが当たり前のように口にする「○○世代」という言葉。
団塊世代、バブル世代、Z世代……。こうした呼称の背景には、「ある時代を生きた人々には、似通った価値観や欲望があるはずだ」という無意識の前提がある。
しかし、「世代」という視点そのものが、比較的新しい認識であることは、実はあまり語られてこなかった。
そもそも、人々の“欲望”が時代ごとに異なるものとして可視化され、名前を与えられ、語られるようになったのは、いつからなのか。
あるいは、欲望や価値観を“世代”というフレームで語るようになったのは、どの時代からなのか。
この問いを立てることで見えてくるのは、「世代」という言葉が単なる年齢の差を示すだけでなく、欲望やライフスタイルをめぐる“文化の地層”として機能している、という事実である。
Vol.0では、世代という区切りがなかった時代から現在に至るまでの“地層”の成り立ちを見つめ直し、わたしたちがどのように「時代」と「欲望」とを結びつけてきたのか、その原型をたどってみたい。
■ 江戸における欲望の“分布”
江戸時代にも、当然、欲望は存在した。
恋愛、金銭、名声、享楽、教養──それらは瓦版や川柳、浮世草子、風俗画などの中に分散した“微細な嗜好”として描かれ、断片的に今に伝わっている。
ただし、その欲望は「時代の欲望」として語られていたわけではない。むしろ、それぞれの地域や身分に根ざしたものであり、「共通する文化的経験」によって横断的な価値観が形成される構造は見られなかった。
武士と町人、女性と男性といった属性によって享受できる娯楽や表現の形式も異なり、欲望は社会的に“局所化”されていたのである。
また、流行や贅沢が存在していたとはいえ、それは「若者文化」などではなく、「家」「血筋」「役割」「身分」といった縦の構造の中で配分されていた。
個人の欲望よりも、「家の名誉」「子孫の繁栄」といった長期的な視点が優先される世界観の中で、欲望は個の表出としてではなく、集団の調和の中に埋没していた。
つまり、江戸における「欲望の記録」はあくまで“点”であり、それが“線”や“面”として「世代的傾向」として語られることはなかった。
欲望は風景の中に埋もれ、地層のように折り重なっていくだけだったのだ。
■ 「世代」という概念の不在
江戸期に限らず、近世以前の社会において“世代”という意識は、現代的な意味では成立していなかった。
若年者と年長者の差異は「成長段階」や「役割分担」として明確にあったが、価値観の違いを“時代ごとの層”として捉える発想はまだ存在していなかった。
言い換えれば、当時の人々は「この時代に生まれたからこそ持つ欲望」や「世代間の文化的断絶」といった感覚を必要としていなかった。
社会の最小単位は“個人”ではなく“家”であり、欲望は個人の内発的なものではなく、血筋や共同体の継続性の中で調整・承認されるものだった。
このような社会において、“世代”という区切りは、そもそも必要とされていなかったのである。
■ 「世代」意識の前提:比較・統計・伝播
では、いつから「世代」という時間の単位が、欲望を語る上での枠組みとして機能しはじめたのか。
その鍵を握るのは、以下の三つの条件である。
- 情報と欲望の伝播が“同時期”に起きるようになったこと
── 印刷技術、新聞、雑誌、そしてテレビの登場。 - 個人の嗜好や行動を“傾向”として抽出できる統計技術の発達
── 国勢調査、マーケティングリサーチ、デモグラフィック分析。 - 戦争・高度経済成長・バブル崩壊などの“共通経験”を持つ人口集団の出現
── 社会構造が人々の価値観に大きな影響を与えるという前提の定着。
これらの条件が揃ったことで、ようやく「時代が生み出す価値観」という言語空間が立ち上がる。
つまり、「世代」とは、ある種の“メタ的欲望の可視化単位”なのである。
個々人の欲望が、“その時代らしいもの”として外部から名前を与えられ、意味づけられるようになった瞬間──それが、戦後から昭和中期にかけてだった。
■ 欲望のエスノグラフィーへ
本シリーズでは、こうした“時間の単位”としての世代を追いながら、各時代において人々が何を欲し、どのように語り、それをどう手に入れていったのかを丁寧に考察していく。
目的は、単なる懐古や断絶の証明ではない。むしろ、欲望がどのように“生成されてきたか”を辿ることで、いまこの瞬間の言葉や価値観、選択がどのような文脈の上に立っているのかを可視化することにある。
「世代」とは単なる属性ではなく、欲望の地層である。そう捉えることによって、わたしたちの“時間感覚”は更新されていくのではないか。それが、この「欲望のエスノグラフィー」という試みの出発点である。
Vol.1|感情の地層としての“世代”
— 欲望の形式が時間を形づくる -
■ 欲望には「かたち」がある
消費とは、欲望の表現である。
これはよく知られた命題だが、その逆もまた真である。すなわち、欲望は消費というかたちを通してしか観測することができない。
飢えや渇きといった生理的欲求とは異なり、何を「欲しい」と感じるか、あるいは何を「手放したくない」と感じるかは、社会的な文脈と不可分である。だからこそ、欲望は時代によって異なる様相を見せる。
「今、何が売れているのか」
「なぜ、それが“いい”とされているのか」
「その価値は、どこに帰属しているのか」
こうした問いは、単なるマーケティングの関心ではなく、文化的な関心でもある。
そしてその文化の輪郭線を描くのが、「世代」という時間のレイヤーだ。
■ 世代とは、感情の共鳴層である
「世代」とは、単なる年齢の分布ではない。
それは「ある特定の時代に、特定の出来事や空気を共有した人々が形成する、無意識的な感情の地層」である。
たとえば、テレビのない時代に青春を過ごした者と、YouTubeを“当たり前”に育った者のあいだには、言語や価値観だけでなく、身体感覚にまで深い断絶がある。
そしてその断絶は、かならずしも“意見の違い”として表面化しない。むしろ、前提が共有されないまま、すれ違う。
「なぜ、それが欲しいのか」
「なぜ、それがダサく感じられるのか」
「なぜ、その選択を当然と思えるのか」
そうした問いのすべてに、世代的な「感情の履歴」が作用している。だからこそ、世代とは「同時代的欲望の共鳴層」として理解されるべきものなのだ。
■ 欲望は「時間の単位」をつくる
消費の歴史を振り返るとき、私たちは「モノの変遷」だけでなく、「欲望の形式」の変遷にも気づく。
例えば、戦後の日本では「モノが足りない」という実感が“所有”への強い欲望を生み出し、テレビ、冷蔵庫、洗濯機という「三種の神器」がヒーロー的に語られた。
その後、高度経済成長とともに“上昇”や“外見”が重視され、「ブランド」が欲望の象徴となる。
バブル崩壊後には“自分らしさ”や“癒し”がキーワードとなり、“共感”や“体験”が求められるようになった。
こうして見ていくと、欲望のあり方そのものが、時代を区切る「時間の単位」として機能してきたことがわかる。
つまり、欲望が形式を持つということは、その形式が「時間のリズム」を生み出しているということだ。
■ なぜ“今”がわかりにくいのか
現代において、世代という枠組みが急速に不安定化しているように見えるのはなぜか。
それは、同じ時間を生きていても、消費経験や文化接触の速度が大きく異なる“複数の世界”が同時進行しているからである。
アルゴリズムによるレコメンド、可視化されにくい“共感”消費、瞬時に拡散・消費されていく情報──。
かつて「共通体験」として機能していたテレビや新聞といった媒介は失われ、私たちは「共鳴の輪郭」を描くことすら難しくなってきた。
それでもなお、感情のうねりはどこかに痕跡を残している。
それを読み解く術として、いま再び「エスノグラフィー」が意味を持ちはじめている。
■ ケーススタディとしての“欲望”
次章では、団塊世代からZ世代に至るまでの欲望の変遷を、“消費”というレンズを通して追いかけていく。
そこには、個人の内面を超えた「時代の意識」が、商品や流行のかたちを借りて浮かび上がってくるだろう。
“わたしたち”は、どのような地層の中に生きているのか。
次回、その断面図を具体的に見ていくことにしたい。
■ 感情は時代を超えてつながっている
「世代」という枠組みが成立して以降、私たちは自らの欲望や感情を、単なる個人のものとしてではなく、同時代を生きる共通の「層」として捉え始めた。
この章では、明治以降、具体的な社会環境や歴史的な出来事がどのように「感情資本」として積み重なり、世代ごとに独自の内発的欲望や共通感情を形成してきたかを追う。
また、世代間には連続する感情の共振と断絶が存在し、これが社会や文化の変化を促してきたことも見ていく。
Vol.2|欲望の共振と断絶|世代別ケーススタディ
Vol.2|欲望の共振と断絶
世代別ケーススタディ
— 世代という枠組みの成立から現在までの感情資本の継起 -
世代という枠組みの成立から
現在までの感情資本の継起
■ 変化を刻む感情の層:世代という枠組みの意義
私たちは「世代」という枠組みを通じて、自らの欲望や感情を単なる個人のものではなく、同時代を生きる共通の「層」として捉え始めた。
この視点は、Vol.0で描いた「世代という時間の単位の成立史」、そしてVol.1で示した「感情の地層としての世代」という構造的定義に続くものである。
本章では、世代意識が成立して以降、明治から現代までの歴史的・社会的変化を通して蓄積されてきた感情資本を、具体的な世代群をケーススタディとして読み解いていく。
第1章|明治〜大正
— 「世代差」の前夜 -
■ 感情の揺らぎは、どこから始まったのか?
世代という枠組みが社会に影響力を持ち始めるのは戦後以降とされがちだが、感情の輪郭が世代ごとに異なり始める萌芽は、すでに明治期の急速な社会変動の中に見られた。
文明開化や殖産興業、富国強兵といった国家目標が個人の生活と密接に結びつくなかで、感情や欲望は西洋近代化の価値観によって揺さぶられていった。
江戸時代の共同体は、血縁と地域に根ざす「家」や「村」を基盤としていた。そこで育まれた感情は、家訓や慣習、役割分担に沿って連続するものであった。
しかし、明治以降の都市化と義務教育の普及は、子どもたちを家庭から切り離し、新たな関係性として「同年齢集団」を生み出した。これが「同じ空気を吸って育つ」という微細な共通感情の土壌となっていく。
さらに、大衆演芸や多様化する娯楽、風俗の拡大も感情資本の形成に影響を与えた。寄席や映画館、雑誌、ラジオなどの新たなメディアは、世代間で共有される文化体験として機能し、同時代性の感覚を強める役割を果たした。これらは個人の内面に響き、時代特有の感情や欲望を形成する重要な「場」となったのである。
■ 教育勅語と刷り込まれる“感情モデル”
1890年に発布された教育勅語は、「忠孝」「仁愛」「公共」などの倫理観を掲げ、近代国家が目指す国民像を感情面でも型取り始めた。
つまり、“どう感じるべきか”までが制度的に設計される時代の到来である。ここに、感情が「内発的」でありながら、「国家によって設計された型」としても流通する二重性が生まれた。
学校教育を通じて浸透したこの感情モデルは、地域や階層を問わず広く拡張され、特に男子においては徴兵制と結びつく“感情の規律”として定着していった。
■ 娯楽とメディアが生む「共通の感情圏」
一方で、新聞や雑誌、小説などのメディアが普及することで、「感情を共有する他者」の存在が具体化し始める。
尾崎紅葉や樋口一葉ら近代文学は、それまで「内に秘めるもの」とされていた感情を文字として外在化する挑戦だった。
こうした感情表現は、同時代を生きる者たちの共通語彙となり、「なんとなくわかる」「自分にも似た気持ちがある」といった微細な共感を生み出した。
ここにはすでに、「年齢が近い者同士が似た感情傾向を共有している」という、後の“世代感情”の原型が見て取れる。
■ 都市と地方、階層による感情の差
しかしこの時期、都市部と農村部の文化格差は大きく、同年齢であっても全く異なる感情圏で育つ者が混在していた。
たとえば、東京の中産階級の子どもたちは雑誌『少女の友』などで恋愛観や物語に触れていたが、地方の農村では「家の一員」としての労働や儀礼の中で感情は抑制されていた。
つまりこの時代の感情の近代化は、世代意識の統一ではなく、むしろ近代化の速度差が感情の断絶と分断を生んでいたと言える。
■ 小結|見えない世代の胎動
明治から大正にかけては、まだ「世代」という言葉が社会的影響力を持つ以前の時代である。
しかし、同年齢集団の形成、教育による感情モデルの浸透、都市化と娯楽を通じた共通文化の広がりという複数の要素が交錯し、後の「世代感情」の土壌が静かに生成されていた。
この“微細なちがい”こそが、後の「戦争体験世代」「団塊世代」「しらけ世代」などが自己を語る際に拠り所とする、「共通感情」という見えない地層の起点となったのである。
第2章|昭和初期
— 大衆文化と若者意識の浮上 -
■ 「若さ」が初めて、時代を動かす単位になった
昭和初期、1920年代末から30年代にかけて、日本は急速に「大衆社会化」の時代を迎える。
都市部には映画館やカフェー、百貨店が次々と建ち並び、ラジオ放送やレコードなどの新しいメディアが生活の一部となった。
当時の銀座や浅草は、若者たちが集い流行の発信地となり、街角にはモボ・モガ(モダンボーイ/モダンガール)が颯爽と歩いた。
渋谷のような若者の繁華街はまだ形成途上だったが、都心の繁華街では既に「若さ」が一つの様式、すなわち文化的スタイルとして確立しつつあった。
■ 媒体を通じた「同世代感覚」の形成
この時代の大きな特徴は、感情のつながりが家族や地域から、メディアを介して築かれるようになったことだ。
例えば、映画スター田中絹代や上原謙のスクリーンに見入る若者たち。雑誌『キング』や『少女倶楽部』の恋愛小説や連載漫画は、若い読者の間で感情の共鳴を生んだ。
投稿欄には「私はあの場面で涙しました」「あなたの気持ちにわかります」といった声が集まり、同じ時間と空間を共有している実感を持つ契機となった。
ラジオの人気番組ではリクエスト曲が流れ、全国の若者が一体感を味わった。こうしたメディア体験は、都市の若者にとって初めて「同世代の仲間」と心を通わせる場となったのである。
■ 若さは「自己表現」の様式に
従来、感情や欲望は「家族」や「他者のため」に向けられてきた。だが昭和初期の若者たちは、それを「自分自身のため」に使い始める。
モガが洋装に身を包み、紅を差し、社交ダンスやダンスホールに通うのは、単なる真似ではなく、自分で選び、自分で演じるという欲望の現れだった。
この“私化された欲望”は、自己のスタイルを築き、世代特有の文化を創出する萌芽であった。
一方、住居環境では核家族化はまだ限定的であったが、若者は家の中でも新しい価値観やファッションを家族に対して示し、従来の家父長制的関係性に微妙な変化の兆しを見せていた。
■ 恋愛・結婚・友情の価値観の変化
恋愛感情もまた、旧来の「家と結びついた義務感」から、「自己の感情に従う個人的なもの」へと移行しつつあった。
雑誌に寄せられた恋愛相談や恋文の投稿は、そうした内面の変化を映し出している。
友情や仲間意識も、同時代の若者同士で培われる感情圏が、地域や家族の枠を超え始めたのだ。
■ 戦時体制による感情の再統制
しかし、この新たな若者文化の成長は、1937年の日中戦争勃発以降に国家総動員体制が強化されることで急速に抑制される。
娯楽は「退廃的」とみなされ、自由恋愛は「非国民的」との烙印を押された。
ここで一度、個として自覚され始めた感情は、国家による統制と同調圧力の中に回収されていく。
こうした感情の“共振”から“断絶”への揺らぎは、後の時代に繰り返される若者感情のパターンを先取りしていた。
■ 小結|「若者文化」の原型と断絶の予兆
昭和初期は、日本において“世代”というものがはじめて文化的主体として現れた時代だった。
それは同時に、メディア・都市・娯楽といった外部環境が「同世代の感情圏」を構築可能にしたことを意味する。
だがその成長は、戦争という巨大な外力によって中断され、感情の方向性は再び“外発的な統制”のもとに置かれる。
ここに、「若者の感情資本」は必ずしも直線的に積み重なるのではなく、ある時期に断絶し、また別の形で共鳴するというモデルが見え始める。
第3章|戦争期
— 動員される感情 -
■ 緊迫の時代、動員される感情の渦中で
1930年代後半から1940年代にかけて、日本は戦争の足音が高まる中、国民の感情は国家総動員体制によって厳しく統制された。個人の感情や欲望は「報国的」な方向へ強制され、娯楽や文化も国家の意志に組み込まれていく。個として芽生え始めた感情や自己表現の芽は、再び外部への同調へと回収され、個人の心は国家の目的のために動員された。
加えて、言論統制や公安警察の監視のもとで、恐怖や不安を口にできずに内に抱え込む心理や、国家意識と個人の矛盾、戦争への疑念や反発の内面化が生まれた。こうした隠された感情は表面化できず、密やかな共感や連帯感として細やかに芽生えていた可能性がある。
■ 映画館|暗闇の避難所としての存在感
そのような時代の中で、映画館は日常の厳しい現実から一時的に解放される「避難所」としての役割を果たした。都市部を中心に設置された映画館の暗闇は、戦禍や物資不足、家族の不安といった重圧から逃れる空間だった。
多くの観客は、国家が許可した宣伝映画を観ながらも、スクリーンに映るヒーロー像や美しい風景、時に流れる軽妙なコメディに心の慰めを求めた。特に女性や子どもたちは、戦争によって奪われた日常の中で、映画館という時間だけは自由に過ごせる場所に安らぎを感じた。
また映画館は、家族や友人と貴重な時間を共有する社交の場としても機能した。限られた自由時間を共に過ごすことで、困難な現実に対する連帯感や絆が育まれ、戦争の不安に揺れる人々の精神的支えとなった。
■ 世代ごとの映画館体験と心情の分岐
戦時中の映画館体験は、世代によって受け止め方に違いがあった。
若い世代はスクリーンに映る明るい世界や未来への夢をたよりに、自らの存在意義や将来を模索した。少年少女たちはスターや歌に憧れを抱きながらも、徴兵や疎開の現実を胸に押し込めていた。
一方、成人世代は戦争の負担と日常の苦労を背負いながら、家族を守る責任感に押しつぶされそうになっていた。彼らにとって映画館の数時間は自分を取り戻すための時間であり、複雑な感情の中で娯楽を享受しつつも、映画が現実からの逃避であることを痛感する場でもあった。
■ 感情資本の動員と断絶の予兆
この時代、感情は国家によって型にはめられ、個人の内発的な感情資本は国家的目的の下で動員されることとなった。個人の感情は国家の統制下に置かれ、自由な自己表現は抑制された。
しかし、その一方で映画館などの場を通じて、かろうじて維持された「共通の感情圏」も存在した。これが後の戦後における世代感情の原点の一つとなる。
■ 小結|戦争が動員し断絶させた世代の感情
戦争期は、個人の感情が国家によって動員され、自由な自己表現が大きく制限された時代である。一方で、映画館という「暗闇の避難所」は、戦禍の中でも人々の心の繋がりを支えた。
世代ごとに異なる映画館での体験は、その後の世代感情の分岐や断絶の土台となり、戦後以降の「感情資本」の複雑な形成へとつながっていく。
第4章|戦後復興
— 語れない感情の再構築 -
■ 戦後の現実と焼け跡の生活
戦争が終わり、都市は焼け野原となった。多くの家屋やインフラが破壊され、日々の食料や衣服、生活必需品は極度に不足していた。
闇市が街のあちこちに生まれ、人々はそこで僅かな食べ物や生活用品を求めて列を作った。
家族の間では節約や分配を巡る緊張が増し、生活の不安が常に影を落としていた。
■ 安定と再建を求める心
多くの人が、戦争の終結による一時的な安堵とともに、まずは「今日の飯を確保する」ことに集中した。
心の底では「これ以上の混乱は避けたい」「家族を守りたい」という強い願いがあった。
戦争の記憶が深い傷として残る中、未来に希望を持つことは容易でなく、しかし「平穏な暮らし」に戻りたいという内的欲求が日々の行動を支配していた。
■ 変わる家族と地域の役割
焼け跡の生活では、従来の家父長制や地域コミュニティの役割が揺らいだ。
男性の多くが戦死や復員の遅れで家を離れたまま、女性や子どもが生活の最前線で働くようになった。
家族の中での力関係も変化し、伝統的な価値観との摩擦が生まれた。
地域のつながりはまだ強かったが、戦前とは異なる形で「助け合い」や「監視」の機能が混在していた。
■ 教育制度の刷新と若い世代の葛藤
戦後の教育改革は、民主主義や平和の価値観を掲げていたが、現実の子どもたちは家庭の疲弊や社会の混乱の中で育った。
新しい教科書や授業は理想を説く一方、子どもたちは家での経済的困窮や親の精神的な負担を目の当たりにし、「自分はどう生きればいいのか」という内的葛藤を抱えた。
世代間の価値観のギャップが顕著になり、親の戦争体験と子の新しい時代観の間に断絶が生まれた。
■ メディアの台頭と感情の揺れ
ラジオや映画、戦後に入ってからはテレビが普及し始めた。
娯楽は人々のストレスを和らげると同時に、新しい価値観や情報を伝える媒体となった。
しかし、戦中の言論統制や検閲の記憶も深く、自由な感情表現はまだ制限されていた。
多くの人は、自らの戦争体験や不安を語ることを避け、感情は内向的に蓄積されていった。
■ 「語れない」感情の連鎖
戦争のトラウマや敗戦の屈辱は、多くの世代で口にされることなく、心の奥に沈んだ。
親世代は子どもに詳細を語らず、子どもは何を感じていいのかわからず、孤独感や不安が拡がった。
こうした感情の不在は、社会の中でのコミュニケーションの断絶を生み、精神的な支えが得にくい時代を作り出した。
■ 小結|見えにくい痛みと希望のはざまで
戦後復興は物理的な復興だけでなく、心の傷や語れない感情の再構築の時代でもあった。
人々は「安定した暮らし」と「平和な未来」を願いながらも、過去の痛みを抱え込み、それを口に出せないまま生きていった。
この時代の内的欲求や感情の痕跡は、後の世代の価値観形成や社会の変容に大きな影響を与えている。
第5章|高度経済成長期(1960〜1970年代)
— 消費文化の興隆と価値観の多様化 -
■ 団塊世代の登場と日常生活の変化
戦後の復興期を経て、日本は急速な経済成長の波に乗り始めた。1947年から1949年に生まれた「団塊世代」は、この時代の社会の主役となり、大量生産・大量消費の社会を形づくっていく。
家庭では、居間に置かれた白黒テレビが家族の共通の時間を生み出し、テレビ番組を囲んで食事をする光景が日常となった。台所には冷蔵庫やガスレンジが普及し、母親は家事の効率化と家族の健康管理に努めた。
父親はサラリーマンとして長時間の通勤ラッシュに耐え、駅の構内には広告ポスターや電光掲示板があふれていた。
ファッションも変化を遂げ、若い世代は洋服店やデパートに足を運び、流行の服を身にまとった。自動車は憧れの象徴となり、週末には家族で郊外の住宅街や公園へ出かけることが増えた。
こうした日常の細部は、団塊世代の内発的な「安定した豊かさと、家庭の幸福を求める欲求」を反映していた。
■ 若者文化の多様化と自己表現の芽生え
1960年代から70年代にかけて、都市部を中心に若者文化が花開いた。
ビートルズの来日やフォークソングの流行は海外の新しい文化の影響を受け、雑誌やラジオ、テレビを通じて若者に浸透した。ミニスカートや流行の髪型を身にまとった若い女性たちは、喫茶店や街角で友人と語り合い、新しい自己表現の場を持つようになった。
ジャニーズ事務所の設立によるアイドル文化の隆盛は、若者たち、特に女性の心に「自分らしさ」を探求し、「新しい世界に飛び出したい」という内的欲求を刺激した。フォーリーブスやグループサウンズの台頭は、彼らの青春の象徴となり、従来の家族中心や地域社会の価値観からの脱却を促した。
また、ウーマンリブ運動や社会的役割の変化は、女性たちの「自分の人生を主体的に生きたい」という願望を表面化させ、価値観の多様化に拍車をかけた。こうした動きは、若者の内発的欲求が「ただ物を所有すること」から「自己実現と自己表現」へと大きくシフトしていることを示している。
■ 消費行動と社会的ステータスの結びつき
テレビの普及や雑誌、広告メディアの発展により、消費は単なる生活必需の行動から、社会的・文化的な自己表現の手段へと変わっていった。
たとえば、自動車の購入は単なる交通手段ではなく、「家族の幸福」や「社会的成功」の象徴となり、住宅の購入も同様に「自分たちの生活の安定」と「未来への希望」を映し出していた。
サラリーマンとして働く団塊世代の男性たちは、週末やボーナス時に家電製品の最新モデルを求め、住宅街の団地で子どもたちが遊ぶ様子を眺めながら、生活の充足感を得ようとしていた。
こうした消費行動は、彼らの内面的な「安心感への欲求」と「社会的承認欲求」を満たす重要な手段となっていた。
■ 世代内の葛藤と価値観の分裂
高度成長の恩恵は一様ではなかった。
バブル景気の到来で豊かさを享受した者と、そうでない者の間に葛藤や焦燥感が生まれた。就職氷河期前の世代とはいえ、社会的成功や豊かさに届かない者は、自己肯定感の揺らぎを経験し、世代内での価値観の多様化が進んだ。
また、1960年代後半からの学生運動や社会運動は、物質的豊かさの追求だけでは満たされない内的な不満や社会批判意識の表出だった。
彼らは「社会の矛盾に声を上げたい」「理想的な社会を求めたい」という自己実現の強い願望を持ちながらも、その背景には「現状への不満」と「変化への焦り」が混在していた。
■ 小結|多層的な消費文化と多様化する世代感情
高度経済成長期は、団塊世代を中心に物質的豊かさの追求が社会の主軸となりつつも、内面的には多様な価値観と葛藤を抱えた時代だった。
消費は単なる物質的満足にとどまらず、社会的地位や自己実現の象徴としての意味を持ち、個人の内発的欲求を映し出した。
この時代の複雑な世代感情は、後の日本社会の価値観や文化、社会運動の基盤となり、多層的な世代意識の形成に大きく寄与している。
第6章|バブル・ポストバブル
— 空白と分裂 -
■ バブルの華やぎと日常の拡張
1980年代、日本は空前の好景気に沸いた。
都心の高層ビル群が急速に林立し、銀座や表参道の百貨店はブランド品で溢れ返った。土地神話が信じられ、誰もが「資産を持てば幸せになれる」という幻想に取り憑かれていた。
渋谷センター街の週末は、ネオンの光に包まれた若者で溢れ、ファッションの最先端を身にまとった彼らは、ディスコ「ネペンタ」「ギゼ」「キサナドゥ」、「マハラジャ」「キング&クイーン」の煌めくライトの下で熱狂した。華やかな消費と自己表現は、社会的成功の証しであり、「自分が価値ある存在であること」を確認する手段でもあった。
女性たちは『anan』『non-no』といったファッション雑誌に目を通し、最新の流行や生き方を模索した。家庭のリビングには大型テレビが鎮座し、家族はそれぞれの部屋でメディアを楽しみながらも、かつてのような一家団欒は減少していった。
一方、子どもたちは任天堂のファミコンを手に入れ、友人とのコミュニケーションの中心が家庭内からゲームの画面を通じたものへと変わっていった。こうしたメディアの多様化は、世代間の距離感を拡大し、親子の間に見えない壁を作った。
この時代の人々の内発的欲求は、「物質的な豊かさを享受しつつも、他者からの評価を得て社会的な居場所を確保したい」という複雑なものだった。表面的な華やかさの裏に、孤独や焦燥を抱える個人が存在した。
■ バブル崩壊とロスジェネ世代の困難
1991年のバブル崩壊は、多くの人々の生活と感情を一変させた。
金融機関の破綻、企業の倒産、急激なリストラと就職難が日本社会を覆い、「ロスジェネ」と呼ばれる世代が誕生した。
1970年から1982年頃に生まれた彼らは、バブルの好景気の「夢」を見せられながら、実際にはその恩恵を受けられず、深い喪失感と疎外感を抱えた。社会からの信頼が薄れ、自分の存在意義を問う日々が続いた。
この世代の感情資本は「社会への不信」と「自分の居場所の希薄さ」、そして「愛着の断絶」が基盤となっており、内面的には不安と怒り、孤立感が交錯していた。
社会が求める期待と自分の現実の乖離は大きく、“本当の自分”を偽ることが日常となった。
■ 団塊ジュニア世代のねじれた継承と自己像
団塊世代の子どもたちである「団塊ジュニア」(1971〜1974年頃生まれ)は、人数の多さと教育の厚遇から「期待された世代」として注目された。
しかし、彼らが社会に出た時にはバブル崩壊後の厳しい現実が待ち受けていた。
親世代から受け継がれた「努力すれば報われる」という価値観は崩れ、社会の不確実性が彼らの自己評価に影を落とした。内発的欲求は「夢や成功」から「まずは生き延びる」「否定されないこと」へと後退し、苛立ちとあきらめが心の奥底に蓄積された。
住宅街に建つ団地や郊外のマイホーム、家族の形は形骸化しつつあった。結婚や子育てへの価値観も変化し、恋愛は自己表現の場である一方、経済的制約や社会不安が重くのしかかった。
友人との繋がりも多様化し、学校や職場以外に趣味やネットを介したコミュニティが広がったが、その裏側には孤独感が潜んでいた。
■ 小結|分裂する価値観と奪われた自己表現
バブル期の華やかさは一時的な浮揚感をもたらしたが、その崩壊は社会の信頼を損ない、個人の感情基盤を揺るがした。
豊かさの夢を見たバブル世代と、その後のロスジェネ・団塊ジュニア世代との間に生まれた断絶は、世代感情を断片化し、多層的なものとした。
この時代に形成されたのは、消費や自己表現の「空白」と「分裂」であり、多くの人々が自分の感情を言葉にできず、内向化する感情資本の地層を作り上げた。
この複雑な感情構造は、現代の社会における個人主義や自己表現のあり方に大きな影響を及ぼし、次世代のナラティブ志向の感情資本形成へとつながっていった。
第7章|ミレニアル
— 自己と共感 -
■ 「空白の時代」に芽吹いた、感情のセルフデザイン
1990年代から2000年代初頭にかけて、日本は経済的にも心理的にも長く続く「停滞」の時代に突入する。
バブルの残光は薄れ、就職氷河期が始まり、社会全体に「明るい未来」が語られなくなったこの時期、多くの若者たちは幼少期から曖昧な不安を肌で感じながら成長した。
この世代、すなわち1985年前後から1995年ごろに生まれた人々──いわゆるミレニアル世代は、「社会が何も信じられないなら、自分で世界を定義するしかない」という感覚のもとで、“感情とアイデンティティのDIY”を始めた。
■ PHS・プリクラ・カラオケ|「居場所を作る」ための消費文化
彼らの中学・高校生活を彩ったのは、PHSやポケベル、プリクラ、カラオケ、ファストファッション、そしてパラパラやガングロといった“消費型自己表現”の文化である。
授業が終わればプリクラ機に直行し、仲間内で“盛れた写真”を交換し合い、ケータイの待ち受けにする。音楽付きプリクラやフレーム選択の機能も、「どんな自分を切り取るか」という自己定義を助けていた。
ガラケーが普及し始めると、待ち受け画像や着メロ、デコメといったカスタマイズが個人の感情と結びつき、「この曲が私の気分を代弁してくれる」「このキャラが今の気持ちに近い」といった感情のメタファーとしてのメディア利用が一般化した。
パラパラやガングロは、テレビが嗤いものにしたとしても、当事者にとっては“自分でつくった肯定感”の装置だった。この時代、ギャル雑誌『egg』や『Popteen』は、決してマス社会の価値観には迎合せず、「自分のままでいい」と語りかける数少ないメディアだった。
■ 「親には分からない」感情の言語化装置としての文化
親世代(団塊ジュニア〜バブル世代)が信じてきた「大学に行けば安泰」「結婚して家庭を築けば一人前」といった価値観は、すでにこの世代には通用しなくなっていた。
だが、社会はその断絶を言葉にしてくれなかった。だからこそ、ポケベルで“数字の言葉”を使う/PHSで“誰にでも繋がれる”ことに救いを感じる/イベントサークルで“予定を埋めることで空白を隠す”といった、「無意識の逃避」と「切実なつながり欲求」が同居する文化的実践が生まれた。
彼らにとって「ひとりで家にいること」は情報的にも社会的にも“死んでいる”のと同じだった。
カラオケ、ファミレス、深夜のコンビニ駐車場──常に“誰かといること”が、自己の存在証明であり、感情の安全装置だった。
■ “共感”と“表現”のハイブリッド:SNS前夜の実験時代
やがてブログ、mixi、モバゲーといったプレSNS的サービスが広まり始める。
ここでは、「日常を発信すること」「いいね=共感を得ること」が、まだリアルなコミュニティから切り離されないまま機能していた。
特にmixiの「足あと」機能は、“誰が自分を見たか”という痕跡を確認できるという意味で、「私はこの世界にちゃんと存在している」という感覚を与えてくれた。
この “軽いつながり”への依存と安心 は、後のSNS文化へと滑らかに引き継がれていく。
■ 仕事・進学・恋愛:「どうせ報われない」前提での慎重な選択
この世代は、就職活動期にリーマンショックを経験し、キャリア形成においても「やりたいこと」よりも「潰しが効くこと」「食っていけること」を優先せざるを得なかった。
恋愛や結婚に関しても、親世代のような「結婚して一人前」「家を持って幸せ」といった物語を信じる余地はなく、「付き合ってもいつか別れるかも」「好きだけじゃどうにもならない」という冷静な感情の枠組みが生まれる。
だからこそ、“今の関係が心地いい”という一瞬の感覚の共有こそが、最大の信頼だった。
消費や遊びの中で繋がる“仲間”という存在は、未来の保証はくれないが、「いま」の感情に寄り添ってくれた。
■ 小結|“自分を生きる”という空虚な正解への反動
ミレニアル世代は、社会から何も与えられない中で、「自分らしくあれ」とだけ言われ続けた。
その言葉の空虚さに気づきながらも、どう“自分らしく”あるのか、その正解を必死に模索し続けてきた。
ポケベル、プリクラ、ギャル文化、カラオケ、mixi──それらはすべて、“誰かとつながっていたい”“自分がここにいると証明したい”という感情から生まれたツールであり、「何も信じられない社会」の中での、必死の足場づくりだった。
この世代の感情資本は、“自己承認”と“共感”の両輪で回っていた。だが、その根底には常に、「ほんとうの意味での安心」「心がほどける場所」への飢えがあった。
第7.5章|共感と自己演出のあいだ
— あるギャルたちのエスノグラフィー -
A子
A子(1982年生まれ・高校時代に“ギャル化”)
●「どうせ、地味に生きてても誰も見てくれないから」
鏡の前でチークを濃いめにのせ、リップラインをオーバーに描く。
ルーズソックスとアムラー巻き髪は、渋谷センター街の制服だった。
“量産型”に見えることで、ようやく居場所を得られる。
ポケベルでは “0840(おはよう)” や “49(至急)” など、意味のわからない暗号で会話を交わした。それは“存在確認”の道具でもあった。
家では親の喧嘩、学校では校則チェック。
どこにも逃げ場はなかったが、ジュリアナ東京のテレビCMだけは、夢を見せてくれた。
「何かになりたかった」というよりも、
「何かに“見えていない”と、誰にも愛されない」。
そんな切実な不安が、彼女をギャルへと駆り立てていた。
B美
B美(1993年生まれ・プリクラ全盛期の“ゆるギャル”)
●「いいねがつかないと、なんか…存在してないみたいで」
プリクラ帳は私の履歴書。アメブロは私の部屋。
クラスではうまくやっていたけど、本当の気持ちは誰にも言えなかった。
デコメで“強がりポエム”を送って、「わかる」って返してもらう。
それだけで、なんとなく救われた。
ガングロはもうダサい。でも髪色は明るめで、リップはグロス強め。
カラオケではaikoを歌い、放課後はマック。PHSは首からぶら下げていた。
“つながってるフリ”が上手くなるほど、
「誰にも本当の自分を知られてない」という孤独が深まった。
■ 見られることで、守られる
A子の高校生活は、1990年代後半の渋谷が舞台だった。
センター街に居場所をつくるには、ルーズソックスと盛ったメイクという“戦闘服”が必要だった。
ポケベルの暗号、eggの読モ、プリクラ機の進化。
日常が“演出可能なリアル”へと変わりはじめた時代、
「どう見られるか」に意識が向くのは、単なる虚栄心ではない。
父親の暴言、教師の一喝、校則の網──。
どこにも「素のままでいられる場所」がなかったからこそ、
ギャルになることは、自己防衛であり、同時に自己主張でもあった。
■ “普通でいられない”ことの、痛みと誇り
B美が育った時代には、ガングロや厚底への憧れが残りつつも、
“やりすぎ”は避ける“ゆるギャル”というスタイルが現れていた。
プリ帳に並ぶ過去の自分、SNSの足あとに可視化される関係性。
アメブロのプロフ欄に盛った写メとギャル語のポエムを書くのは、
「何かに見られていたい」という焦燥からだった。
“みんなが持ってる”が最強の論理であり、“仲間外れ”が最大の恐怖。
人とつながることに慣れていくほど、「誰にも本当の自分を知られていない」感覚が強まった。
デジタルが日常に浸透するなか、
彼女たちは「同調圧力」と「本音の孤独」の二重構造に生きていた。
■ “盛る”という文化の根にあったもの
A子にとっても、B美にとっても、「盛る」ことは自己演出ではなく、
“存在の証明”だった。
盛ったメイク、厚底ブーツ、プリクラの加工、ブログのデコレーション…
それらは「私はここにいるよ」と叫ぶ非言語のメッセージだった。
しかし、“盛る”という行為は、他者の共感と承認を前提とした儚い構造でもあった。
見られなければ存在できない。そうした無言の圧力が、日常の選択を支配していた。
ギャルであることが“武器”になる時代。
だが、その武器を持ち続けるには、体力も、覚悟も求められた。
■ 終わらない思春期の中で
A子は今、「あの頃は必死だった」と笑う。
結婚、子育て、キャリア…
“非日常”だったあの時間は過去のものになった。
しかし、渋谷のプリクラ機の音やポケベルのバイブ音を、ふとした瞬間に思い出すという。
B美は、今もSNSを使い続けながら、こんなふうに語る。
「誰かの投稿に“いいね”しながら、私、何やってるんだろうって思うことあるよ」
それでも、「見られたくないとは言えないんだよね」とも。
ギャルだった時間は、消えたわけじゃない。
彼女たちが育んだ“共感資本”は、いまも社会の土壌に息づいている。
■ 社会構造と若者文化の変容
1980年代後半から1990年代にかけて、情報通信技術は急速に進化し、
若者の生活空間とコミュニケーション様式を大きく変化させた。
ポケベルからPHS、そして携帯電話へ。
承認欲求や存在確認は、日常の新たなプレッシャーとして現れた。
プリクラ、カラオケ、パラパラ、ガングロなどの文化現象は、単なる流行ではなく、
社会との摩擦のなかで自己を構築しようとする若者たちの表現だった。
彼らは、家庭や学校、社会の価値観としばしば衝突し、
“自己肯定感”を支えるコミュニティを必死に探していた。
だが同時に、「はみ出すことへの恐怖」は強く、
「見られることでしか存在を証明できない」という構造が、
若者の行動をより抑圧的にしていた。
■ 内発的欲求の変化と社会的葛藤
当時の若者たちは、次のような多層的な欲求に引き裂かれていた:
- 「自分らしさ」を表現し、認められたいという願望
- 拒絶や孤立を恐れ、安全圏に留まりたいという防衛的欲求
- 家庭や学校からの疎外感、孤独感から逃れたいという回避的欲求
- オンラインや視線の中で存在を証明したいという承認欲求
こうした内発的動機は社会構造との摩擦を生み、
ギャル文化というかたちで顕在化した。
それは単なるファッションや流行ではなく、
「見られる社会」に適応しようとした、感情と構造の接点だった。
■ 小結|自己表現と社会構造の狭間で揺れるミレニアル世代の若者たち
ギャル文化は、若者たちの内発的欲求と社会的制約の交差点に現れた現象だった。
彼女たちは情報技術と都市文化のただ中で、承認と孤独、自由と同調圧力のはざまで、
日々の感情資本を築きあげた。
この時代の経験は、SNS時代以降の若者にも確かに継承されている。
インスタグラムの“ストーリー”、TikTokの“バズ”、Xの“バズらなさ”──
そこには、ギャルたちが先取りしていた「共感と自己演出の構造」が、いまもなお潜んでいる。
ギャルたちの物語は終わっていない。
それは、“見られる時代”を生きるすべての世代にとっての、原点のひとつなのだ。
第8章|Z世代
— 共鳴と流動性 -
■ 境界のない世界に生まれて
Z世代──1996年以降に生まれた彼らにとって、「最初からインターネットがある世界」は前提であり、「他者にアクセスできる自分」が“自己”の最初のかたちだった。
SNS、サブスク、マルチデバイスに囲まれて育った彼らは、世界を物理的な制約で捉えない。
固定された場所や名前、肩書や帰属ではなく、流動的なタグやステータスでつながる関係性。
「自分をどう見せるか」は、他者との関係の中で流動的に調整される。
自分が「誰か」であることより、「誰かとつながっている」ことが重要だった。
■ 生活のリアリティ:オンラインとリアルの等価性
彼らの家庭には、小学生の頃からWi-Fiがあった。タブレットで宿題をし、YouTubeで学ぶ。スマホをリビングに置いたまま、Apple Watchで通知を確認する。
通学電車の中ではBluetoothイヤホンで「推しの配信」を聴き、授業が終われば、スタバのコンセント席で動画編集やSNS更新に時間を使う。
ZEPETOやRobloxでは、「なりたい自分」として友達と遊び、リアルの身体よりもアバターの見た目のほうが“本人らしい”とされる。
部屋には“推し”のグッズが並び、コンビニは日常食のインフラに。
「家族で夕食」という行為は薄れ、親と同居していても、同じ空間で別々の時間を生きている。
食べ物や風景も「インスタ映え」するか否かが価値を左右する。
■ 欲望のかたち:「本当の自分」より「切り替え可能な自分」
Z世代は「自分らしさ」という言葉に慎重だ。
「らしさ」に縛られることを恐れ、自分をひとつの属性に固定しない。SNSでは複数のアカウントを使い分け、Xでは共感ネタを、Instagramでは加工されたリア充を、Discordでは本音を吐き出す。
かつての世代が「仮面を脱ぐ」ことで自由になろうとしたのに対し、Z世代にとっての自由は「仮面を自在に使い分けること」。
彼らの中には、「本質」という発想そのものが重たく、他者に固定される危険なものとして映っている。
「“素を出していいよ”って言われると、逆に怖い」
「ひとつに決めたくない」
「バズりたいけど、バズったあと炎上するのは嫌」
彼らの欲望は、承認されることよりも、“承認されすぎないバランス”にある。
目立ちたい。でも傷つきたくない。
語られすぎたくない。しかし、忘れられたくもない。
■ 摩擦の在り方:「沈黙」や「無関心」という選択肢
Z世代の葛藤は、過剰な自己開示を求める世界との摩擦にある。
親は「何がしたいの?」「夢はあるの?」と訊くが、Z世代にとって“何者かになる”ことは、もはや義務ではない。
学校では「個性を出せ」と言われる一方で、「空気を読め」「調和を壊すな」という無言の同調圧力が支配している。
政治的な発言は、即炎上リスクになる。だから彼らは「発言しない自由」を選ぶ。
LGBTQ+やフェミニズムへの関心もあるが、「語りすぎること」が“過激”や“面倒”とラベル付けされるのを嫌い、静かに「“推す”ことで連帯する」。
かつての世代が「語ることで抵抗」したなら、Z世代は「距離をとることで拒否」する。
■ 価値観と自己像:「流動性」こそがアイデンティティ
Z世代にとっての“正しさ”とは、正しさを語らないことかもしれない。
彼らは“バズること”や“いいねを得ること”に価値を置くが、それを露骨に欲しがると「ダサい」とされる。
- つながりたい、しかし距離もほしい。
- 自分を見てほしい、しかし決めつけないでほしい。
- 安心したい、しかし所属したくはない。
その矛盾の中で、彼らは生きている。
自己像は、固定された人格ではなく、「その場で最適化されたインターフェース」として構築される。
アイコン、ひと言コメント、絵文字、音楽、推しグッズ、着信音。すべてが“自分らしさ”を編集するピースだ。
■ かつての自由/いまの自由
かつての自由は、「与えられた名前や役割から解放されること」だった。
だがZ世代にとっての自由は、「どんな役割も自分で選び、切り替えられること」にある。
“ひとつの仮面を脱ぐこと”が自由だった時代から、
“複数の仮面を自在に使いこなすこと”が自由になった時代へ。
その転換は、抵抗の形をも変えた。
政治を語るのではなく、ミュートする。
街頭に出るのではなく、タグで揃う。
怒りを爆発させるのではなく、「わかる」と言い合うことで緩やかな連帯を起こす。
Z世代の“自由”とは、
「意味づけからの自由」であり、
「ひとつであることを拒む自由」なのだ。
第8.5章|仮面と可変性のはざまで
— あるZ世代たちのエスノグラフィー -
C子
C子の視点(2003年生まれ・SNSネイティブな高専生)
●「“素”とか“本音”とか、逆に何それ?って感じ」
Instagramのメイン垢は、大学受験前に非公開にした。
本音はXの鍵垢(いわゆる“裏”)に吐き出してるけど、それすらも「見られてる感」があって、最近は匿名日記アプリに引っ越した。
仲いい友達とはSnapchat、推し活はLINEオープンチャット、ゼミのグルチャはSlackで通知切ってる。
「自分って何?」って聞かれても困る。
全部“自分の一部”だし、どれも“本当の私”ではないかもしれない。
好きなものはあるけど、「好き」って言った瞬間に、それが“アイデンティティ”になっちゃうのが面倒で。
“推し”も定期的に変えてる。共感されすぎるのもしんどいし、逆に誰にも理解されないのもイヤ。
だから、複数の仮面を持ってる状態が一番安心。
「ひとつの顔」で固定されることが、いちばん怖い。
D太
D太の視点(2006年生まれ・YouTubeと通話アプリで育った高校生)
●「リアルの方が“仮面”でしょ。ネットの方が素に近い」
学校では普通に話すけど、本音はあんまり出さない。
昼休みに誰かといると“ぼっち”って言われなくて済むからいるだけ。
ほんとは家に帰ってから、通話アプリでずっと話してる人たちのほうが気が合う。顔も知らないけど、そっちのほうが素。
スマホは22時までって決まってるけど、Bluetoothイヤホンで寝たふりして、ずっと聞いてる。
話してないと、自分が消えちゃう気がして。
でも、「ひとりでいたい」とも思う。
配信者の言葉に救われることもあるけど、全部を信じてるわけじゃない。
誰も信用してないけど、誰かとつながってたい。
この矛盾、誰にも説明できない。
■ 浮上する世代的な感情構造
2人の語りに共通するのは、「自分が誰かであることへの重さ」への警戒と、「選べる/切り替えられる/距離を取れる関係性」への安心感だ。
ギャルたちが「見られること」「目立つこと」に自我を賭けていたとすれば、Z世代は「見られすぎないこと」に賭けている。
- “炎上しない範囲で注目される”
- “自分を守りながら誰かとつながる”
- “断絶ではなく、緩やかなフェードアウトを選ぶ”
それが、Z世代の感情設計なのかもしれない。
■ 誰にも固定されずに、自分を仮構すること
C子とD太は、「仮面を被っている」自覚はあっても、それが“偽り”だとは思っていない。
むしろ、“仮面こそが自分”だとすら感じている。
これは、「自由とは仮面を脱ぐことだ」と信じた旧世代の価値観とは正反対だ。
仮面を自在に使いこなし、「何者かになること」を保留し続けること。
それこそが、Z世代のサバイバル知であり、生きる戦略なのだ。
■ 結語:本音の時代の終わり?
Z世代のナラティブは、決して「内面が空っぽ」なのではない。
ただ、“内面を表すこと”そのものに疑念があるだけだ。
かつては、素直に語ることで「本当の自分」に近づけた。
しかし今は、語ることすら演出になってしまう。
「本音」や「素」を語れば語るほど、他者によってカテゴライズされていく世界。
だから彼らは、距離をとり、切り替え、可変性をもって応答する。
Z世代にとっての“本当の自分”とは、
「本当の自分を固定されない状態」なのかもしれない。
Vol.3|欲望を照らすモノたち
— 商品・サービスが映す感情のランドスケープ-
商品・サービスが映す
感情のランドスケープ
■ 「モノ」を見ると、欲望が見える
スマートフォン、スニーカー、コスメ、ガジェット、キャラクターグッズ、音楽サブスク…
これらの商品やサービスの背後には、単なる機能や価格以上に、その時代の欲望の形が浮かび上がっている。
なぜ、あるアイテムは熱狂的に求められ、別のアイテムは忘れ去られるのか。
なぜ、似たような商品が「今この時期」にだけ特別に売れるのか。
これらの問いに答えるには、プロダクトを「物質」としてだけでなく、時代の感情インフラとして読み解く視点が必要になる。
つまり、商品やサービスは、世代が何を大事に思っていたかを可視化する“感情のインターフェース”なのだ。
■ プロダクトは、時代の欲望を翻訳する
商品やサービスには、それを生み出した時代の“価値観”が埋め込まれている。
たとえば、1980年代の「ブランド志向」は、所有による社会的上昇の欲望を体現していたし、
2000年代の「癒し系グッズ」は、失われた安心感への回帰を求めていた。
Z世代が愛用する“無名性”と“即時性”を特徴とするアプリや、インフルエンサー発のコスメは、
可変性と個別最適を欲望する時代のプロダクトである。
このように、プロダクトは、感情の形をまとって出現し、やがて廃れていく。
その“栄枯盛衰”のプロセスをたどることで、わたしたちの欲望がどのような地層の上に立っているのかが見えてくる。
■ 1950年代生まれ(戦後復興期)
— 「モノ」が希望だった時代の、音と光と温もり -
「モノ」が希望だった時代の
音と光と温もり
■ 三種の神器がやってきた
ちゃぶ台の中央にラジオが置かれ、夕方になると家族全員が自然とそこに集まる。
外では子どもたちがゴム跳びや缶蹴りに夢中になり、母親たちは井戸端で洗濯機の話をしている。
「電気冷蔵庫が来たのよ」
「あら、うちはまだ氷屋さんなのよ」
そんな日常の会話が、確かな社会の前進を感じさせた。
「三種の神器」と呼ばれたテレビ・洗濯機・冷蔵庫は、単なる便利な家電ではなかった。
それらは“生活の格”を上げ、家族の絆を強め、豊かさの実感を与える象徴だった。
■ 家父長制と家庭内ヒエラルキー
この時代の家庭は明確な序列で構成されていた。
父は絶対的な権威であり、黙っていても家族を統率する存在。
母は家事に従事し、子どもたちは“よい子”でいることが求められた。
団地や長屋での暮らしには、人目というもうひとつの規律があった。
家の玄関を開けっぱなしにすれば近所中の声が聞こえる。
プライバシーよりも、共同体との調和が重んじられていた。
■ 「豊かさ」と「まっすぐな努力」
この世代が欲したのは、「何もない」状態からの脱却だった。
焼け跡と物資不足を知っている親世代に育てられた彼らは、豊かになることを恥とは思わなかった。
- より多く食べられること。
- 自分の部屋があること。
- 家に電話があること。
そうしたモノの獲得は、そのまま「ちゃんとした生活」への階段だった。
勉強し、働き、蓄える…
「努力すれば報われる」という物語は、まっすぐに信じられていた。
まだ未来が「明るくなるもの」として想像できた時代である。
■ 社会との摩擦より、社会への適応
この時代の若者は、制度や大人社会との摩擦を抱えるよりも、
むしろ“その中でどう成功するか”に関心を向けていた。
教師の言うことを守り、就職先を見つけ、結婚して家庭を築く。
そのルートから外れることは、不安でしかなかった。
モノは、その「正解の人生」の中で必要なツールであり、
冷蔵庫やステレオの有無は、自分の人生の進捗を確認するような機能を果たしていた。
■ 「家族の顔」としての自己像
この時代の自己像は、個人よりも「家族の一員」としての役割が先に立った。
子どもは「親の顔に泥を塗らない」ようにふるまい、
母親は「よその奥さんに恥ずかしくない家」を作ろうと努めた。
つまり、モノの所有は、社会的な“顔”を守る装置でもあった。
人は自分のためにではなく、誰かの期待を裏切らないために生きていたのだ。
■ 1960年代生まれ(高度経済成長と反体制文化)
■ 1960年代生まれ
(高度経済成長と反体制文化)
— 「正しさ」に抗いながら、「意味」を探した青春 -
「正しさ」に抗いながら
「意味」を探した青春
■ “大人たち”に対するうっすらとした違和感
1950年代生まれが「モノ」に未来を託した世代だったとすれば、
1960年代生まれは、その“正解”の空気にどこか違和感を抱いていた世代だった。
進学すればよい、就職すればよい、家庭を持てばよい──。
そう言う親たちの背中を見ながら、彼らは問う。
「その人生、本当に幸せそうですか?」と。
経済は成長し、街にはネオンが灯り、欲しいものは手に入るようになった。
しかし同時に、“正しさ”だけが幅をきかせる社会のムードに、どこか薄ら寒さを感じていた。
■ 学生鞄、フォークギター、反戦ポスター
この世代のシンボルは、反骨と表現のアイテムたちだ。
硬質な学生鞄、ギター1本で歌えるフォークソング、壁に貼られたベトナム反戦のポスター。
その一つひとつが、声を上げる手段であり、抵抗の記号だった。
教室で教師の理不尽に抗議すること。
学校の制服に手を加えること。
路上で自作の詩を売ること。
彼らの自己表現は、社会のルールからはみ出すことで生まれていった。
■ 制度の中で「自分探し」を始めた最初の世代
1970年代にかけて、教育制度は安定を見せる一方で、子どもたちの中には“中身の空虚さ”が滲み始める。
偏差値教育、校則、内申点。
「なぜこれが大事なのか」と問うても、誰もはっきり答えてはくれなかった。
そんな中で、この世代は初めて、“自己”というブラックボックスをのぞき込むようになる。
「本当の自分はどこにいるのか?」
その問いは、単なる内省ではなく、社会への批判でもあった。
■ モノが語る“反逆”と“自己の物語”
この世代にとってのプロダクトは、「逆らう」手段であり、「語る」ための道具だったと考える事ができる。
・学生運動のヘルメットやゲバ棒
・劇場ポスターやサブカル雑誌の切り抜き
・自主制作のZINE(個人出版の小冊子)
それらは単なるモノではなく、自分の立ち位置を世界に対して表明するメディアだった。
モノが“生活の質”ではなく、“世界との関係”を示す記号に変わったのは、この世代からかもしれない。
■ 「ノー」と言えることが、自分を持つことだった
この時代の若者は、「社会に馴染む」よりも、「自分の違和感に忠実である」ことに価値を置いた。
たとえ非合理でも、非効率でも、「それは違う」と言えることが、大人になる条件だった。
つまり、モノは“賛同”のしるしではなく、“反論”のツールだった。
ギターを鳴らし、雑誌を切り抜き、仲間とビラを配る。
そんな日常の中に、小さな闘争と、静かな誇りがあった。
1970年代生まれ|中流幻想と個室文化のはじまり
1970年代生まれ
中流幻想と個室文化のはじまり
— 「みんなと違う自分」が欲しかった時代 -
■ 「何不自由ない」ことが、どこか物足りなかった
1970年代生まれの子どもたちは、戦後の成長と混乱が一段落した「安定」の中に育った。
テレビは一家に2台、車もあって、郊外には新興住宅地が広がる。
家族旅行、塾通い、ファミレスでの外食…
親世代が渇望していた“豊かさ”が、ある程度満たされた社会だった。
だがその分、どこか画一的で、閉塞的だった。
「いい学校に行って、いい会社に入ればいい」と繰り返す親たちの言葉は、
この世代にとって、安心というより「予定調和への同調圧力」として響いていた。
■ ジャンプ、ウォークマン、カセットテープ
この世代のプロダクトは、「個人化」と「パーソナルな感情」に接続されている。
『週刊少年ジャンプ』の熱狂的な読者文化。
ウォークマンで音楽を“ひとりで”聴く体験。
好きな曲を録音したカセットテープを交換するコミュニケーション。
共通しているのは、「日常にひとりだけの領域をつくる」感覚だ。
それは、家族単位のコミュニケーションや、学校社会の序列から一歩距離を置き、
“自分だけの世界”を持ちたいという初期的な欲望の現れだった。
■ 家庭内個室化と感情のパーソナライズ
70年代後半から80年代にかけて、「子ども部屋」の文化が定着していく。
リビングで家族と過ごす時間よりも、自分の部屋に閉じこもってマンガを読んだり音楽を聴いたりする時間が増える。
この「個室化」は、単なる住環境の変化ではない。
感情や欲望の単位が“集団”から“個人”へと移行する構造的な分岐点だった。
親の持つ価値観を「反抗」ではなく、「距離を取る」ことで回避する。
反体制ではなく、非関与。政治ではなく、感性。
そんな空気がこの世代には根強く流れていた。
■ メディアと共に育った自己像の分裂
もうひとつの特徴は、メディアとの共生である。
この世代はテレビ・マンガ・ゲーム・雑誌といったメディアコンテンツを、
消費者であると同時に、“自分づくり”の素材として受容していった。
ジャンプの主人公たちのように生きたい。
アイドルのように見られたい。
ラジオの深夜番組にハガキを送りながら、自分の存在を確認する。
こうして、「外からつくられた自己像」と「内にある本当の自分」のあいだに、
ギャップやズレを感じながら成長していったのが、この世代だった。
■ モノがくれた“ひとりでいる自由”
この世代にとってモノは、仲間とつながるための道具ではなかった。
むしろ、“ひとりでいる自由”を可能にするインターフェースだった。
- 自分だけの選曲がつまったカセットテープ
- 誰にも見せないマンガのスクラップ帳
- 雑誌の切り抜きでつくったコラージュのノート
それらのプロダクトは、家庭や学校という制度の中では得られなかった
「自分の領域」を静かに、しかし確実に切り開いていた。
1980年代生まれ|バブルと自己演出のはじまり
1980年代生まれ
バブルと自己演出のはじまり
— 「どう見せるか」が人生の中心に置かれた時代 -
「どう見せるか」が
人生の中心に置かれた時代
■ 消費が“演出”になった最初の世代
1980年代生まれは、バブル経済の絶頂と崩壊の狭間で育った世代である。
街に流れるJALのCM、テレビを飾る原宿発のファッション、カリスマ読モたちの雑誌グラビア。
それらは、単なる広告やファッションではなく、“なりたい自分”を見つけるためのテンプレートだった。
彼らが子どもから思春期へと向かう90年代半ば、社会にはまだバブルの残り香が漂っていた。
親世代がブランドバッグを掲げ、DCブランドに身を包み、海外旅行に浮かれるなかで、
「見せるための消費」が当たり前の空気として家庭内に流れ込んでいた。
自分を飾ること。周囲に「いいね」と思われること。
消費は、ステータスの誇示や実利のためではなく、自己演出の手段として機能しはじめる。
アムラー、コギャル、ルーズソックス、ケータイストラップ。
これらはすべて、“見せる前提”で選ばれ、使われていた。
■ メディアと“鏡像の自分”
この世代にとって、メディアは「情報源」ではなく、「もうひとつの現実」だった。
テレビドラマの都会的な恋愛、音楽番組に出てくるスタイル、ファッション誌の読モたち。
それらは手の届かないものではなく、“なりうる理想像”として消費されていた。
本当の自分よりも、「映える自分」「見られる自分」が重要になる。
ルーズソックスの履き方、プリクラでのポーズ、カリスマモデルの真似。
自己は内側から掘り下げるものではなく、外側から組み立てられていくものだった。
“メディアの中に理想がある”という感覚が、この世代の深層には染み込んでいる。
それは、後にSNSによって可視化・加速される「自己演出の社会」の、静かなはじまりだった。
■ 「自分らしさ」は、他者の目から作られる
DCブランドやカリスマ読モの「個性」もまた、あらかじめデザインされたスタイルだった。
「自分らしく」あることは、選択肢から“適切に選ぶ”ことでしかなかった。
自分の趣味も、服装も、表情さえも、他者の評価を前提とした演出だった。
だからこそ、「自分らしさ」は、いつもどこか空虚だった。
「私ってこういう人間だから」ではなく、「こう見えるようにしているから、私はこう」なのだ。
■ 見せるためのモノ、“語彙”としての消費
この時代のモノは、所有することで何かを得るのではなく、見せることで自己を語る道具だった。
- ブランドバッグ=階層や大人っぽさの演出
- PHSやケータイ=流行感度や通信スピードの誇示
- 制服の着崩し=集団との距離感や“ノリ”の可視化
アムラーやコギャルのスタイルもまた、仲間と“そろえる”ことで共鳴し、差異を通じて個性を出す表現だった。
見せ方こそがコミュニケーションの核となり、プロダクトはその“語彙”として機能した。
■ 見えないプレッシャーと、「らしさ」の疲労
しかしこの「演出としての自己」には、常に他者の視線がつきまとう。
「どんなに工夫しても、結局、他人の評価で価値が決まる」
そんな感覚が、この世代の深いところにある焦燥や不安の根となっている。
見る/見られるの構造が、コミュニケーションの前提になった最初の世代。
そして、消費=自己表現の舞台装置という構図が、この時代の“モノ”に刻まれていた。
1990年代生まれ|不況下の“日常の祝祭化”
1990年代生まれ
不況下の“日常の祝祭化”
— 「ふつうの毎日」をいかに彩るかが感情の焦点 -
「ふつうの毎日」をいかに彩るかが
感情の焦点
■ 「豊かさ」は、手の届く楽しさに変わった
1990年代生まれは、バブルの余韻を知らない最初の世代である。
景気は停滞し、ニュースでは「失われた10年」「就職氷河期」といった言葉が飛び交っていた。
しかし、彼らの暮らしには、悲壮感よりも「それなりに楽しむ」軽やかさがあった。
プリクラ、たまごっち、ポケベル、PHS、ガラケー──。
そうした身近なガジェットやサービスは、大きな夢ではなく、小さな遊びを提供してくれた。
それは、身の回りの「ふつう」をカスタマイズして、“ちょっと楽しく”見せるための道具だった。
祝祭は、特別な日ではなく、日常のなかにあった。
プリクラで友達とふざけ合い、ゲームセンターで景品を取り合い、
放課後のコンビニ前で、ただしゃべって笑う。
日常こそが舞台であり、そこに“演出”を持ち込むことが、この世代の新しい感性だった。
■ 「共感」がつながりの単位になった
この世代は、「群れ」や「集団」に強く依存しない。
仲間とは、地縁や学校といった固定的なつながりではなく、
同じノリやテンションで共鳴できる関係でつながっていた。
プリクラ帳、キャラもの文房具、UFOキャッチャーの景品、着メロ──。
それらは、情報感度やセンスをさりげなく示すアイテムであると同時に、
「あなたもそれ好きなの?」という共鳴のトリガーでもあった。
仲間内で盛り上がる“内輪の祝祭”が、何よりも大切だった。
友達と揃えて買ったキャラクターグッズや、交換日記に貼られたシール。
そこにあったのは、大きな物語ではなく、小さな共感の物語だった。
■ 「手の届く特別感」こそが価値
この世代にとって、特別であることは、努力や才能の結果ではない。
誰でも手が届く範囲のなかで、ちょっと可愛く、ちょっと個性的であることが重要だった。
制服のリボンを少し変える、デコメでメールを飾る、プリクラに背景を足す。
そうした細部の工夫に、“自分らしさ”がにじみ出る。
ただし、その“らしさ”もまた、雑誌やテレビが提供するテンプレートの中で選び取られたものだった。
可愛さや楽しさは、等身大であることが前提。
「がんばらないけど、ちゃんと見せたい」
そんなゆるく構えた自己演出が、この時代のモノやサービスに反映されていた。
■ 「飾るモノ」から「盛るモノ」へ
ガラケー文化は、この世代の“感情のインターフェース”だった。
ストラップの数や種類、着信画面、デコメのセンス。
それらは、「誰かとつながる」ためではなく、どう“盛るか”という個性の見せ場だった。
- プリクラ帳=友情の証/遊びの記録
- デコメ絵文字=センスと感情の表現
- ガチャグッズやキャラ文具=かわいい“共感ポイント”の提示
こうしたアイテムは、自分を語るための言語であると同時に、
他者との距離感やテンションの調整装置でもあった。
■ モノは、世界と「ほどよくつながる」媒介だった
1990年代生まれにとって、モノは“自己演出”だけでなく、
周囲とのノリを合わせるための潤滑油でもあった。
見せびらかすのではなく、さりげなく共鳴させる。
主張しすぎない範囲で「わたしらしさ」をにじませる。
- 「仲間はほしいけど、ベッタリはイヤ」
- 「個性は出したいけど、浮きたくはない」
そんな微妙な距離感を成立させる感情のインフラとして、
この時代のプロダクトたちは機能していた。
2000年代生まれ|“個の拡張”としてのガラケー文化
2000年代生まれ
“個の拡張”としてのガラケー文化
— 「つながること」が自己表現になる時代 -
「つながること」が自己表現になる時代
■ 「モノ」は自分の延長線になっていった
2000年代前半に生まれた世代の一部は、ガラケーを通じて他者とつながる文化に強く影響を受けた世代でもある。
小学校高学年〜中学時代にモバゲー、前略プロフィール、デコメなどを使いこなし、
そのプロダクトは、単なる道具ではなく、感情や関係性を写す“もう一つの自己”として機能していた。
携帯電話には、待受画像、着うた、プロフ、絵文字など、自分好みにカスタマイズされた「自分だけの世界」が広がっていた。
こうした傾向は、それ以前の世代に見られた「所有するモノ」としてのガジェットから、
“自己を構成するメディア”へと進化した形とも言える。
■ 「誰かといるときの自分」にリアリティが宿る
この世代にとって、「自分らしさ」は他者と接続された状態でこそ実感されやすかった。
“誰かとつながっている”ことで確認できる自己という感覚が、日常に浸透していたように見える。
メールの送受信数、プロフィールの訪問数、ゲームでつながる友人の数──。
そうした「反応」や「痕跡」が、自分という存在の輪郭を示す尺度として意識されていた。
モバゲーやプロフ帳、デコ画像の共有などを通じて、
自己表現は「誰かに見せること」を前提に進化していったといえる。
個人の輪郭は、単独ではなく、他者との関係のなかで立ち上がるものになっていた。
■ 「自然体」も、どこか調整されたスタイル
この時代の「個性」は、強く打ち出すものではなく、
日常の中で“微調整”されるものとして現れていた傾向がある。
どの画像をトップに置くか、誰とのプリクラを載せるか、
どんな絵文字や文字装飾を使うか──。
それらは、「自然な自分らしさ」をいかに演出するかという選択の連続だった。
完全な“素”では落ち着かない。
しかし、“やりすぎ”も好まれない。
そんな絶妙なバランス感覚が、
この時代の「リアルさ」の基準だったと考えられる。
■ 感情は、言葉より「匂わせ」で伝える
ガラケー文化におけるコミュニケーションは、
直接的な言語よりも、雰囲気や感覚での共有に重きが置かれる傾向があった。
- デコメ絵文字は、文字だけでは伝わりにくい感情を彩った。
- 待受画像は、そのときの「気分」や「空気感」をにじませるメディアだった。
- プリクラや前略プロフィールは、関係性や現在地を可視化するツールとして機能していた。
このように、感情や状態を“匂わせる”表現手法が文化の一部となっていった。
「好き」「さみしい」と言葉にせず、
それらを“察してもらう”ためのビジュアル言語が重視された。
■「つながり方」は、自分で選ぶ時代へ
この時代の携帯電話は、
他者とのつながり方を“自分で設計できるツール”としての役割を強めていった。
友達リストは多くても、やり取りする相手は限られている。
すべての投稿が「オープン」ではなく、
“誰にどれだけ見せるか”をコントロールする感覚が育っていった。
この「関係の距離を調整する感覚」は、
後のスマホやSNS文化──たとえば鍵アカ、ストーリー、既読スルーといった
「つながりすぎない設計」の萌芽として見ることもできる。
■ 前後世代との接続に触れる
1980〜90年代生まれの世代が“自己演出”や“祝祭的な日常”の感覚を育てるなか、
2000年代生まれの世代では、それがより感覚的かつインターフェース的な自己表現へと進化した。
こうした文化は、次世代において、SNS上の複数人格的なセルフ表現や、
“本音と建前の使い分け”の感覚としてさらに拡張されていくことになる。
2010年代生まれ|分人主義と可変的自己の時代
2010年代生まれ
分人主義と可変的自己の時代
— 「キャラ」がリアルを超えていく時代 -
■ 「わたし」は、一つじゃなくてもいい
2010年代に生まれた世代は、はじめから“インターネットと共にある世界”に育った最初の世代の一つだと言える。
スマートフォンは家庭内に浸透し、小学校の高学年になる頃には一人一台が当たり前という環境も多く、
TikTokやYouTubeなどの動画コンテンツを通じて、“視覚で他者を知る・見せる”ことが生活に組み込まれている。
この世代の特徴の一つとして挙げられるのが、
「自分とは何か?」を一つに定義しようとせず、状況や文脈によって複数の自分を切り替えて使い分けるという感覚だ。
親や教師の前での「まじめな自分」、
友人グループでの「ノリのいい自分」、
ゲームやSNS上の「別の人格やアバター」…
それらを無理に統合せず、“すべてが本当の自分”として自然に共存させるという意識が広がっている。
■ SNSの“本音アカ”文化とキャラの使い分け
このような可変的な自己感覚は、SNSの使い分け文化にも現れている。
- 本音を出す“裏垢”や“鍵垢”、
- 趣味専用のサブアカウント、
- ストーリーだけで存在感を出す“見る専”。
こうしたアカウントの併用は、2010年代生まれのZ世代後半〜α世代初期にとってはごく自然な行為であり、
一人の人間が複数のキャラや感情レイヤーを持つことへの違和感がない。
このような感覚は、哲学者・平野啓一郎が提唱した「分人主義」と重なる部分も多く、
「一貫した本当の自分」よりも、「誰といるかによって生まれる複数の自分」こそがリアルという感覚が強い。
■ 感情は「顔」や「声」ではなく、「編集された時間」で伝える
この世代が最も親しんできた表現手段は、短尺動画と動的ビジュアルである。
TikTok、YouTube Shorts、インスタのリール──。
そこでは「どんな言葉を発するか」ではなく、
「どのBGMを使い、どのフィルターを重ね、どんなテンポで切るか」によって、
気分・感情・主張を伝える方法が主流となっている。
その結果、“感情は編集でつくるもの”という感覚が日常に入り込んでいる。
- 悲しみも、かわいく編集される。
- 怒りも、ネタとしてラッピングされる。
- 「かわいい自分」も、「ぶっちゃけキャラ」も、演出次第で共存できる。
それは、リアルと演出の境界が“意識的に編集可能なもの”になったという意味でもある。
■ 「キャラ」は“本当のわたし”を隠すものではなく、見せる方法の一つ
かつては「素の自分=本当の自分」とされ、「キャラ」は“仮面”や“嘘”として扱われがちだった。
しかしこの世代にとっては、キャラは“自分のある一面”を効果的に伝えるための形式であり、
「演じること」が必ずしも“偽ること”ではないという前提が広く共有されている。
これは、VTuberやアバター文化ともつながる。
バーチャルな身体や名前であっても、そこに本音や感情が込められていれば「リアルなわたし」として受け入れられる。
フィジカルではなく、コミュニケーションの質こそが“自分”を規定する要素になりつつある。
■ “見られる”から“見せる”へ、そして“切り替える”へ
スマホと動画文化の中で育ったこの世代にとって、
「見られる自分」を意識するのは当然の前提となっている。
しかし、それをプレッシャーと捉えるのではなく、
“状況に合わせて見せ方を選ぶ”という感覚に変換する能力が育っている。
ある意味では──
- 自己演出が重くてしんどかった1980年代生まれ
- 軽やかな演出を楽しんだ1990年代生まれ
- つながりで自分を構成した2000年代生まれ
こうした世代の文脈を引き継ぎつつ、
「柔軟な自己編集」を日常的に実践する世代ともいえる。
■ 複数の「わたし」を管理する力、それが新しい“リアル”
ひとつの価値観に縛られず、
複数の自己を持ちながらも、それらを自分で切り替え・管理し・更新する力。
それは単なる“キャラ変”ではなく、関係性の中で可変的に生きることを肯定する知恵でもある。
「どれが本当のわたし?」ではなく、
「どの“わたし”も、ある状況ではリアルだった」と捉えられるこの柔軟さは、
変化の多い時代を生きるうえでの、重要な自己戦略になっているのかもしれない。
■ まとめ|プロダクトが語る「わたしたちの気分」の地層
消費は、単なる買い物ではない。
わたしたちは、モノを通じて、自分を知ろうとしてきた。
どの時代も、目の前のプロダクトには、その瞬間の欲望や不安、期待や諦念が投影されていた。
1950年代に生まれた人びとは、家電という“未来の象徴”に夢を見た。
1970年代は、音やマンガのなかに、自分の部屋と感情の輪郭をつくっていった。
1980年代は、ブランドという他者の目に、“わたし”を貼り付けた。
1990年代には、モノが“日常のイベント”になり、友だちとの共鳴が自分をつくった。
2000年代は、ガラケーを手に「わたし専用の世界」をカスタマイズした。
2010年代には、“キャラ”を切り替えることで、ひとつではない自己を肯定する感覚が育った。
こうして見てみると、プロダクトとは、時代ごとの“感情インフラ”だったことが、あらためて浮かび上がってくる。
それは単に何を買ったかではなく、
どんな“気分”が、それを欲望させたのかを掘り起こす作業である。
“何が流行ったか”だけを並べても、わたしたちは自分の時代を語ることはできない。
そこにあるべきなのは、なぜ、それが必要だったのかという問いである。
プロダクトの背後には、わたしたちの「生きづらさ」も、「楽しさ」も、「すれ違い」も刻まれている。
それを読み解くことは、単なる懐古でも、単なるマーケティング分析でもない。
そして、この一連の感情の履歴をAIとの対話を通じて深掘りし、客観的な視点を得たことで、
私たちはこれまで見過ごされがちだった、モノと感情のより複雑な結びつきを多角的に捉えることができた。
それは、わたしたちの“感情の履歴”を読み直すことなのだ。
Vol.4|未来の世代はどこにあるのか
— AIとエスノグラフィーによる感情の予測地図 -
AIとエスノグラフィーによる
感情の予測地図
これまでの章では、過去の「感情の地層」を掘り起こしてきました。
では、この分析を未来へと繋げるには、どうすれば良いのでしょうか。
次章では、AIがどのように私たちの感情履歴の記述をサポートし、さらにその先にある「感情の予測地図」を描き出す可能性を探ったのか、その具体的なプロセスをご紹介します。
AIによる定量的なデータ分析と、人間による定性的なエスノグラフィーの融合が、いかに感情の未来を読み解く新たな視点を提供しうるのかを見ていきます。
「これからの世代」は、まだこの世界に生まれていない。
あるいは、生まれていても、名前を持たず、集団とも認識されていない。
だが、わたしたちはすでに、その“未来の感情”を育て始めている。
過去を記述することは、未来を構想する準備である。
1950年代から2010年代まで、わたしたちはプロダクトや文化を通じて、ある種の「感情の履歴書」を書き綴ってきた。
そして今、その地層の上に、「次の気分」は芽吹こうとしている。
問題は、「どのように予測すればよいのか?」である。
消費トレンドや技術革新を読むことはできても、「まだ可視化されていない感情」を、どうすれば掴めるのか?
ここで手がかりになるのが、AIによる定量的分析と、エスノグラフィー(民族誌)的な定性的観察の融合である。
数百万件の言葉や行動を機械が読み解く時代に、わたしたちはその中から、“まだ名前のついていない感情”を抽出できるかもしれない。
つまり、ここからの問いはこうだ。
「未来の世代」は、どこにいるのか。
そして、どのような“気分”をまとって現れるのか。
次章では、この方法論を実際に組み合わせ、“感情の未来”を仮説的に描く試みを展開していく。
Vol.5|“今ここ”の情動を見える化する
Vol.5|“今ここ”の情動を
見える化する
— 記述・構造・生成の三位一体モデルの試み -
記述・構造・生成の三位一体モデルの試み
■ 感情を「記録」することから始まる
わたしたちの試みは、まず一人ひとりが抱いた感情を記述することから出発する。
その瞬間の出来事、身体の反応、浮かんだ言葉や沈黙の重み。
これらを丁寧に書き留めることは、個人の内面を外化し、後から再び“読み直せる”形に変える営みだ。
記述は断片的であり、不完全である。
しかし、その不完全さこそが「観測点」となり、後続の解釈や構造化を可能にする。
■ 感情を「構造」に位置づける
次の段階では、その記述を構造に結びつける。
単なる個人的な記録を越えて、複数人のデータが重なり合うと、感情のパターンや流れが見えてくる。
- どの場面で怒りが生じやすいのか。
- どんな環境で安心が生まれやすいのか。
- その背後にはどんな社会的・文化的コードが働いているのか。
構造化の過程で、個別の体験は「感情地層」として積み重なり、個と社会の間に横たわる関係性を浮かび上がらせる。
■ 感情を「生成」する未来へ
そして三つ目の段階が生成である。
記述と構造の分析から導き出されたパターンは、やがて新しい体験や感情の設計へと応用される。
たとえば、ある空間をどう設計すれば安心感が増幅されるのか。
どの物語が、人々に共通する共感を呼び起こすのか。
「生成」とは、感情のデータを未来の出来事にフィードバックする試みである。
それは単なる再現ではなく、あたかも“未来の地層”を先取りするような行為に近い。
■ 観測点としての「わたしたち」
こうして「記述」「構造」「生成」が三位一体となったとき、わたしたちは感情をめぐる複雑な運動のなかで、自らを観測点として再定義することになる。
私たち自身がデータを生み出し、同時にそのデータを参照し、未来を形づくる存在となる。
「感情を観測する主体」と「感情を生成する主体」が重なり合う地点――そこに立ち上がる新しい風景こそ、このプロジェクトの全体設計が目指すものである。
エピローグ
感情を記録することは、過去を振り返るためだけではない。
構造として見渡すことは、いま起きていることを理解するためだけでもない。
生成の回路へとつなげるとき、感情は未来の社会をかたちづくる設計資源となる。
その営みの只中に、わたしたちは「観測点」として存在している。
主体であると同時にデータでもあるという、矛盾を抱えた存在として。
その矛盾を解くことはできない。
だが、矛盾に踏みとどまりながら記述し、構造を編み、生成に手を伸ばすとき、はじめて“感情地層”という大きな地図が立ち上がる。
このプロジェクトは、その地図の一枚を描く試みであり、続きは、わたしたち自身の歩みに委ねられている。



