《 視座を選ぶ自由 》
- 無自覚なプレイヤーから抜け出すために -
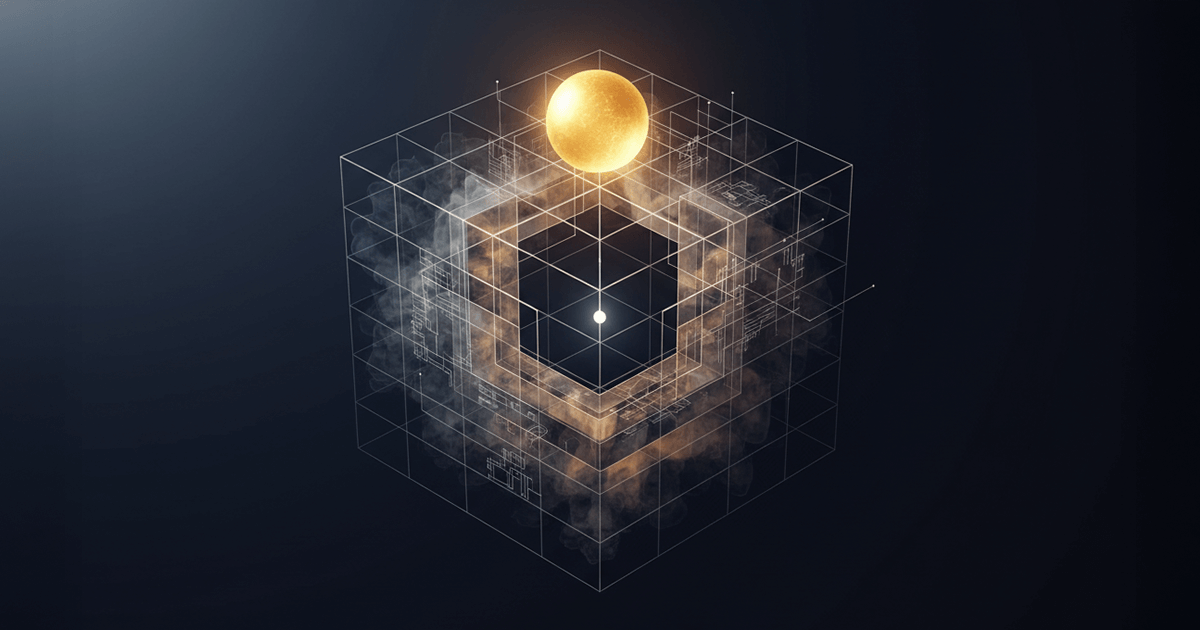
プロローグ:
私たちは日々、無数の「物語」のプレイヤーとして生きている。
それはSNSでのシェア、寄付、怒りといった善意の行動の瞬間に、誰かが設計した構造へと無自覚に加担しているのだ。
厄介なのは、「正しいことをしている」という確信が、他者への想像力や配慮を鈍らせることである。
気づけば、私たちは自分がどの物語の中にいるのか、そのプレイヤーであることを自分で選んだのか、という問いを忘れてしまう。
このコラムは、「悪意」ではなく「善意」を凶器に変えてしまう構造から、いかにして抜け出すかを探る。
鍵は、世界との関係性を変える力を持つ「視座のジャンプ」である。無自覚なプレイヤーから、どのプレイヤーになるかを選び直す自由を手にする、それがこの試みの本質なのだ。
Vol.0|巻き込まれるということ
— どの物語に、加担しているのか -
■ 善意の構造に取り込まれる瞬間
何かを信じて行動するとき、私たちはその構造の中でプレイヤーになっている。
それは、特別なことではない。
むしろ日常のあらゆる場面で、私たちは何かの構造に“参加”している。
SNSで特定の発言をシェアしたとき、
チャリティに寄付したとき、
政治的なニュースに怒りを覚えたとき。
そこに、「自分の意思」があるように思える。
だが、その意思は本当に、自分の視座から発動したものなのか?
気づけば、私たちは誰かが設計した物語のプレイヤーになっている。
しかも、そのことにほとんど気づかないまま。
■ 善意であることが、免罪符になる怖さ
問題は、「悪意があるかどうか」ではない。
むしろ厄介なのは、“善意であるがゆえに”自分のふるまいを疑わなくなることだ。
「正しいことをしている」という自負は、思考停止をもたらす。
その瞬間、自分の行動が誰かを傷つけているかもしれないという想像力は鈍る。
疑いの余地のない正義は、最も危険な武器になる。それは歴史の中でも、日々の会議室の中でも、繰り返されている。
■ 「参加していないつもり」が最も危うい
何かに巻き込まれているという自覚がない人ほど、構造の中で積極的な役割を担ってしまう。それは、正義感に駆られる活動家だけではない。沈黙を貫く観客も、ある意味でその物語の“加担者”なのだ。
「自分は関係ない」「自分はどちらにも属さない」
その無自覚な立ち位置こそ、構造を見えなくさせる最大のフィルターになる。
■ どの物語の登場人物になっているのか?
大切なのは、「プレイヤーになるな」という話ではない。問題は、自分が今どの構造に巻き込まれているのかを自覚しているかどうか。そして、そのプレイヤーであることを自分で選んだのかどうか。
物語は、日々立ち上がっている。それはメディアの中だけではない。職場の会話の中、SNSのタイムライン、NPOの活動報告、あるいは家族の中で。それらはすべて、ある種の物語だ。
そして私たちは、そのどれかのプレイヤーとして日々生きている。
Vol.1|視座のジャンプ
— 見えているものが、変わる瞬間 -
■ 「構造を見たい」という欲望
人は時折、世界の“裏側”を見ようとする。目の前で起きている出来事が、単なる偶然ではなく、何かの構造に沿って起きているのではないか――そんな予感に取り憑かれるときがある。
ニュース、SNS、社内の会議、政治的言説。どれも表面的には異なる文脈に見えるが、「構造としては似ている気がする」と直感することがある。
それは、構造を見る“視座”が生まれた瞬間だ。そしてこの視座は、持ってしまったが最後、もう以前のようには世界を見られなくなる。
■ 視座とは、立ち位置のこと
「視座」とは、単にものの見方ではない。それは、世界に対して自分がどの地点に立っているか――その位置のことだ。つまり、何を前提として、どの高さ・距離からその現象を捉えているか。
たとえば、現場の営業担当は、取引先との信頼関係から「この施策は現実的じゃない」と言う。一方で経営陣は、「中長期で見ればこの投資は妥当だ」と主張する。
どちらが正しいという話ではない。彼らは、異なる視座に立っているのだ。視点の違いではなく、“立っている場所”そのものが違う。
■ 視座が変わると、ナラティブが変わる
同じ出来事も、視座が変われば意味が変わる。「不正義の告発」は、「感情的な攻撃」にもなりうるし、「場を和ませる冗談」は、「無意識の差別」とも捉えられる。
つまり、出来事そのものよりも、どの視座から語られた物語かが、その意味を決定づけている。それに気づくとき、世界の“語られ方”が変わる。
自分が信じていた物語が、ある視座から見た幻想だったと知ることは、多くの人にとってひどくショックな体験になる。だが、そのショックこそが、視座のジャンプを促す。
■ ジャンプは選べる、ということ
視座は、固定されたものではない。思考を重ね、観測点をずらすことで、人は意識的にジャンプすることができる。それは、世界との関係性を変える力を持っている。
この視座のジャンプができる人は、構造の中に自分がいることを自覚し、ときにその構造から一歩外れて見ることができる。誰かを責めることなく、ただ起きている現象を眺めることができる。
プレイヤーであることをやめるのではない。どのプレイヤーになるかを選ぶための“自由”を手にすること。それが視座のジャンプの本質なのだと思う。
Vol.2|正義の構造
— 配慮の欠落が、善意を凶器に変える -
■「正しさ」は、暴力の起点になりうる
多くの人が、善意から行動している。差別をなくしたい。弱者を守りたい。不正をただしたい。
その根底にある感情が純粋であればあるほど、その人は「正しさ」に確信を持つようになる。だがその確信が、ふとした瞬間に他者への“攻撃”へと転じてしまうことがある。そしてそのとき、本人にとってそれは“攻撃”ではない。ただ「正義を実行している」に過ぎないのだ。
だからこそ、それは危うい。無自覚のまま発動される“正義の構造”は、予想以上に強固で破壊的だ。
■ なぜそれが「配慮の欠落」に至るのか
本来、配慮とは「他者の存在を想像する力」だ。しかし、自分の“正しさ”が確信に変わったとき、その想像力は一気に鈍くなる。「こんなことを言ったら、相手はどう受け取るだろう?」という問いが消えてしまうのだ。
正しさが、配慮を殺す。そしてそれが、正義の構造のなかでもっとも厄介な点だ。悪意ではなく善意が、暴力の扉を開いてしまう。
■ 歴史はこの構造を何度も繰り返してきた
ポル・ポト政権による大量虐殺、宗教的な異端審問、“正しさ”の名の下で行われた戦争。それらの多くは、無自覚な正義の発動によって起きている。
誰もが「自分は悪を成している」とは思っていなかった。むしろ、「人類の未来のため」「神の教えのため」――そんな“善意”の確信こそが、数えきれないほどの犠牲を生み出した。
そしてこれは、過去の話ではない。現代でも、SNSの炎上、社会運動、企業改革の中に同じ構造が静かに潜んでいる。
■ ナラティブの中にいるということ
この構造がやっかいなのは、人が「物語の中にいること」を忘れてしまうからだ。
イエス・キリストが十字架にかけられたのも、“正義の物語”の中での出来事だった。多くの人が、それを「正しい選択」として加担した。その背景には、政治的・宗教的な構造とナラティブが複雑に絡んでいた。
善悪の判断を支えていたのは、それぞれの人の「視座」と「所属する物語」だった。その自覚がないままに、誰もがプレイヤーとして動いていた。
■ 「問い」が始まる場所に立つ
問題は、「正しさ」を持つことではない。それを“疑いなく”行使してしまう構造にある。
そして、そこに気づくためには、問いが必要だ。
自分が今、どのナラティブの中にいて、どんな視座から、誰を“正して”いるのか。その問いが、配慮を取り戻す鍵になる。
この章は、問いのはじまりの場所にすぎない。構造の中にある自分自身を見つけること。それが、真の意味での“プレイヤーの選択”へとつながっていく。
Vol.3|悪魔と構造
— あらかじめ決まっている、という絶望と光 -
あらかじめ決まっているという
絶望と光
■ すべては構造に支配されているのか?
ある瞬間、ふとこう思った。
「あ、人間って詰んでるな」と。
何をどう選んでも、結局は構造の中に巻き込まれていく。善意も悪意も、戦争も祭りも、たいていのことが「同じパターン」で繰り返されている。
選んでいるつもりで、選ばされている。思考しているつもりで、与えられた問いの上で踊らされている。
“構造がすべてを決めている”という感覚。そこに立ったとき、希望は薄れる。
■ ラプラスの悪魔とレミングの本能
この感覚は、「ラプラスの悪魔」によく似ている。
すべての因果を知っている知性があれば、未来は完全に予測可能になる――そんな決定論的な世界観だ。
さらに、生物学的な視点から見れば、“群れの自滅”すらプログラムされているように思える。
いわゆるレミングのように、ある種の自己崩壊が自然の一部として組み込まれているとしたら、人類の争いや破壊も「個々の意思を超えた遺伝的衝動」によるものなのかもしれない。
そう考えると、戦争すら「自然のアポトーシス(計画的自壊)」に見えてくる。破壊と再生のリズムは、地球規模でバランスを取るための手段なのかもしれない。
■ 神の会議、そして神話の中の構造
こんな妄想もよぎった。
もし、各生物の代表のような“神”がいたとしたら?
彼らが年に一度、島根あたりに集まって、「今年は鹿を10万減らそう」「いや、狼をもう少し戻そう」などと会議しているとしたら?
そんな構造的ユーモアに包まれているのが、実は神話の本質ではないかと。
古事記で描かれる神々のやり取りも、構造としての“調整”を象徴していたのではないか。
イザナミとイザナギの言い合い――「お前が一日五百人殺すなら、私は一日千人生む」
これは自然界の死と再生、破壊と創造のバランスの比喩かもしれない。
■ フラクタルの中に生きているという自覚
結局、どこを切り取ってもフラクタル構造に見えてくる。
個人、組織、社会、国家、地球、生態系――
すべてが同じようなリズムとパターンで動いている。
そしてその中で、人は無自覚に「コントロールしよう」とする。
まるで、それが自分の役割であるかのように。
でも、それもまた構造の一部。
「人が人をコントロールしようとする構造」もまた、
大きな“物語”の中に織り込まれている。
■ それでも、選べるという希望
そんな中で、ひとつだけ希望があるとすれば――
人は、「今、自分がどのプレイヤーになっているか」を自覚することができる。
そして、そのプレイヤーを“選び直す”こともできる。
構造がすべてを支配しているかのように見えても、
観測し、問いを持ち、視座を変えることで、
わずかに軌道をズラすことができる。
マクスウェルの悪魔が熱の偏りを見つけるように。
「観測」が、変化のトリガーになる。
それはきっと、微細でも確かな“選択”なのだ。
■ 構造を知ったその先で、再び選ぶ
構造を見ようとする欲望は、
決してすべてをコントロールするためではない。
むしろ、“流されていた自分”を見つけるためのものだ。
そのうえで、
自分がどのナラティブを語り、
どのプレイヤーを選ぶのか。
それは、「希望」に似た動き方なのだと思う。
Vol.4|選び直しの技法
— 構造に気づいたあと、人はどう生きるのか -
■ 無自覚のプレイヤーから、自覚的なプレイヤーへ
私たちは、いつの間にか「何かのプレイヤー」として生きている。
それは「教師」「経営者」「親」「活動家」「リーダー」…
役割として与えられたものもあれば、気づかぬうちに自ら選び取ったものもある。
その役割にどっぷり浸かりすぎると、
自分が“なぜそれを演じているのか”を忘れてしまう。
気がつけば、他者に影響され、構造に巻き込まれ、
視座も発言もふるまいも、全部が“無意識の再演”になっていく。
そのことに気づいたとき、初めて「選び直す」という問いが立ち上がる。
■ 視座のバリエーションを知るということ
同じ現象を、異なる視座から眺めるとまったく違う物語が立ち上がる。
たとえば「コロナ禍」――
ある人にとっては「人類への警告」であり、
別の人にとっては「社会実験」や「陰謀の暴露」だったりもする。
政府の立場、医療従事者の立場、飲食店経営者の立場、
子育て中の親、都市のホームレス、アーティスト、大学生、旅行業者…
その一つひとつの視点に「正しさ」がある。
その一つひとつのナラティブに「痛み」と「選択」がある。
視座のバリエーションを知ることは、
絶対的な正解を持たないことと向き合うことでもある。
そしてそれは、“構造を見破る”技術ではなく、
“構造を観察する”姿勢へと私たちを連れていく。
■ 選び直しとは、「どの物語に立つか」を意識的に選ぶこと
選び直すとは、
「自分はどの物語のプレイヤーになっていたのか?」を見つけ、
そこから一歩離れてみるということだ。
たとえば、
「無意識に“正義”をふりかざしていなかったか?」
「誰かの“敵”として語ることで、安心を得ていなかったか?」
「“賢くいたい”という欲望のために、誰かを犠牲にしていなかったか?」
そうやって、自分のナラティブの背後にある動機や構造を見つめ直す。
そのとき、初めて、別の視座にジャンプする準備が整う。
選び直しとは、ナラティブの乗り換えだ。
“正解”に辿り着くことではない。
■ 問いを持つことが、再選択の起点になる
「何を信じていたのか?」
「何に依存していたのか?」
「何を見ようとせずにきたのか?」
問いは、選び直すための“灯”になる。
そして、問いを持ち続けることそのものが、構造の外に立つ行為になる。
このとき大切なのは、「自分を責めること」ではない。
むしろ、「構造に巻き込まれていた自分を、静かに観察すること」だ。
そこには羞恥も後悔もあるかもしれない。
でも、それらを“責め”として消費しないこと。
問いとは、自分に課す裁判ではなく、
新しい選択肢を生むための土壌である。
■ 再選択のあとに生まれるもの
選び直したあとに待っているのは、
たいてい、不安定さだ。
かつての安心、かつての物語、かつての居場所――
それを脱したあとの空白には、何も保証されていない。
だが、その不安定さこそが「新しい構造の芽」になる。
見えなかったものが見えはじめ、
耳をふさいでいた声が聞こえはじめる。
再選択のあとに、微細な“ズレ”が生まれる。
それが、構造の中にできた小さな抜け道となり、
他者との新たな関係性を生む道となる。
■ プレイヤーを意識的に選ぶことが、自由への唯一の道
無自覚にプレイヤーであることと、
自覚的にプレイヤーになることは、まったく別物だ。
自覚的にプレイヤーを選ぶとは、
「今、自分がこの立場で語っている」ことを忘れないこと。
その立場をいつでも“降りることができる”ということ。
構造を知り、問いを持ち、
選び直し、もう一度プレイヤーとして立つ。
それは、支配でも正義でもなく、
静かな自由に向かう営みである。
Vol.5|語るという責任
— 言葉は、構造を再生産もできれば、解体もできる -
言葉は構造を再生産もできれば
解体もできる
■ 言葉には、構造を強化する力がある
「誰かを論破する」
「わかりやすく断罪する」
「インパクトのある言葉で、空気を支配する」
――それは一見、理性的で、賢く、鋭く見える。
けれどその言葉が、どんな構造を強化し、
どんな関係性を切断し、
どんな沈黙を生み出しているのかを
私たちは、ほんとうに見えているのだろうか。
言葉は、構造そのものである。
言葉によって世界は記述され、
言葉によって現実は“分けられる”。
だからこそ、語ることには責任がある。
■ 「語る自由」は、「語らない自由」とセットであるべき
沈黙することには、勇気が要る。
特に、語れば優位に立てるとき、
語れば喝采を浴びるとき、
語れば「正しさの陣営」に加われるとき。
それでも語らないという選択には、
構造を消費しないという意志が含まれている。
語る自由は、沈黙の自由と表裏一体である。
そのどちらも持てるとき、初めて“言葉”は責任ある行為になる。
■ 語りは、「構造に加担する営み」でもある
たとえば、SNSで流れる「強い言葉」に乗っかるとき。
たとえば、誰かの過ちを“わかりやすく切る”とき。
その言葉の選び方、使い方は、どこかで構造を強化しているかもしれない。
無意識のうちに「プレイヤー」として加担していないか?
あるいは、「語ること」で誰かを“静かに排除”していないか?
語るとは、「どの物語を支援するか」を選ぶことでもある。
■ それでも、語ることをやめてはいけない
語らなければ、存在しないことになる現実がある。
語らなければ、共有されない苦しみがある。
語らなければ、変わらない構造がある。
語るとは、痛みを差し出すことだ。
沈黙を破る責任でもある。
だから、語らなければならない。
それは“戦うため”ではなく、
“問いを差し出すため”であるべきだ。
■ 「語ること」そのものを問い続ける態度
問いは、語ることの暴走を止めるブレーキになる。
「その言葉は、誰かを黙らせていないか?」
「その語りは、どの構造を再生産していないか?」
「語ること自体が、快楽や支配になっていないか?」
この問いを持ち続けることが、
語るという行為を“構造の外”につなげていく。
語りとは、本来、関係性を結び直すためのものである。
■ 語り直すことが、未来を編み直すことになる
語り直すことは、選び直すことでもある。
構造に無自覚に巻き込まれて語っていた過去を、
静かに見つめ直し、
新たな言葉で、もう一度語る。
それは「やり直し」ではない。
“未来を編み直すための現在”である。
語る責任とは、
自分自身の過去に向き合いながら、
構造の罠を超えて、次の物語を編み始める態度なのだ。



