《 問いを扱うコンサルタント 》
- 行動ではなく、構造を問う -
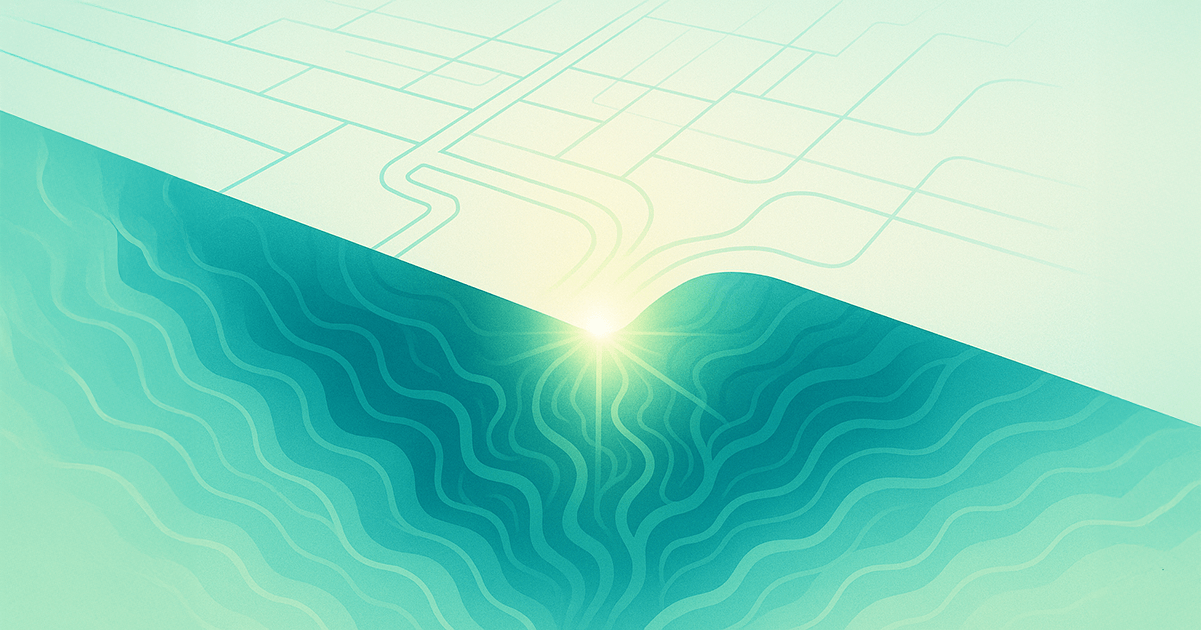
プロローグ:
問いを扱う営みを説明すると、たいてい「コーチングですか?」と尋ねられる。
確かに外から見れば似ている。問いを投げ、答えを引き出す構造だけを切り取れば、区別はつきにくい。
しかし、銀座スコーレが焦点にしているのは、行動や成果ではなく、その手前にある前提や構造だ。
同じ問いでも、刺さる層が違えば、残るものも変わる。
この違いをどう伝えるか――その試みが、このコラムである。
Vol.0|よく聞かれること
— 社会的イメージ -
■ コーチングですか?
銀座スコーレの活動を説明すると、必ずといっていいほど「コーチングですか?」と尋ねられる。問いを投げる、対話する――その表面的な構造は、確かにコーチングと重なって見える部分がある。
■ カウンセリングに近い感覚
実際には、自分の感覚としてはカウンセリングのほうに近い。相手の中にある思いや経験を扱うからだ。
ただ、カウンセリングの領域とも一致しない。立ち位置を明確にするのが難しく、説明のたびに戸惑うことがある。
■ なぜ混同されるのか
では、なぜ「コーチング」と見えてしまうのか。問いを扱う営みはすべて同じ枠に回収されやすい。
そこには「問い=コーチング」という強い社会的イメージがある。外から見れば、相手に問いを投げ、答えを引き出そうとする姿は同じに見える。だから混同が起きる。
次章で、その混同の背景を見てみたい。
Vol.1|混同される理由
— 見た目と期待 -
■ 「問い=コーチング」という思い込み
日本では「問いを投げかける対話」と聞くと、多くの人がまずコーチングを思い浮かべる。企業研修や自己啓発の文脈で広まった結果、「問いを使う=コーチング」という図式が定着している。だから、問いを扱う営みはすべてコーチングに見えてしまう。
■ 外から見れば似ている構造
コーチングも銀座スコーレも、答えを教えるのではなく、相手の内側から引き出す点では共通している。支援の構造だけを取り出せば同じように見えるため、違いが見えにくくなる。だが、実際に扱っているものの深さや方向性はまったく異なる。
■ 期待されている役割の影響
依頼する側が「問題解決」や「行動改善」を望んでいるとき、問いを使う営みは自然とコーチングのイメージに重ねられる。実際のやりとりよりも、社会的に広まったラベルが強く働くためだ。混同はその延長で起きている。
■ ファシリテーターとの重なり
「滞っているプロセスを促す」という点では、ファシリテーターとも似て映る。会議やワークショップの進行役として問いを投げる姿は広く知られているからだ。だが、そこには「進行を整える問い」と「構造そのものを探る問い」という違いがある。
外から見れば、コーチングやファシリテーションと重なって見える部分がある。
だからこそ混同が生まれる。
次の章では、その表面的な共通点を超えた「決定的な違い」を整理してみたい。
Vol.2|決定的な違い
— OSという層 -
■ 扱う“層”が違う(行動 → 構造)
一般的にコーチングは、目標や行動、成果といった領域を扱うものと理解されることが多い。
銀座スコーレが焦点にしているのは、それらの手前にある前提や価値観、組織や個人を動かす,“パラダイム”や“思考の癖”と言い換える事もできる「OS」。
同じ問いを投げかけているように見えても、刺さっている階層が違う。
■ ゴールの設計が違う(達成 → 自覚と再定義)
コーチングは「目標を明確にし、行動へつなげること」が重視されやすい。
一方、銀座スコーレの営みは、選択がどこから生まれているのかを自覚し、その基盤を再定義することにある。
結果として行動は変わることもあるが、狙いは行動そのものではなく「選択の由来」を意識化することに置かれている。
■ 時間の効き方が違う(即効 → 換装後、更新の連鎖)
コーチングは、セッション直後の行動変化につながることが多い。
銀座スコーレでは、問いがその後も残り続ける。無自覚の前提に気づくと、いままで当たり前だと思っていた立脚点が揺らぎ、相手との齟齬に目が向く。
そこから「自分を疑う力」が働き、自然とエンパシーが育っていく。
その往復の体験を通じてOSが換装され、そこから先は更新として重なっていく。
■ ファシリテーターとの違い(個人の滞りを扱う場合)
ファシリテーターは一般に、場や集団の合意形成や意思決定を前進させる役割として理解されている。
銀座スコーレの営みは、前進を大切にしながらも、同時に「なぜ今ここで止まっているのか」に意味を見出す。
滞りの背景にある構造を探ることも欠かせない部分になっている。
■ コンサルタントとの違い(解を与えるか、構造を問うか)
コンサルタントは一般的に、課題を外部から分析し、解法や施策を提示する役割として理解されやすい。
銀座スコーレは、答えを与えることよりも「なぜその課題が現れているのか」を問い直し、OSそのものに立ち返る。
解は外から輸入されるのではなく、自らの基盤から立ち上がるものとして扱われる。
■ 成果の見え方(手触りの差)
カウンセリングやコーチングでは、具体的な行動計画や目標達成の道筋が成果として残ることが多い。
銀座スコーレで残るのは、そうした「形のある成果」ではない。
むしろ、「無自覚(暗黙)の前提に気づいたこと」や「意思決定の基準が変わった実感」といった感覚だ。
ときには言葉になるが、あえて形にせず、そのまま問いや気づきとして持ち帰ることもある。
その柔らかさこそが、この営みの特徴といえる。
■ 銀座スコーレという営み
銀座スコーレの営みは、行動や成果を直接変えることではない。焦点にしているのは「選択に自覚的であるかどうか」。
- その選択は、自分を自分たらしめる“掟”や純度の高い欲求から来ているのか。
- それとも、外的な刺激や環境への反応なのか。
どちらを選んでも構わない。
ただ、その選択に自覚を持てるかどうかが重要になる。
無自覚の前提に気づくことでOSが換装され、そこから更新が重なっていく。すべての解は暫定的であり、気づきのたびに選択肢の並び自体が変わっていく。
その繰り返しの中で、少しずつ「自分」という輪郭が鮮明になっていく。
これが銀座スコーレの営み。名前をつけて説明しきるものではなく、問いを通じて続いていくプロセスそのものだ。
Vol.3|比喩で示すなら
— 選択肢の並び -
■ ナビと地図のちがい
コーチングを「ナビゲーション」にたとえるなら、銀座スコーレは「地図そのもの」に近い。
ナビは、既に描かれた地図の上で、最短経路や効率的なルートを示してくれる。目標地点が決まっていれば、そこに至る方法をわかりやすく案内してくれる。
銀座スコーレの営みは、そもそもの地図を描き直すことに近い。
どの道を選ぶのか以前に、「いま自分はどんな地図を生きているのか」「その地図には、どんな前提や境界線が刻まれているのか」を問い直す。
ときには、これまで存在しなかった道が浮かび上がることもある。
■ 道案内と土台の違い
ナビは進む方向を教えてくれる。地図の描き直しは、世界そのものの見え方を変える。
同じ景色を見ていても、どんな地図を持っているかによって、選択できる道や見えてくる目的地はまったく違ってくる。
■ 選択肢が更新されるということ
銀座スコーレの営みは、「選択をどう進めるか」を支援するのではなく、「どんな選択肢がテーブルに並ぶのか」自体を問い直す。
気づきが生まれるたびに地図が更新され、これまで見えていなかった、若しくはこれまで選ぶことのなかった選択肢のカードが新たに置かれていく。
そのとき、行動は自然に変わる。変化を生むのは、方法論ではなく、基盤となる地図そのものだ。
Vol.4|銀座スコーレ
— 構造を問い、OSを換装する -
■ 銀座スコーレという名の営み
ここまでの流れで、銀座スコーレが「コーチング」や「カウンセリング」「ファシリテーション」と同じ枠には収まらないことを見てきた。
では、それは何なのか。ひとことで言えば「銀座スコーレ」という営みそのものだ。
■ 名前の背後にある意図
問いを扱う営みは、成果や行動を直接動かすことではない。無自覚の前提を掘り起こし、そこに自覚を宿すことでOSが換装される。
そのあとで更新が重なり、選択の基準が少しずつ変わっていく。
その過程をまるごと包む名前として「銀座スコーレ」がある。
■ 関わりしろとしての銀座スコーレ
ここにあるのは完成したモデルではなく、問いを通じて動き続ける場だ。手に取ってみたくなる「関わりしろ」としての営み。
方法論を学ぶのではなく、選択の由来を自覚し、OSを換装していく体験そのものが、銀座スコーレの核にある。
普通のコンサルタントが「解を提示する」役割を担うのに対し、銀座スコーレは「解が生まれるOSそのもの」を扱う。課題や答えの前に、問いと構造に立ち返る営みとして存在している。
銀座スコーレは、問いを通じてOSを換装する営みだ。
その営みは、ここに触れる一人ひとりの選択の中にも立ち上がっていく…



