《我関せず、のち晴れ 》
- 「正しさ」の影に潜む、静かな圧力 -
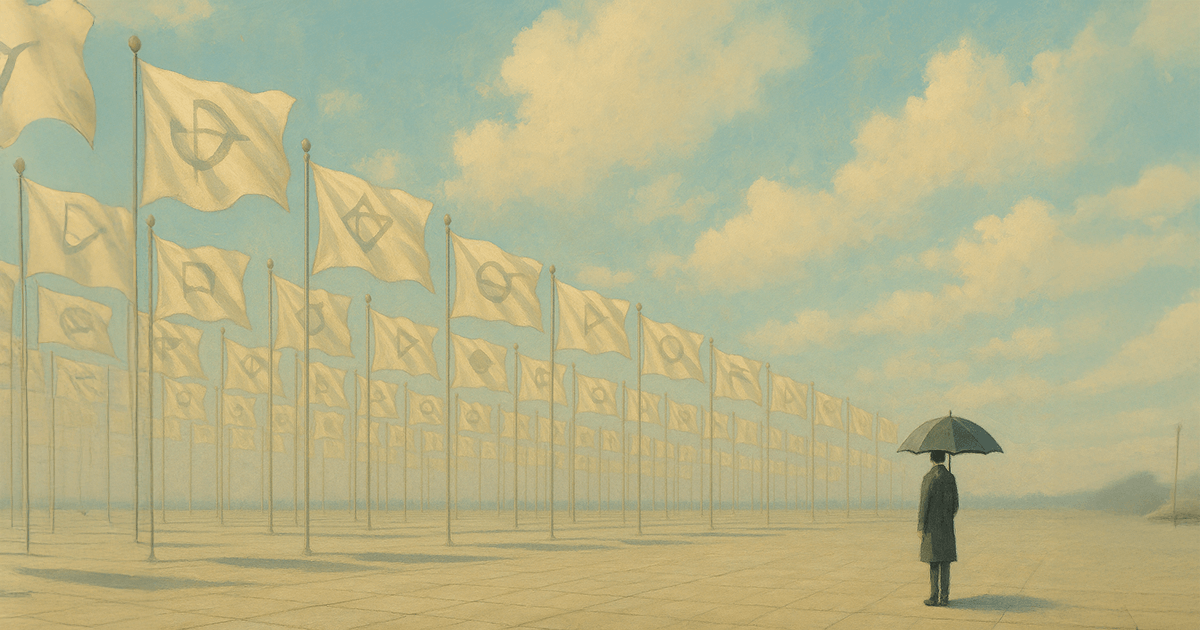
プロローグ:
「それ、いいですね」と共感を示しながらも、胸にざわつきを覚える瞬間がある。
古い正解を手放したつもりが、気づけば新しい正解に縛られている。
善意から滲み出す「こうあらねば」の空気は、知らぬ間に他者の自由を奪うこともある。
だからこそ問いたい。選ばない自由、関わらない自由もまた、確かな選択肢ではないか、と。
Vol.0|違和感は繰り返される
— 新しい正解 -
ある日、SNSを眺めていたら、目に留まった投稿があった。
ざっくり言えば、こんな主旨だった。
「うちはもう、お客様との飲み会や会食は一切やってません。」
「毎月の経費、ほぼゼロで回してます。」
「レジ袋もレシートも断ってる。“無駄”を持たない暮らしが心地いいんです。」
—たしかに、ひとつの考え方としては、わかる。
だけど、なぜか胸の奥がざわつく。
言葉にはできないけれど、どこかで感じたことのある“違和感”だ。
■ 「脱・正解」の顔をした、新しい正解主義
この違和感の正体は、おそらくこれだ。
「旧来の正解主義」を否定しながら、別の形の“正解”を打ち立てている構図。
「こうすべき」という明文化された指針はなくとも、
「これが自然でしょ?」「こっちが誠実でしょ?」という空気が、
やんわりと、しかし確実に他者を包み込んでいく。
古い価値観の押し付けがダメだということは、みんな分かってきている。
でもその反動として、「新しい正しさ」を作りたくなる衝動もまた、人間の性なのかもしれない。
それが、
「経費を使わない私は自立している」
「ポイントカードを持たない私は損得に支配されていない」
というかたちで表出すると、
知らぬ間に、また別の“理想像”を量産することになる。
■ 善意が染み出す、その先にある圧力
厄介なのは、それらが「善意」から発されているということだ。
悪意でも支配欲でもない。
ただ「自分がそうしたら、心地よかった」
「だから勧めたい」—それだけのこと。
でも、ふとした瞬間に思うのだ。
それってほんとうに“自由”なの?
それを採らない人の“自由”は、どこにあるの?
押しつけのつもりはなくても、
共有が過剰になれば、やがて“空気”になり、
空気が定着すれば、それは見えないルールになる。
「自分の選択」を語っているようで、
その語り方が、“他人の選択肢”を閉ざしてしまうことがある。
■ 「正しさ」より、「責任」の方が深い
ぼくは、コロナ禍のときに、そのことを痛感した。
あのとき、ワクチンをどうするかという話題が、世間を二分していた。
打つべきか、打たざるべきか。
善か、悪か。
正義か、愚かさか。
でも、そのどれでもなく、
「自分の人生として、どう選ぶか?」 を、はじめて本気で考えた。
誰かの意見をうのみにするでもなく、
誰かに後押しを求めるでもなく、
「後悔しないかどうか」を軸に、自分で決めた。
そのときはじめて、
「選択に責任を持つ」ということが、
こんなにも自由で、怖くて、静かなんだと知った。
■ 違和感は、次の問いを開く種
だからこそ、感じるのだ。
この静かな違和感が、どこかでまた「新しい檻」になりかけていることに。
それが悪いわけではない。
何かを信じて、選ぶことは大事だし、共感しあうこともあっていい。
でも、その正解の輪の外にいる人たちを、取り残すような語りは、
できれば避けたいと思うのだ。
正しさよりも、責任を。
共感よりも、余白を。
たとえ一人ひとりの選択が違っても、
その違いが、心地よく風に揺れるような社会であってほしい。
違和感は、次の問いを開くための、静かなノックなのかもしれない。
Vol.1|善意のくせがすごい
— 優しさの圧力 -
■ 善意のマントの下で
「あなたのためを思って言ってるんだけどさ」
この言葉の出だしには、だいたい少しの善意と、たっぷりの正しさが混ざっている。
税理士が「小さな会社こそインボイスはチャンスですよ」と言ったとき、
それは職業倫理かもしれないし、親切心かもしれないし、単なる営業トークかもしれない。
でも、受け手がそれを“唯一の正解”として聞き取ってしまったとき、
善意は一気に「信仰」へと変わってしまう。
SNSでよく見かける「本当に豊かに生きるための5つの習慣」なんてのも、
たいていはその人の経験則であって、万人にとっての真理ではない。
でも、その語り口が断定的であるほど、
それを正解と信じたくなる人が現れる。
善意のくせがすごい。
■ 「それが正しい」と信じたい心理
不思議なもので、人は自分の選択に確信が持てないときほど、
他者の選択に口出ししたくなる。
「そうじゃないよ」「こうしたほうがいいよ」
その声の根っこには、
“自分の選んだ道がきっと正しい”という確信が欲しい、
という静かな不安があるように思う。
なぜ、そうなるのか。
おそらくそれは、
自分が選んだことによって得られる未来を、どこかで強く期待しているから。
まだ来ぬ未来に、選択の正しさを委ねているから。
逆にいえば、いまこの瞬間の自分に納得していれば、
他人の選択にそこまで敏感にはならない。
「そういうのも、あるよね」と自然に言える人は、
きっと“自分のあり方”に、ある程度の手応えを持っているのだと思う。
■ 正しさの布教活動
“自分の選択”を“みんなの正解”にしようとするのは、
どこかで安心を共有したいからだ。
それ自体は悪いことじゃない。
ただ、その行動が「正しさの布教」になってしまうと、
途端に“自由”が失われる。
たとえば生活スタイルや子育て論、働き方改革や地方移住。
どんなトピックでも、誰かが語りはじめた瞬間、
それが「理想」として消費されてしまう。
語り手が自信たっぷりであればあるほど、
聞き手はそれを“正解”だと信じたくなる。
でも、よくよく見てみると、
その理想の形が「自分の望む豊かさ」とはまったく違っていた、なんてこともある。
それでも、声が大きければ勝ってしまうのが、
この世界の構造だ。
■ マジョリティの旗の持ち替え
面白いのは、かつてマジョリティの立場にいた人が、
“脱マジョリティ”の旗を掲げるときの力学だ。
「かつての自分は、間違っていた」と語る姿には潔さもある。
けれど、その語りが“新しい正しさ”を生んでしまうこともある。
たとえば都市生活から地方移住した人が、
「本当の豊かさは自然の中にあった」と語る。
それ自体は真実かもしれないし、心からの実感なのだと思う。
でも、それが「地方こそが本来の生き方」となってしまうと、
また別の圧力が生まれてくる。
一周回って、やってることは「元いた場所」とあんまり変わらなかったりする。
ただ、看板が変わっただけ。
■ 「それもありだね」と言える人
本当に自分のあり方に納得している人は、
他人の選択に干渉しない。
「それは違う」とも言わないし、
「こっちが正しい」とも言わない。
ただ、「それも、ありだね」と静かに言うだけ。
それって、ものすごく勇気がいることだと思う。
自分を信じつつ、他人の選択も尊重するという姿勢には、
内側の成熟がいる。
でも、私たちはコンサルティングという場に立っていると、
そうも言っていられないことがある。
相手の無自覚な前提を指摘せざるをえない時、
“自分の選択を押し付けてしまうかもしれない”というジレンマが生まれる。
「それもありだね」と思っていても、
同時に「ここは見ておいた方がいいですよ」と言いたくなる。
■ 盟友との対話
ここで登場するのが、“盟友”の存在だ。
アーノルド・ミンデルの言うところの、厄介者でもあり、力でもある存在。
曖昧さのなかに留まりつつも、必要なときには輪郭を立てる。
そのとき、ふと現れては、破壊的なまでの明晰さをもたらす。
ときに鋭く、ときに苦々しい真実を突きつける。
この“盟友”は、自分の中にある“エッジ”——越えづらい境界を知らせてくれるし、
相手がどこで立ちすくんでいるのかにも気づかせてくれる。
つまり、ただの鋭さではない。
ただの優しさでもない。
あくまで、その場に必要な“明晰さ”を連れてくる存在。
僕たちは、この“盟友”を恐れずに、ちゃんと仲間として迎え入れる必要があるのかもしれない。
善意と正しさの狭間で、揺れるその場に、ほんの少しの深呼吸とともに。



