《 読みかえるこころ 》
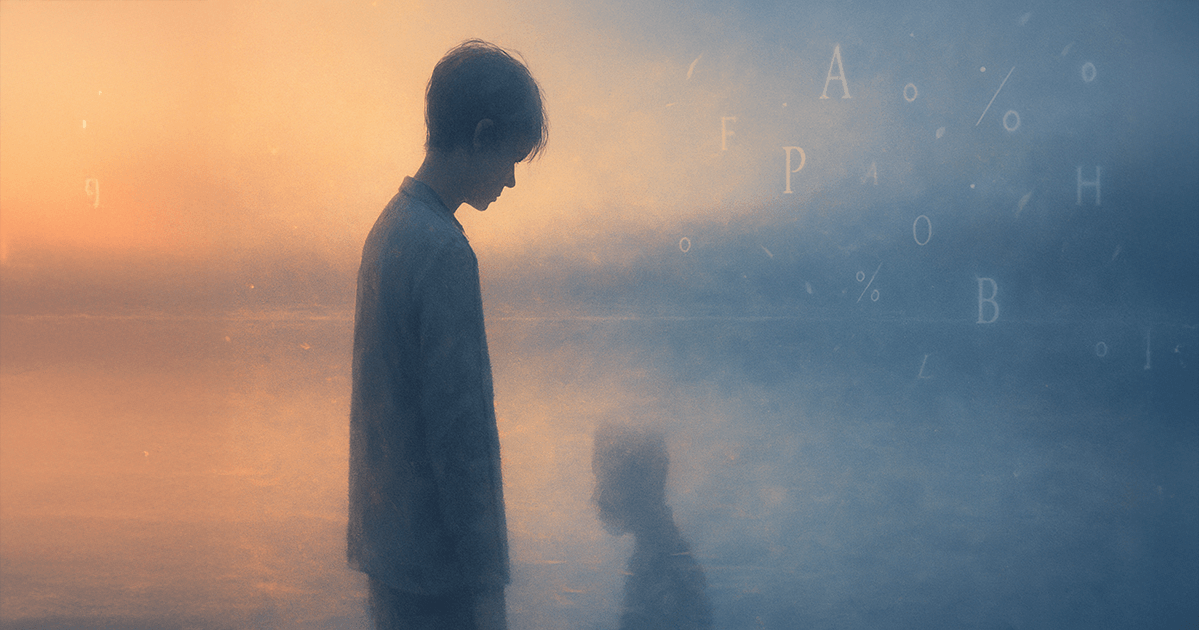
プロローグ:
感情は、いつも正体を隠してやってくる。
不安とときめき、恐怖と興奮。
どれも同じように身体を震わせるのに、
私たちはそこに名前をつけたがる。
とはいえ、本当に“それ”は、不安だったのか?
この連載では、そんな問いを手がかりに、
身体と心のあいだにある微細な回路をたどってみる。
それは、感じたままを信じ込まず、
そっと“読みかえてみる”という試み。
ささやかな実験とともに、
「感じること」の奥を覗いていく旅のはじまりである。
※ご注意ください
ここで紹介している内容は、あくまで個人の体験をもとにした思考と試みのひとつです。
医学的な根拠や治療的な効能を保証するものではありません。
心臓や呼吸器、脳血管などに不安のある方、また通院中の方は無理をせず、専門医の判断を優先してください。
体はいつも、あなたに何かを伝えようとしています。
その声に、丁寧に耳を澄ませながら進めてください。
Vol.1|ドキドキは、どこから来るのか?

■ その鼓動は、何を告げているのだろうか?
緊張しているとき。
誰かを強く思っているとき。
あるいは、恐怖に包まれているとき。
どれも心臓は、同じように脈を打つ。
ドキドキと、高鳴る。
不安も、ときめきも、興奮も、
すべてが似たような身体反応を伴うとすれば――
私たちはそれをどうやって「不安だ」と判断しているのだろうか。
身体の反応はひとつ。
だが、その解釈は複数存在するのではないか?
■ 夢が語るのは、身体の状態かもしれない
かつて、毎晩のように悪夢を見ていた時期があった。
目が覚めると、全身が汗で濡れており、心臓は荒々しく脈を刻んでいた。
だが、ある朝ふと思ったのだ。
「悪夢を見たから心拍が上がった」のではなく、
「心拍が先に上がっていたから、
その状態に辻褄を合わせるように、脳が悪夢を描いた」のではないかと。
私たちは、出来事に意味を与えるために「物語」をつくる。
その物語が、もしかすると身体の状態を“解釈”しているのだとしたら。
感情とは、身体の後追いで編まれるフィクションなのかもしれない。
■ 感情を書き換える、身体の回路
不安でたまらないとき、私はよく試していたことがある。
深く息を吸い、止める。
両手を握りしめ、顔も脚も腹も背中も、全身に力を込める。
そして、限界まで力を入れたのち、息を吐きながら一気に力を抜く。
その瞬間、心拍数はさらに跳ね上がる。
だが、不思議なことに不安は静かに退いていた。
まるで「この心拍は、不安のものではない」と、
身体が新しい解釈を脳に提示してくれたようだった。
同じ“ドキドキ”でも、
それが何を意味するのかは、どうやら選べるらしい。
■ そっと触れてみるための小さな方法
以下は、私が繰り返し試していたやり方である。
もしよければ、静かな場所でそっと触れてみてほしい。
- 深く息を吸い、止める。
- 手足、腹、肩、顔……全身に意識的に力を入れる。
- 数秒保ったあと、ゆっくり息を吐きながら一気に力を抜く。
- そのまま、数秒。
- 身体に起きた変化を、感じてみる。脈。呼吸。胸の奥。
これは「正解」を求めるための動作ではない。
ただ、動いた身体がどんな感情を連れてくるのかに、
そっと耳を澄ませるだけである。
■ このドキドキは、敵だろうか? 味方だろうか?
私たちは、心臓の鼓動を恐れるように育ってきた。
「不安だ」と、「緊張している」と、「逃げなければ」と。
とはいえ、心拍の上昇は、必ずしも“敵”のサインではない。
ただ、何かが始まろうとしている身体の準備なのかもしれない。
エンジンがかかるとき、音がするのは当然である。
その音を、「不安」と名づけるか。
あるいは「始まり」と捉えるか。
意味の分岐点は、もしかすると――
こちら側にあるのかもしれない。
今日、あなたの鼓動は何を告げていただろうか。
そのドキドキを、もう一度そっと手のひらにのせてみることはできるだろうか。
Vol.2|こころのBGMが、世界を作る。

■ 同じ風景が、別の物語に聴こえるとき
十数年前、
ある実験をしたことがある。
まったく同じ画像を30枚、同じ順番で表示させ、
2つのアニメーション動画を作り、
ひとつにはバラードを、もうひとつにはポップな曲を
BGMとして流すというものだ。
そして、数人の人にその動画を連続で見てもらい、
画像の印象について尋ねてみた。
「この動画の画像はすべて同じ画像です」
と伝えると、ほとんどの人が驚きの表情を浮かべた。
どうやら、音楽が大きく印象を変えていたのだ。
同じ視覚的な情報であっても、
その背景に流れる音楽によって、
まったく異なる物語を感じ取ったのだ。
■ 内なるBGMが、世界を編みなおす
この実験から、ひとつの仮説が浮かび上がった。
私たちは、世界という“同じ風景”を、
心の中で鳴っている音楽を通して
読み替えているのではないか?
視覚や触覚といった五感から得る情報も重要だが、
そこに流れる音、つまり内なるBGMが、
私たちの解釈や感情に大きな影響を与えているのだ。
逆境に直面したとき、
心の中でどんな音楽が鳴り響いているだろうか?
その音楽こそが、
私たちの体験を形作る土台となるのではないだろうか。
■ 逆境の中のメロディー
考えてみてほしい。
不安で胸がいっぱいのとき、
頭の中で流れているのは、どんな曲だろうか?
心が焦り、恐れが忍び寄るとき、
その“音楽”は、私たちをどんな世界へと連れて行くのだろうか?
たとえば、何かがうまくいかないときに流れる音楽が、
重たいバラードだとしたら、
どこかで絶望感を引き寄せてしまうことがあるかもしれない。
もしも、内側で流れている音楽が、
悲壮感を増幅させるようなものだとしたら、
視界に映る現実もそれに合わせて、
どんどん暗く、厳しく感じられるだろう。
でも——
ひょっとしたら、その音楽を少し変えるだけで、
状況をまったく違うものとして
捉え直すことができるかもしれない。
■ 心のBGMを、意図的に変えてみる
逆境の中でも、“音楽”を意識的に変えてみることで、
状況そのものが変わり始めるという実験を、ぜひ試してみてほしい。
たとえば、どうしても感情的になってしまう場面で、
思い切って「アホな曲」を流してみる。
たとえば、映画のエンドロールのような、
感動的だけど少しおちゃめなポップソングを、
頭に浮かべてみるのだ。
その曲が心に流れ始めたとき、
あなたは少しだけ軽くなり、
少しだけ笑顔を浮かべてしまうかもしれない。
内側で流れる音楽を、どうチューニングするか。
それは、あなたの“世界の読み替え”の手段となる。
■ 今日の一場面に、どんな音楽を重ねるか
いま、あなたが直面している一場面に、
どんな音楽を重ねるだろうか?
少しだけ、普段とは違う音楽を、
意識的に思い描いてみてほしい。
その音楽があなたの感情に、
どんな変化をもたらすのか、感じてみるのだ。
もしそれが、何かの挑戦や逆境であれば、
その状況を少しでも軽やかにする“音楽”を選んでみるのだ。
あなたの心の中で鳴る音楽こそが、
あなたが世界をどう見ているかを決定づける、
重要な要素である。
その音楽を、少しだけ意識的に書き換えてみることで、
あなたの一日はきっと、新しい色を帯びるだろう。
■ あとがき
感情はコントロールできないもの、
そう思い込んでいたのかもしれません。
ですが、そこに流れる“音楽”の存在に気づいたとき、
わたしたちは少しだけ、その感情との関係を変えられるのかもしれません。
落ち込んだ日に、頭の中にあえてユーモラスな曲を流してみる。
緊張の場面で、壮大なオーケストラを重ねてみる。
そんなささやかな選曲が、世界の見え方を静かに変えていきます。
感情は止められなくても、
その“BGM”を選びなおすことなら、今日からでもできるのです。



